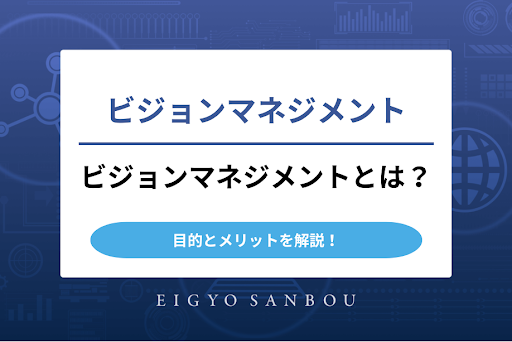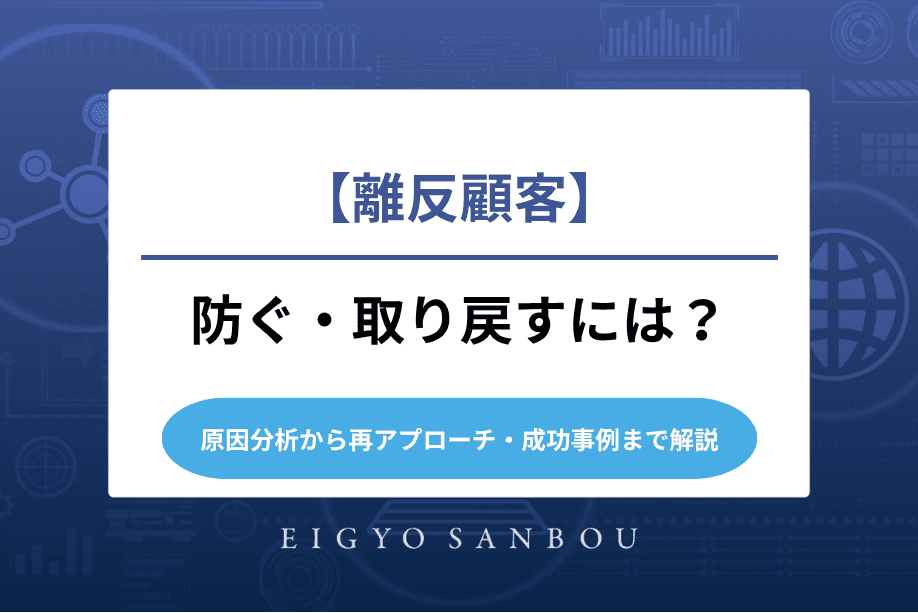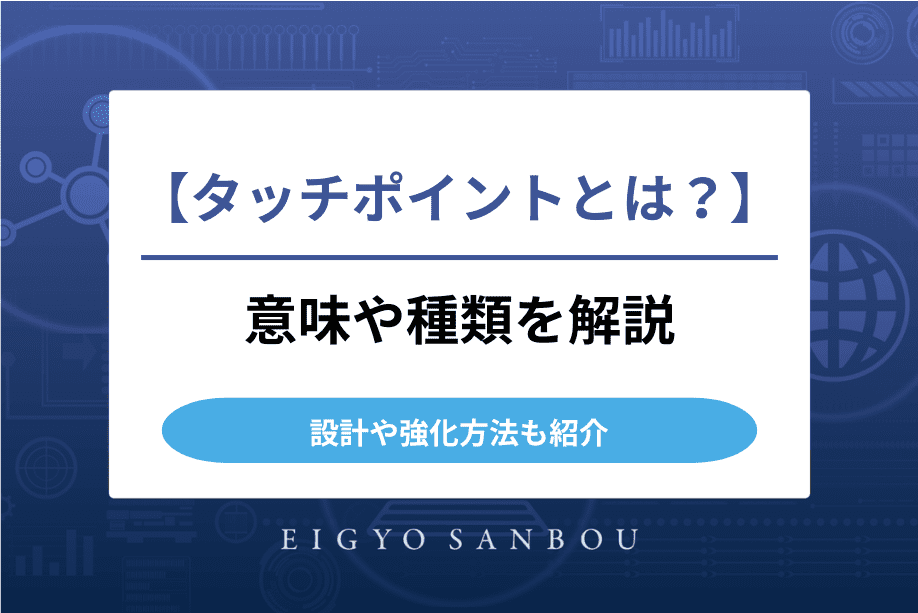「誰に向けて、どんな価値を届けるか」を明確にするペルソナ設定は、マーケティング活動において重要な役割を果たします。商品やサービスの魅力を最大限に伝えるには、相手を具体的に思い描いたうえで戦略を練る必要があります。
しかし、ただ人物像を想定するだけでは不十分で、情報の収集・分析・表現方法にも工夫が求められるのです。
本記事では、ペルソナ設定の基本から実践的な手順、導入する際のメリット・デメリット、さらには注意点までを体系的に解説します。初めて取り組む方にもわかりやすいよう、ステップごとに整理してお届けします。
▶︎貴社の事業成長を営業の側面からサポートするパートナーサービス『営業参謀』についてはこちら
営業でお悩みのことありませんか?
目次
「ペルソナ設定」とは

マーケティング活動で顧客の理解を深め、施策の精度を上げるためには、ペルソナ設定の考え方が欠かせません。
ここでは、ターゲットとの違いや、避けるべき相手を明確にする「ネガティブペルソナ」についても詳しく見ていきましょう。
ターゲットとペルソナの違い
ターゲットとペルソナは、どちらも顧客を理解する手段ですが、指す内容には明確な違いがあります。
ターゲットは、年齢や性別、職業などの属性情報をもとにした「グループ像」です。たとえば「30代・女性・会社員」といったように、広い範囲で層を捉える傾向があります。
一方、ペルソナはそのグループ内に存在すると想定される“ひとりの人物”を深く描き出すものです。日々の行動、価値観、悩みや欲求といった心理的な要素にまで踏み込むため、リアリティのある顧客像を作り上げられます。
この違いを理解することで、訴求力のある施策設計が可能になります。ターゲティングスキルや顧客層の選定に関しては、以下の記事もあわせてご一読ください。
営業ターゲティングスキル:効果的な顧客層選定と売上余地の発見
ネガティブペルソナとは
ペルソナと聞くと、理想の顧客像を描くイメージが強いですが、実は「ネガティブペルソナ」も戦略的に重要な考え方です。これは、自社のサービスと相性が悪いと予想されるユーザー像を指します。
たとえば、価格ばかりを重視して価値を見出してくれない人や、サポートコストが過剰にかかる利用者などが該当します。あらかじめ対象外とする人物像を明確にすることで、本当にアプローチすべき層に集中でき、マーケティングの無駄を省けるのがメリットです。
理想の顧客像と同時に、関係を深めるべきでない相手の線引きも意識することが、成果を高める第一歩といえるでしょう。
関連記事:ABM(アカウントベースドマーケティング)導入で売上アップ!7つのメリットを徹底解説
ペルソナ設定はなぜ重要なのか?

ペルソナを丁寧に設計することで、施策の軸がぶれにくくなり、部門間の連携やユーザー理解が格段に深まります。ここでは、マーケティングや開発、商品設計における重要性を3つの視点から見ていきましょう。
マーケティング施策の成果を高めるため
マーケティング施策を展開する際には、誰に向けて発信しているのかを明確にすることが成果に直結します。漠然としたターゲットでは、訴求の方向性があいまいになりがちです。
そこで、具体的なペルソナを想定することで、広告のメッセージやクリエイティブの表現に一貫性が生まれ、共感を得やすくなります。
また、ペルソナの感情や行動を起点に施策を組み立てれば、より強いインパクトを与えることが可能です。見込み客に響く表現や接点を明確にするうえで、ペルソナは欠かせない存在といえるでしょう。
関連記事:ペルソナ設定と関連深いフレームワーク6選|活用場面やポイント
開発チームでの共通認識を促進するため
商品やサービスの開発現場においても、ペルソナの共有は大きな意味を持ちます。たとえば、エンジニアやデザイナーがそれぞれ異なる利用者像を前提に設計を進めてしまうと、仕上がったプロダクトに整合性がなくなりやすい傾向があります。
認識のズレを防ぐためにも、ペルソナによって「どのような人が、どう使うのか」を具体的に描き、全メンバーが共通理解を持つことが重要です。共通の視点を持つことで、チーム全体が顧客志向にそろい、一貫したユーザー体験の構築につながっていきます。
ユーザーのニーズに応えるサービスを実現するため
市場で求められるサービスを生み出すには、表面的な属性情報だけでなく、ユーザーの内面に踏み込んだ理解が必要です。ペルソナ設定を通じて、価値観や生活スタイル、悩みや期待まで掘り下げることで、ニーズに沿った機能や体験を設計しやすくなります。
さらに、利用シーンを想定した設計が可能となるため、ユーザーが本当に必要としているポイントに焦点を当てたプロダクト作りが実現します。見えにくい本音に近づくほど、満足度の高いサービス提供が可能になるでしょう。
ペルソナ設定のメリット4選
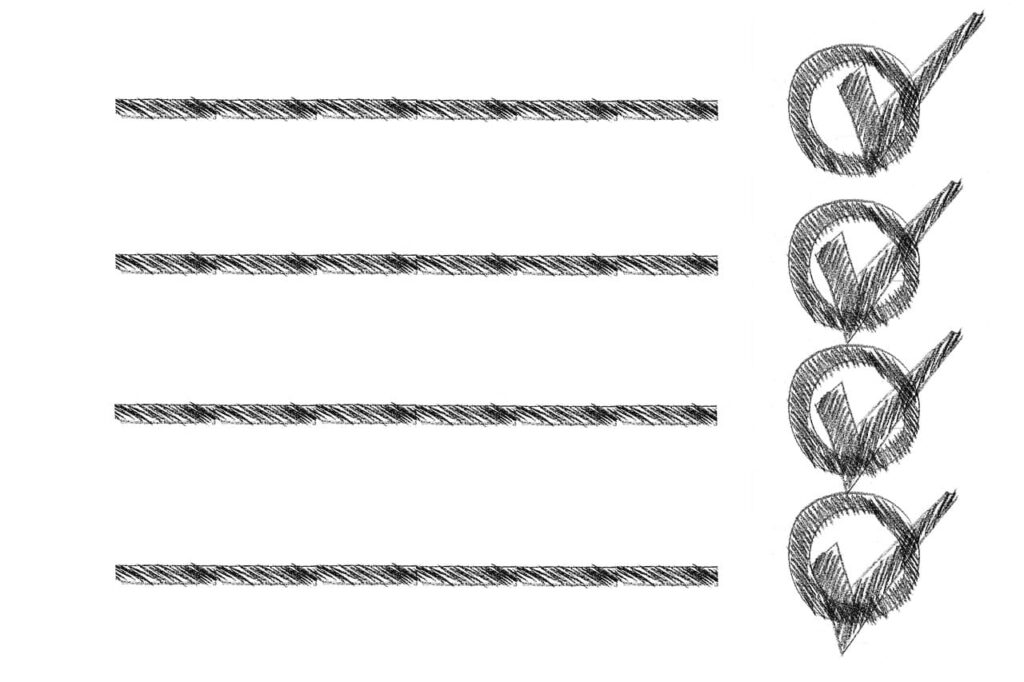
明確なペルソナを持つことで、顧客理解の深度が増し、戦略全体の質が向上します。ここでは、マーケティングやチーム運営の実務において特に実感しやすい4つの利点を紹介します。
ユーザーのニーズを把握しやすくなる
ペルソナを設定することで、単なる属性情報にとどまらず、価値観や日常の行動パターン、抱えている悩みにまで目を向けることができます。たとえば「忙しいワーキングマザー」ではなく、「朝は子どもの支度でバタバタし、買い物はスマホで手早く済ませたい母親」といった具体像に落とし込むことで、潜在的なニーズが浮かび上がります。
このような深掘りが可能になるため、ユーザーが求める商品や情報に対する理解が進み、提案の質も高まっていくのです。
関連記事:セールスコピーとは?売れる仕組みと営業戦略をつなぐ方法を解説
効果的な広告に絞り込める
誰に向けた広告なのかが曖昧だと、訴求内容もぼやけてしまいます。
しかし、具体的なペルソナがあることで、届けるべきメッセージや伝え方が明確になります。たとえば、価値を重視する層に向けては機能説明よりもレビュー重視の訴求が有効だったり、スピード感を求める相手には即効性を前面に押し出す広告が適していたりします。
的確なターゲティングによって、無駄な広告費を抑えながら反応率の高い広告運用が実現しやすくなります。
マーケティング戦略を最適化できる
戦略立案の際に、どのチャネルを使うべきか、どのタイミングでアプローチすべきかといった選択に迷うことは多いものです。
そこで活躍するのが、具体的に描かれたペルソナです。想定した人物の生活スタイルや情報収集の方法に基づいて戦略を組み立てれば、より実態に即したプランニングが可能になります。
加えて、効果測定の際も「このペルソナには何が響いたのか」という観点で振り返ることで、改善のスピードと精度も高まっていきます。
チーム内で認識を共有できる
関係者の間で理想顧客像にズレがあると、施策の方向性がぶれてしまいます。ペルソナを活用すれば、共通の顧客像を可視化できるため、チーム全体が同じ基準を持って動けるようになります。
とくに、企画・開発・営業など複数部門が連携するプロジェクトでは、誰のためにサービスを作っているのかを共有しておくことが極めて重要です。ペルソナは、その基盤となる「共通言語」の役割を果たしてくれるのです。
ペルソナ設定のデメリット3選

効果的な戦略立案に役立つ一方で、ペルソナには落とし穴も存在します。導入前に知っておきたい3つの注意点を確認しておきましょう。
時間やコストがかかる
ペルソナ設定は、想像でつくるだけでは意味を成しません。実際の顧客の声やデータを集める必要があり、そのためには調査やインタビューといったプロセスを経ることになります。とくに初めて取り組む場合は、どのような情報をどの粒度で集めれば良いか迷うことも多く、結果として手間や費用がかさみがちです。
社内リソースが限られている場合には、他の業務とのバランスも考慮する必要があり、導入をためらってしまう要因となることもあるでしょう。
実際のユーザーとずれている可能性がある
どれだけ丁寧に作り込んだとしても、設定したペルソナが実際の顧客像と完全に一致するとは限りません。思い込みや先入観に基づいて描いた人物像が、マーケティング施策を誤った方向に導いてしまうケースもあります。
また、データを集めた時点の顧客像が、その後の市場変化に伴ってずれていくこともあるため、ペルソナは常に正解というわけではありません。設計にあたっては、柔軟性を持ちつつ検証と見直しを重ねる姿勢が欠かせません。
ペルソナが固定化されてしまい、変化に対応できない
一度作成したペルソナをそのまま使い続けていると、時代の流れやユーザーの行動変化に対して鈍感になってしまう恐れがあります。とくに、社内でペルソナが“前提”として扱われるようになると、変化を受け入れる柔軟性が失われ、逆にマーケティングの自由度を制限する結果になりかねません。
ペルソナはあくまで「仮説」であることを前提にし、定期的な更新や再構築を行うことが、環境変化に対応した施策運用につながります。
ペルソナの設定方法

効果的なマーケティング施策につなげるには、ペルソナを正しく構築することが大切です。ここでは、実践的な5つの手順を順に解説していきます。
1. 自社や商品・サービスの立ち位置を把握する
ペルソナを設定する前に、まずは自社の強みや市場でのポジションを明確にしておく必要があります。たとえば、競合と比較してどのような価値を提供しているのか、誰に選ばれやすいのかといった視点で整理していくと、自然とターゲットとなる人物像が見えてくるでしょう。
自社の立ち位置を正確に理解することができれば、ペルソナの方向性にも一貫性が生まれ、後続の設定作業もスムーズに進められるようになります。
2. 情報収集をする
リアルなペルソナを作るには、実際のユーザーに関する情報を集めることが欠かせません。アンケートやインタビュー、アクセス解析ツールのデータなど、多角的に調査することで信ぴょう性の高い基礎資料が整います。
仮説だけで進めてしまうと偏った人物像になりかねないため、客観的なデータに基づいてユーザーの実像を捉えることが大切です。現場の営業やカスタマーサポート担当からも意見を集めると、より具体的なニーズや課題が見えてくるでしょう。
顧客分析について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
顧客分析とは?目的、手法、ツールを徹底解説
3. 集めた情報を仕分ける
多くのデータが手元に集まったあとは、整理整頓の工程が重要になります。
- 属性
- 価値観
- 課題
- 行動パターン
など、テーマごとに分類することで、人物像の輪郭が徐々に明確になっていきます。ここでの作業を丁寧に行うことによって、曖昧だったニーズや動機の背景も見えてくるようになります。
収集した情報の断片をバラバラにせず、意味をもたせてグルーピングすることで、次のステップに向けた土台がしっかり整います。
4. ペルソナの形に仕上げる
情報の整理が終わったら、いよいよ具体的な人物像に落とし込んでいきます。
年齢、性別、職業、居住地といった基本プロフィールに加え、ライフスタイルや行動傾向、価値観なども盛り込むことで、実在するようなペルソナが完成します。
単なる統計的な要素ではなく、1人の「人」として描くことがポイントです。ここで深みのある設定ができていれば、施策全体に説得力と一貫性をもたらすことができるようになります。
5. ストーリーとしてまとめる
完成したペルソナを実務に活用するには、単なる情報の羅列ではなく、物語として仕上げる工夫が効果的です。たとえば、「ある平日の朝から夜までの行動」や「サービスと出会ったきっかけ」など、日常のシーンを交えて描くと、より関係者の理解が深まります。
ストーリー化することで、開発や営業の現場でも顧客の視点が持ちやすくなり、チーム全体で共有しやすい形に落とし込むことが可能になります。
落とし込んだうえで、顧客が実際に商品を購入するまでに、どのようなプロセスをたどるのかを検討します。これをカスタマージャーニーといいます。
カスタマージャーニーについては、こちらの記事をご覧ください。
カスタマージャーニーマップの作り方と成功させるためのポイント
ペルソナ設定における3つの注意点

適切にペルソナを活用するには、設定時の盲点にも目を向けることが大切です。ここではよくある3つの落とし穴と、それぞれの対処法を詳しくご紹介します。
収集データの正確性
ペルソナの信頼性は、もととなるデータの精度に大きく依存します。仮説だけで構成された人物像では、実際のユーザー行動とのズレが生じやすく、施策の成果にも悪影響を及ぼしかねません。
たとえば、SNSの声やアクセス解析など、一見有用に思える情報も、断片的で偏りがある場合は注意が必要です。調査対象や質問設計を工夫し、客観性を担保したデータを用いることで、より確度の高いペルソナ設計が可能になります。
根拠ある情報に基づく判断が、信頼性を高める鍵となります。
現実的で具体的なペルソナ設定
ペルソナを作る際に陥りがちなのが、理想像ばかりを追い求めてしまうケースです。たとえば「情報感度が高く、常に最先端のトレンドを把握している20代女性」のように、あまりに理想的すぎる像を描いてしまうと、実際のユーザーとかけ離れた施策になってしまう恐れがあります。
大切なのは、実在しそうな一人の生活者としてのリアリティを持たせることです。現場の声や一次データを踏まえながら、手が届く範囲で想定できる人物像を描くようにしましょう。
定期的に見直す
一度設定したペルソナを使い続けることにはリスクも伴います。市場のトレンドや顧客の価値観は常に変化しており、過去に有効だった前提が現在も通用するとは限りません。
とくに変化のスピードが早い業界では、ペルソナの鮮度が落ちるのも早いため、定期的な見直しが欠かせません。
施策の効果が鈍化してきたと感じたときは、ペルソナの妥当性を再検証するタイミングと考えましょう。柔軟にアップデートを重ねることが、長期的な成果につながります。
まとめ
ペルソナ設定は、マーケティング戦略の精度を高め、チームの方向性を一つにまとめるうえでも有効な手法です。理想の顧客像を具体化することで、伝えるべきメッセージや開発すべき機能が明確になり、施策の質と成果の向上につながります。
ただし、時間や手間がかかる点や、現実とのズレに注意する必要もあります。データの正確性を保ち、定期的な見直しを行いながら、柔軟に活用していくことが重要です。
セールスアセットでは、営業戦略の立案から実行、プロジェクトマネジメントまで網羅したサポートを提供しています。
営業戦略の実行とあわせて、内製化までも支援可能です。
興味を持たれた方は、ぜひ下記よりお問い合わせください。
【貴社の事業成長を営業の側面からサポートするパートナーサービス『営業参謀』の資料のダウンロードはこちら】
これひとつで
営業参謀のすべてが分かる!
BtoB営業組織立ち上げ支援サービスの内容や導入事例、料金プランなど営業参謀の概要がまとめられた資料をダウンロードいただけます。



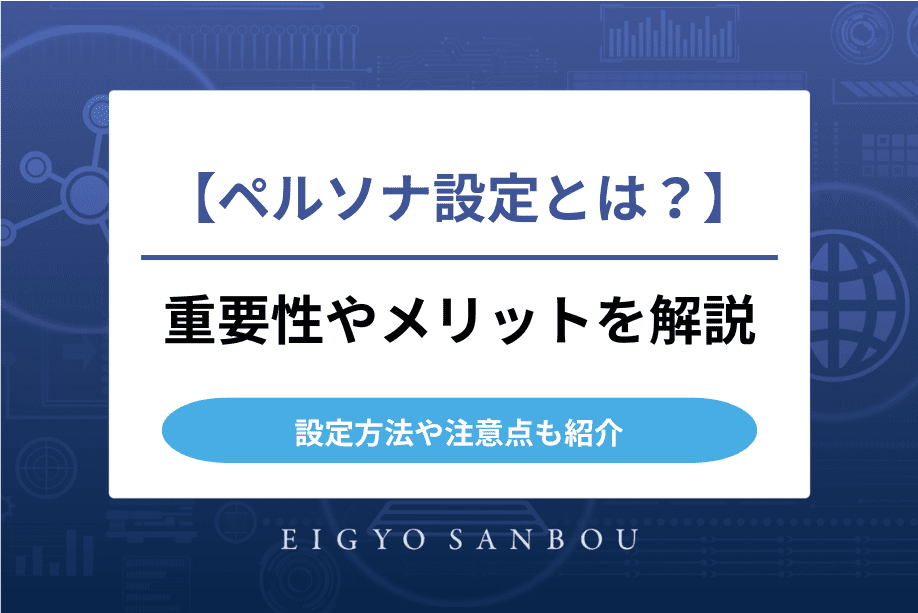
 ツイートする
ツイートする シェアする
シェアする LINEで送る
LINEで送る URLをコピー
URLをコピー