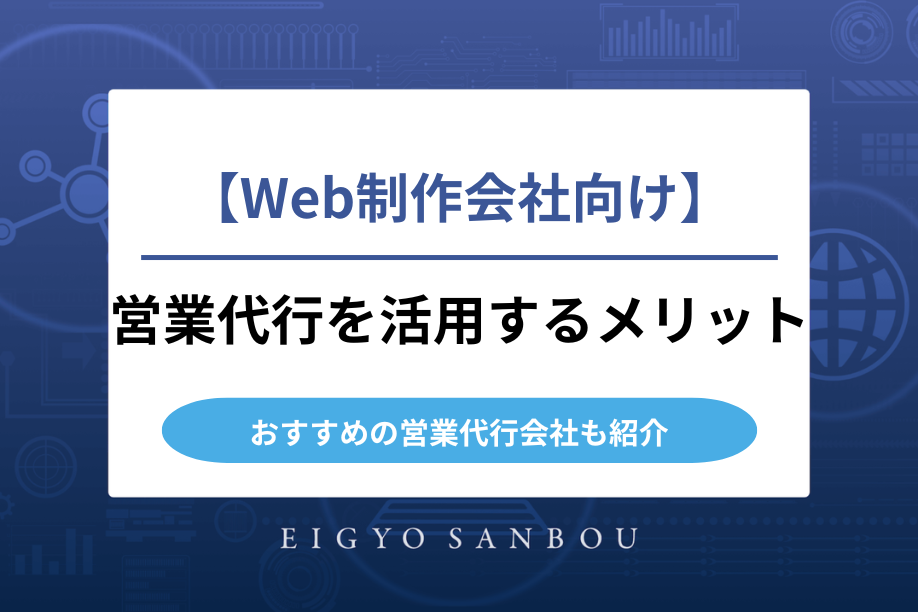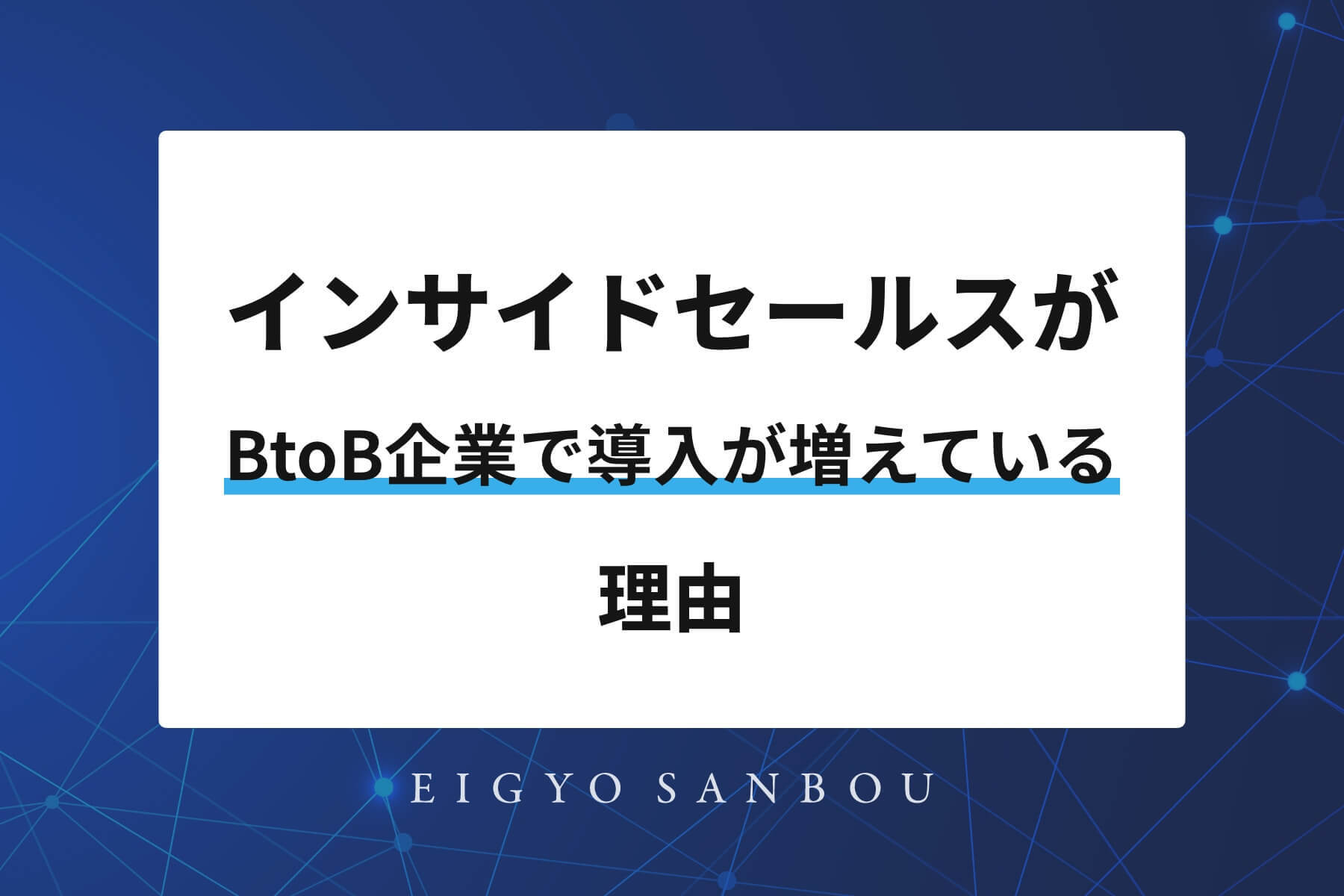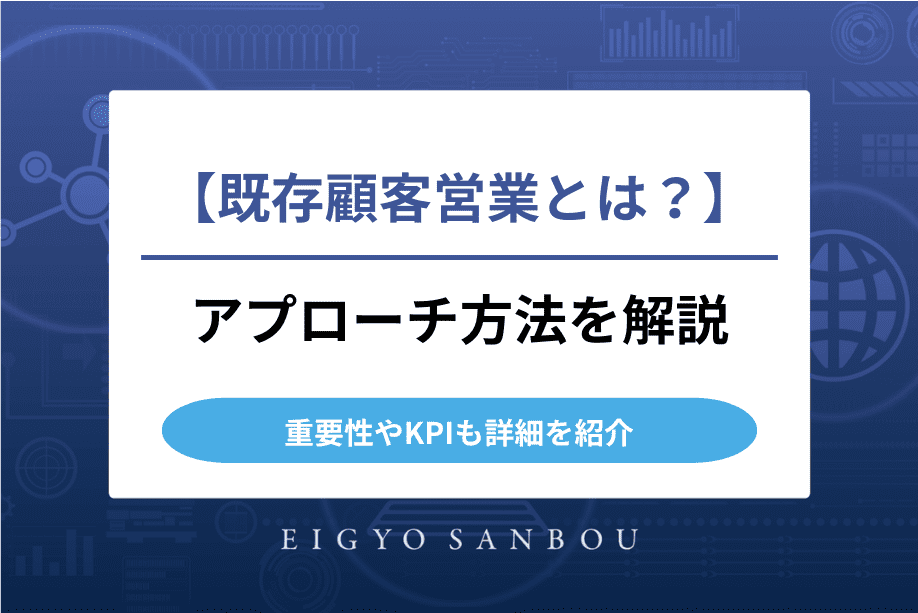業務効率化やコスト削減を目指す企業にとって、アウトソーシングは有効な手段です。経理や総務のような定型業務だけでなく、人事、営業サポート、IT運用など幅広い分野で活用され、リソース不足の解消や生産性向上にも直結します。
成功事例を理解することは、導入効果を最大化するための第一歩です。一方で、丸投げや社内連携不足により期待した成果が得られない場合も存在します。
本記事では、成功と失敗の両面から学び、最適な活用方法を整理します。
▶貴社の事業成長を営業の側面からサポートするパートナーサービス『営業参謀』についてはこちら
営業でお悩みのことありませんか?
目次
アウトソーシング事例を理解する前に押さえる4つの基本ポイント

アウトソーシングを成功させるには、導入前に理解しておくべき基本知識があります。業務を外部に委託する意味や主な種類、人材派遣との違い、さらに適した業務の見極め方を押さえることで、事例を読む際の理解が深まります。ここでは4つのポイントを詳しく見ていきましょう。
アウトソーシングの意味と導入が進む背景を知る
アウトソーシングの導入が加速している背景には、複数の経営課題が存在します。国内の労働力人口は減少傾向にあり、企業は必要な人材を確保しにくくなっています。人手不足が続く状況で、限られた社員に業務が集中すれば、残業や属人化が進み、生産性は低下しやすくなるでしょう。
加えて、事業拡大や新規プロジェクトへの対応には、社内だけのリソースでは限界が生じます。外部に業務を任せることで、専門知識を持つ人材を柔軟に活用し、効率的に業務を進められるようになります。
導入が進むもう一つの理由はコスト構造の改善です。社員を採用して教育するよりも、必要な業務だけを委託するほうが費用を抑えやすい場合があります。人材不足と経営効率化の双方を解決する手段として、アウトソーシングが注目を集めているのです。
関連記事:営業代行の選び方とは?メリットやどこを重視すべきかポイントも解説
BPO・ITO・KPOなどの種類と特徴
アウトソーシングには複数の形態があり、業務内容に応じた選択が必要です。代表的なものとして、BPO・ITO・KPOが挙げられます。
BPOはビジネスプロセスアウトソーシングの略で、経理や総務、人事などのバックオフィス業務を包括的に委託する方法です。標準化された定型作業を効率的に処理でき、企業はコア業務に集中しやすくなります。
ITOはITアウトソーシングの略で、システム開発や運用、インフラ管理などのIT関連業務を外部に委託します。専門スキルを持つ人材を確保しにくい企業でも、最新技術に対応した運用が可能です。
KPOはナレッジプロセスアウトソーシングと呼ばれ、分析や調査、企画など高い専門性が求められる業務を対象にします。複数の形態を理解し、業務特性に合わせて活用することが、成功事例につながる重要なポイントです。
関連記事:ビジネスモデルの作成・分析に役立つ5つのフレームワークを解説
人材派遣との違いと導入の目的
アウトソーシングと人材派遣は、どちらも外部の力を活用する点は同じですが、仕組みと目的は異なります。人材派遣は、派遣会社から社員を受け入れ、社内の指揮命令下で作業を行う形式です。一方、アウトソーシングでは業務そのものを外部に委託し、成果物やプロセスの責任は委託先が負います。
上記の違いにより、求められる社内対応も変わります。人材派遣は短期的な人員不足解消に向くのに対し、アウトソーシングは業務効率化や品質向上を狙った戦略的な施策として活用されます。
導入の目的を明確にしないまま選択すると、期待した成果が得られない可能性があるので、注意が必要です。事例を参考にする際も、委託形態と目的が合致しているかを意識すると理解が深まり、失敗を避けやすくなります。
導入に適した業務や活用シーンを見極める
アウトソーシングの効果を最大化するには、委託に向く業務を見極めることが欠かせません。定型作業が多く、マニュアル化や標準化が可能な業務は委託に適しています。経理の仕訳処理、給与計算、問い合わせ対応などは代表的な例です。
また、繁忙期に業務量が大きく変動する作業も外部活用で負荷を平準化しやすくなります。一方で、社内の機密情報を扱う業務や、経営判断に直結する企画業務は、委託する際に慎重な検討が必要です。
さらに、事業拡大や新規プロジェクトの立ち上げ時もアウトソーシングは有効です。短期間で専門人材を確保でき、スピーディーな事業推進につながります。事例を理解する際には、対象業務の特徴や発生頻度、社内リソースの状況を考慮しながら、導入シーンを具体的に思い描くことが成功の近道です。
営業代行のメリット・デメリットについて、もう少し詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
営業代行の評判は本当?導入前に知っておきたいメリット・リスクと成功のコツ
業務別に見るアウトソーシング成功事例

企業がアウトソーシングを活用する背景には、人手不足や専門性の確保、業務の平準化といった多様な課題があります。導入に成功した企業は、課題の整理から委託範囲の見極めまでを丁寧に進め、成果へとつなげているのです。ここでは、実際に成果をあげた企業の具体的なケースを3つ取り上げ、それぞれの工夫と効果を紹介します。
株式会社AIRDO
航空会社の株式会社AIRDOでは、IT部門の社内ヘルプデスク業務を外部に切り出す取り組みを実施しました。導入前の社内対応では、担当者ごとの対応スピードや品質に差が生じやすく、さらに対応履歴の属人化も進んでいたといいます。
対して、マニュアル化やナレッジ共有の強化を図るとともに、対応内容の標準化を徹底しました。委託先との間で定期的なミーティングを設け、改善点や対応品質についても継続的な見直しが行われています。
結果として、問い合わせ対応のスピードは向上し、社員からの評価も改善傾向がみられました。属人化から脱却し、業務の安定運用へとつながった点が高く評価されています。
株式会社ベネッセコーポレーション
教育サービス大手の株式会社ベネッセコーポレーションでは、カスタマーサポート部門の一部を外部委託する取り組みを進めました。自社ブランドに対するユーザーの信頼感を守りつつ、対応品質のばらつきや人材不足の課題に対処する目的で、専門性の高い業務委託を活用しています。
導入にあたっては、コールセンター業務に求められる対応マナーや表現のトーンを細かく定義し、パートナー企業と情報を共有しました。さらに、応対スクリプトの整備やトレーニングプログラムの実施により、オペレーターの品質維持を図っています。
定期的な評価やフィードバックのサイクルも機能しており、ユーザー満足度の維持と安定した稼働が実現できた好例といえるでしょう。
株式会社ブリヂストン
製造業界のリーディングカンパニーである株式会社ブリヂストンでは、調達・購買部門における業務の標準化と効率化を目的に、アウトソーシングの導入が進められました。とくに、業務フローが部門ごとに異なることが生産性の低下や情報共有の障壁となっていたことから、定型業務のプロセス可視化と再設計が課題となっていたのです。
外部パートナーの支援を受けて、各拠点の業務手順を洗い出し、ドキュメント化と統一化を推進しました。その結果、業務プロセスの重複や無駄を削減し、全社的な生産性向上に寄与する形となっています。
さらに、委託先との月次レビューを通じて改善点を継続的に洗い出し、業務品質の維持と強化に努めている点も、成功の要因といえるでしょう。
アウトソーシングの事例から学ぶ失敗パターンと注意点

アウトソーシングは多くの企業で成果を上げていますが、適切な準備や運用がなければ失敗につながることもあります。丸投げや社内調整不足などの典型的な失敗は、事前に知ることで回避が可能です。ここでは、代表的な失敗事例と注意点を整理します。
業務を丸投げしてブラックボックス化した事例
アウトソーシングで最も多い失敗のひとつが、業務を丸ごと委託し、社内で状況を把握できなくなるケースです。たとえば、経理処理を全面的に外部へ任せた企業では、進捗や処理内容を確認する仕組みを作らなかったため、決算期に重大なミスが発覚しました。
原因は、社内に知見が残らず、業務がブラックボックス化したことにあります。外部委託は効率化に役立ちますが、監視や報告のフローを欠くとリスクが高まります。
成功企業では、定期的な報告会や進捗共有ツールを活用し、委託業務を可視化していました。アウトソーシングは業務削減だけでなく、管理体制の構築も伴うことを理解し、丸投げを避ける姿勢が求められます。
関連記事:営業代行のトラブル事例と回避策|失敗を防ぎ成果につなげる実践ステップ
委託先選定の甘さで成果が出なかった事例
委託先の選定が不十分な場合も、期待した成果は得られません。実際に、営業サポート業務を委託した企業では、価格だけで業者を決めた結果、対応品質に問題が生じました。顧客への連絡が遅れたり、資料の誤送付が発生したりと、ブランドイメージに影響を及ぼす事態に発展しました。
失敗を防ぐためには、実績や得意分野、担当者のスキルを含めた総合的な評価が欠かせません。複数社を比較し、試験的な導入でパフォーマンスを確認した上で契約することが有効です。
成功事例に共通するのは、コストだけでなく、品質・対応力・コミュニケーション能力を重視している点です。委託先を慎重に選ぶことは、長期的な成果を左右する重要な要素となります。
社内連携不足で混乱した事例
アウトソーシングの導入時に社内調整を怠ると、業務フローが乱れやすくなります。たとえば、コールセンター業務を外部委託した企業では、担当部署への情報共有が不十分で、顧客対応の内容が社内に伝わらず、クレーム対応が遅れました。原因は、委託開始前に社内の役割分担や報告ルートを明確化していなかったことです。
失敗を避けるには、業務開始前に関係部署を巻き込み、情報連携の体制を構築することが不可欠です。成功した企業は、問い合わせ内容や進捗を共有するためのツールを導入し、社内外で同じ情報をリアルタイムに確認できるようにしていました。社内連携を軽視すると、せっかくの委託効果が半減するため、事前調整に十分な時間を割く必要があります。
情報セキュリティリスクが顕在化した事例
情報管理の不備も大きな失敗につながります。顧客情報を含む業務を委託した企業では、委託先での取り扱い基準が不十分で、外部への情報漏洩が発生しました。信用の失墜は大きく、取引先対応や再発防止に多大なコストがかかりました。情報セキュリティを軽視した委託は、効率化以上の損失を生む可能性があります。
成功企業は、契約時に情報管理基準やアクセス制限の条件を明記し、定期的に監査やチェックを行っています。セキュリティ意識の高い委託先を選び、管理体制を社内外で二重に整えることが重要です。事例が示す通り、アウトソーシングではスピードやコスト削減だけでなく、安全性の確保も成功の前提となります。
成功事例に共通するアウトソーシング活用のポイント

アウトソーシングで成果を出している企業には、共通する工夫があります。目的の明確化や業務範囲の整理、進捗確認の仕組みづくり、将来的な内製化を見据えた運用などです。ここでは、成功事例に共通する4つのポイントを解説します。
目的と期待成果を明確にした事例
成果を上げた企業は、導入前に目的と期待成果を具体的に定義していました。たとえば、経理業務を委託した企業は「作業時間削減」と「月次決算の早期化」を数値で設定し、委託範囲を明確に決定しました。
目標を定めたことで、委託先との認識が揃い、導入後の評価もしやすくなりました。目的が曖昧なまま進めると、効果測定が困難となり、社内での評価も下がりやすくなります。成功事例では、KPIやスケジュールを共有し、達成度を定期的に確認する仕組みを構築していました。
期待成果を明示すると、委託先も成果を意識した運用を行いやすくなります。明確なゴール設定は、アウトソーシング活用の第一歩として不可欠な要素です。
業務範囲を適切に整理・分解した事例
アウトソーシングの効果は、業務範囲の整理によって大きく変わります。成功した企業は、業務プロセスを細かく分解し、委託に適した部分と社内で残す部分を明確化しました。
たとえば、コールセンターを委託する場合でも、FAQ作成や顧客対応方針は社内で決め、実務対応のみを外部に任せる方法を採用しています。業務の切り分けを丁寧に行うことで、品質を保ちながら効率化を実現できました。委託範囲が曖昧な状態で進めると、責任の所在が不明確になり、トラブルの原因となります。
事例に学ぶと、業務をフローごとに見直し、委託の可否を判断するステップが重要です。業務の分解と整理は、効果的なアウトソーシングを実現するための基本施策です。
定期的な進捗共有・評価で品質を維持した事例
アウトソーシングで高品質を維持するには、定期的な進捗確認と評価が欠かせません。成功事例では、週次や月次のミーティングを実施し、成果物のチェックや改善点の共有を徹底していました。
ある企業では、営業サポート業務を委託し、受注件数や対応スピードを指標化することで、外部とのパフォーマンス差を常に把握していました。進捗報告の仕組みがあると、問題が発生した場合も早期対応が可能です。
また、委託先も評価基準を理解しているため、品質向上に向けた意識が高まります。成果を継続的に出す企業は、単に任せるのではなく、社内外で情報を循環させる運用を行っています。進捗共有と評価は、信頼関係を強化しながら長期的な成果につながる取り組みです。
将来的な内製化や知見蓄積を考慮した事例
長期的な視点で成果を出している企業は、アウトソーシングを単なる外部依存にしていません。業務を委託する一方で、社内に知見を蓄積し、将来的な内製化を見据えた運用を行っています。
たとえば、IT運用を委託した企業では、マニュアル化や手順書の作成を並行して進め、数年後に一部の業務を社内で実施できる体制を整えました。知見を記録することで、委託先の変更や追加委託の際もスムーズに対応できます。
成功企業に共通するのは、短期的な負荷軽減だけでなく、中長期的な自社強化を意識している点です。内製化を視野に入れた運用は、リスク分散やコスト最適化にも直結します。戦略的に知見を残す姿勢が、持続的なアウトソーシング活用につながります。
アウトソーシング導入を成功に導くステップ

アウトソーシングを効果的に活用するには、導入の流れを明確にし、計画的に進めることが重要です。現状分析から委託先の選定、評価・改善までを段階的に行うことで、リスクを抑えながら成果を最大化できます。ここでは4つのステップを整理します。
現状課題とリソースの整理
導入の第一歩は、社内の課題とリソース状況を明確にすることです。業務フローを棚卸しし、負荷が高い作業や属人化しているプロセスを洗い出すと、委託に適した業務が見えてきます。
さらに、人材や時間、コストの観点から、現在の対応力を数値で把握することも有効です。たとえば、月次で経理処理に30時間以上を費やしている場合、外部委託による削減効果を試算しやすくなります。課題の把握とリソース分析を行うことで、導入目的や期待成果が明確化されます。
成功企業は、初期段階で問題点を具体的に整理し、社内関係者の認識を統一していました。最初のステップを丁寧に実施することで、後続の計画や委託範囲の決定がスムーズになります。
適した業務と委託先の選定ポイント
次のステップは、委託に向く業務の特定と適切な委託先の選定です。定型的で標準化しやすい業務はアウトソーシングに向いていますが、社内の戦略や判断が必要な業務は残す方が安全でしょう。
委託先の選定では、実績や専門性、セキュリティ体制、対応品質などを多角的に評価することが大切です。価格だけを基準に選ぶと、後に品質面で問題が発生する可能性があります。成功事例では、複数社に提案を依頼し、試験運用を経て最終決定を行っていました。
また、担当者同士のコミュニケーションがスムーズかどうかも重要な判断材料です。業務特性と委託先の能力を適切にマッチさせることで、安定した運用につながります。慎重な選定は、長期的な成果を生む土台となります。
営業代行会社の選び方について、もう少し詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
営業代行の選び方とは?メリットやどこを重視すべきかポイントも解説
導入後の評価・改善サイクルを構築する
アウトソーシングは、導入して終わりではなく、運用しながら改善することで最大効果を発揮します。導入直後は、進捗や成果物を頻繁に確認し、問題があれば迅速に修正しましょう。
評価指標としては、作業時間の削減率、エラー件数、コスト削減額などが活用されます。成功事例では、月次の振り返り会議を行い、委託範囲の見直しや手順改善を継続していました。改善サイクルを組み込むことで、業務品質を維持しながら効率化を加速できます。
さらに、評価の仕組みを明確にすると、委託先も成果に直結する行動を取りやすくなります。アウトソーシングを継続的に最適化する姿勢が、投資効果を高め、長期的な安定運用を実現するでしょう。
失敗しないための社内体制づくり
最後のステップは、社内体制の整備です。委託先とのやり取りをスムーズに行うために、窓口となる担当者や連絡ルールを決めておく必要があります。情報共有の仕組みを整えると、社内での把握漏れや対応遅れを防ぎやすくなります。
とくに、顧客情報や経理データなどの機密情報を扱う場合は、アクセス権限や承認フローを明確にすることが重要です。成功企業は、社内マニュアルや問い合わせ対応ルールを事前に整え、トラブル発生時の対応も想定していました。
体制を構築してから委託を開始すると、業務の混乱や品質低下を避けやすくなります。社内と外部の連携を意識した仕組みづくりが、失敗の回避と安定的な成果につながります。
まとめ
アウトソーシングは、業務効率化やコスト削減にとどまらず、企業の成長戦略や競争力強化に直結する手法です。成功事例に共通するのは、導入前の課題整理と目的設定、業務範囲の適切な分解、定期的な進捗共有による品質維持です。失敗事例で多く見られる丸投げや社内連携不足を避ければ、委託効果を最大化できます。
さらに、長期的な知見蓄積や将来的な内製化を視野に入れた運用が、持続的な成果につながります。導入を検討する際は、業務特性やリソース状況に応じた計画的な進め方が不可欠です。
弊社の営業参謀では、業務を請け負うだけでなく、貴社のビジネスモデルや方針を深く理解したうえで、成果につながる営業戦略の立案から実行、さらに将来的な内製化まで一貫して支援が可能です。
伴走者にとどまらず、事業成長をともに実現する戦略パートナーとして貢献します。
これひとつで
営業参謀のすべてが分かる!
BtoB営業組織立ち上げ支援サービスの内容や導入事例、料金プランなど営業参謀の概要がまとめられた資料をダウンロードいただけます。



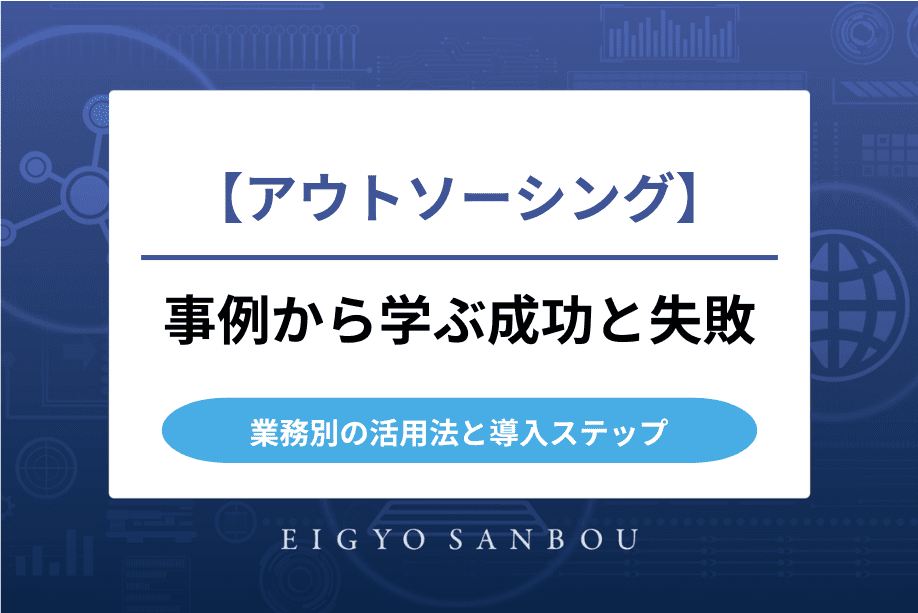
 ツイートする
ツイートする シェアする
シェアする LINEで送る
LINEで送る URLをコピー
URLをコピー