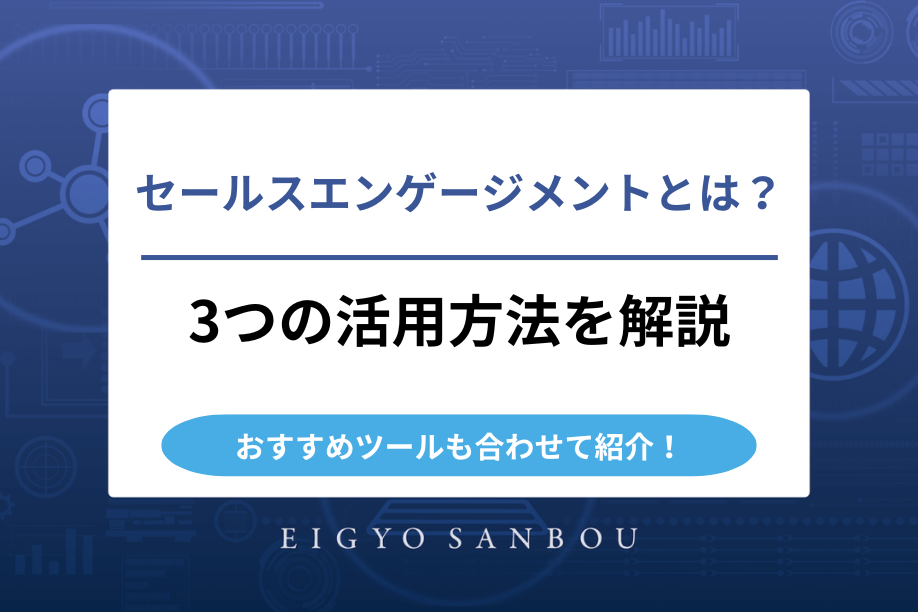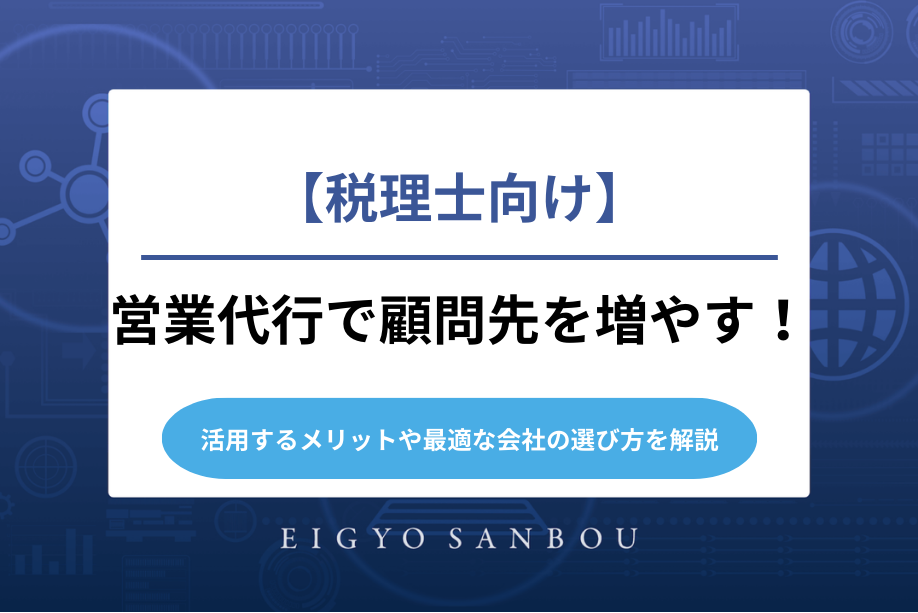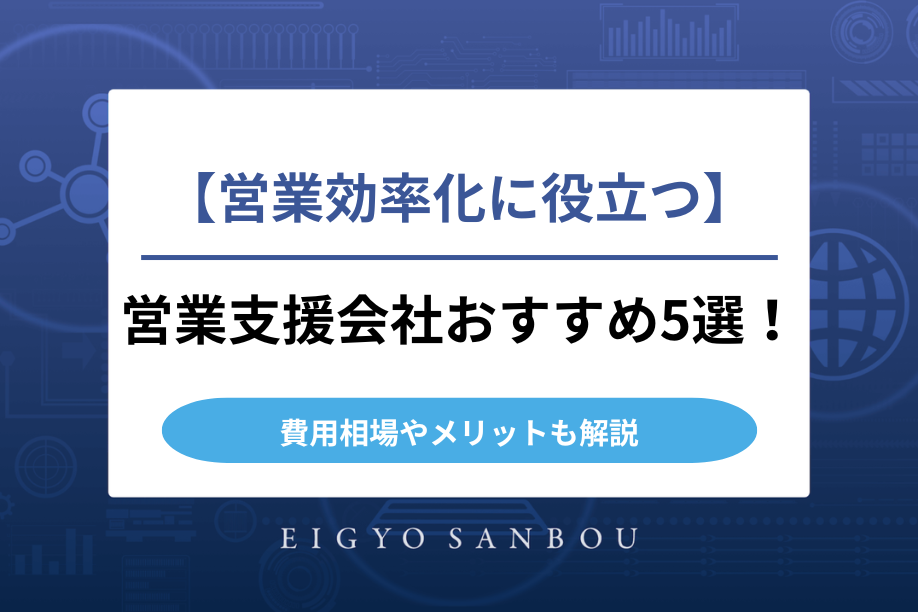営業として結果を出し続けるには、単なる話術や経験だけでは限界があります。変化の激しい市場や顧客の期待に応えるには、営業活動の本質を理解し、再現性のある行動に落とし込む視点が不可欠です。
本記事では、成果を上げる営業に共通する本質的なスキルや、営業組織として強くなるための工夫、さらには時代に適応する進化の方向性までを詳しく解説します。
▶貴社の事業成長を営業の側面からサポートするパートナーサービス『営業参謀』についてはこちら
営業でお悩みのことありませんか?
目次
営業の本質とは何かを明確に理解する

営業という職種には幅広い活動が含まれていますが、表面的な成功体験や手法に偏ると本質を見誤りがちです。本来の営業の役割とは何かを理解し直すことで、行動指針に明確な軸が生まれます。ここでは、営業という職能の根源的な意義を掘り下げていきます。
営業と販売の違いを押さえる
営業と販売は混同されがちですが、実際には役割が異なります。販売は商品やサービスを提供し対価を得る行為ですが、営業は顧客の関心が薄い段階から関係を築き、必要性を顕在化させるプロセスを含みます。この違いを理解することが、戦略的な活動に結びつくのです。
営業は「欲しい」と思われていない段階の相手に価値を届ける行為です。そのため、単なる価格競争に陥らず、信頼構築や課題の共有が重視されます。対話を通じて顧客の理解を深め、提案の土台をつくる活動が営業の本質にあたります。
言い換えれば、営業とは「売る」以前に「つながる」役割を持つといえるでしょう。販売とは異なり、信頼に根差した関係づくりが最終的な成果へとつながります。
関連記事:営業目標の設定方法と具体例|モチベーションを維持し成果を上げるための工夫も解説
顧客視点が営業の起点になる理由
営業活動の出発点は、顧客の立場に立つ視点にあります。商品やサービスの特性ばかりを伝える営業は、相手に届かないことが多いです。求められているのは、相手の課題や背景を理解し、それに合致する形で価値を提供する姿勢です。
ニーズを正確に把握するには、聞く力や観察力も求められます。営業担当者が一方的に話すだけでは、本当の意味での信頼関係は築けません。相手の意見や反応を受け止めながら、柔軟に考え方を変えていく力が必要です。
売り手の視点から脱却し、常に相手のメリットを中心に据えることで、提案の精度は自然と向上していきます。相手の期待に沿う行動こそが、営業としての成果を生み出すでしょう。
「売る」のではなく「買ってもらう」姿勢
営業においては「売り込む」という発想から離れることが重要です。多くの場合、成果が出ない営業は、自社目線での押しつけに終始しています。営業の本質は、顧客が自発的に購入を決めるよう導くプロセスにあるのです。
したがって、相手が判断しやすい環境や情報を整える必要があります。無理に契約を迫るような姿勢は、かえって信頼を損ねる原因になります。
納得して選ばれる状態を作ることが営業の役割です。一方的に伝えるだけでなく、対話を通じて相手の価値観や意向を理解し、共にゴールを目指す意識が求められます。買ってもらうという姿勢が定着すれば、継続的な関係の構築にもつながりやすくなります。
関連記事:営業ターゲティングスキル:効果的な顧客層選定と売上余地の発見
営業職が果たす本来の役割とは
営業担当者は、単なる売上の確保にとどまらない広範な役割を担っています。顧客との接点において信頼を築き、ニーズに応じた価値を提供するだけでなく、その声を社内に持ち帰ることで、商品やサービスの改善にも貢献可能です。
つまり営業は、企業と顧客をつなぐ架け橋でもあります。外部の情報を取り込みながら、社内の関係者と連携し、顧客に最適な提案を行う調整役ともいえるでしょう。また、顧客からの信頼を得ることで、企業のブランド価値や継続的な収益の基盤を築くことにもつながります。
営業職の本質を理解している担当者は、ただ数字を追うのではなく、長期的な信頼関係を構築することを優先しています。
営業活動に必要なマインドセット
営業で成果を出すには、表面的なスキルよりも根本的な考え方が影響します。顧客の立場に共感し、常に学び続ける姿勢を持つことが、信頼される営業に必要です。失敗や拒否を恐れずに行動し、変化する状況にも柔軟に対応する姿勢が求められます。
また、誠実さや責任感をもって業務に取り組むことで、関係性の質は向上します。自分の都合で動くのではなく、相手の期待を超える行動を意識することが、評価につながりやすくなるでしょう。
成果が出ないときこそ、マインドセットを振り返る機会と捉えることで、次の成長に結びつけることができます。営業における信頼は、日々の積み重ねによって形成されるものです。
関連記事:営業活動の効率化と新たなターゲット層開拓を実現した営業支援
売れる営業に共通する「営業の本質的スキル」

営業成果に差が出る背景には、特定のスキルセットの有無が大きく関係しています。成果を上げ続ける営業担当者には、共通する技術や姿勢があるのです。ここでは、売れる営業が持つ本質的なスキルを5つに分けて詳しく見ていきましょう。
傾聴力と共感力を土台にする
成果を上げる営業担当者は、話すこと以上に「聞く力」を重視しています。相手の話をただ受け止めるのではなく、背後にある意図や感情まで丁寧にくみ取る傾聴力が、信頼を築く第一歩です。
表面的なニーズに飛びつくのではなく、対話を通じて本質的な課題を明らかにする姿勢が重要です。そのうえで共感力を発揮し、顧客の感情に寄り添いながら関係性を深めていくことが求められます。
話を聞いてもらえたと感じた相手は、自然と心を開く傾向にあります。相手の立場に立ち、言葉だけでなく態度でも理解を示すことで、商談の質は大きく変わってきます。高い傾聴力と共感力を持つ営業担当者は、受注率だけでなく、継続的な関係構築においても優れた成果を出しているのです。
価値を見極める課題発見力
顧客の言葉をそのまま受け入れるだけでは、真のニーズを把握することはできません。売れる営業担当者は、対話のなかに隠れた問題や機会を見つけ出す「問いかけ力」に長けています。
たとえば、現状の業務に関する漠然とした不満があったとしても、それが業務効率なのか、属人化なのか、あるいは社内連携に起因するのかを明確にする必要があります。表面に出ていない情報を引き出すには、仮説を立てたうえで、深掘りする質問が効果的です。
また、顧客が気づいていない課題を指摘できれば、相手からの信頼も得やすくなります。本質的な価値を見極める能力がなければ、提案は単なるスペックの説明に終始してしまいます。課題発見力は、他の営業と一線を画す要素であり、最終的な差別化につながるでしょう。
納得感を高める提案力
相手にとって本当に意味のある提案ができるかどうかで、営業の成果は大きく左右されます。優れた営業担当者は、顧客の課題に合致した解決策を論理的かつ具体的に提示します。ただ情報を並べるだけではなく、導入後の変化や期待される効果までを明確に伝えることが必要です。
また、相手の立場や職責に合わせて、提案内容の見せ方や言葉選びを調整する柔軟性も求められます。説明を受ける側が「自分にとって必要なものだ」と感じることが、受注につながる最も大きな要因です。
営業担当者が熱心であるだけでは足りません。根拠や数字を用いながら、納得感のある構成に仕上げることが、信頼を得るための前提条件になります。適切な提案力を持つことで、比較検討のなかでも優位に立てる可能性が高まります。
クロージングに頼らない信頼構築法
成果を追い求めるあまり、クロージングに力を入れすぎてしまう営業担当者は少なくありません。しかし、信頼が十分に築かれていない状態で強引に契約を促しても、結果的に関係が途切れてしまうケースが多く見受けられます。
売れる営業は、契約を急がずに相手の不安や懸念を丁寧に解消しながら、関係性を積み上げていきます。その過程で「この人から買いたい」と感じてもらうことができれば、契約は自然な流れで成立するでしょう。
また、誠実で一貫した対応を続けることが、信頼を生む基盤となります。一度の商談で成果を出そうとせず、長期的な視点での関係構築を優先する姿勢が重要です。クロージングの技術に依存しないスタイルこそが、継続的に選ばれる営業の本質を体現しています。
顧客の意思決定を支援する質問設計
効果的な質問は、顧客の思考を整理し、意思決定を後押しする大きな役割を果たします。単なる情報収集ではなく、相手が自ら課題を認識し、その重要性に気づくプロセスを促す質問が必要です。
たとえば「現状で何が最も負担に感じられますか?」といった問いかけによって、顧客自身が課題を言語化できるようになります。また、段階的に質問を展開することで、相手の理解度や購買意欲を自然と引き出すことも可能です。
売れる営業は、問いを通じて相手の意思を尊重しながら、対話のなかで共通認識を築いていきます。意思決定を促す質問は、決して誘導ではなく、選択を整理するための手助けです。相手の納得を重視した設計を意識することで、無理のない合意形成が実現しやすくなります。
営業力を支える4つの本質的要素

営業活動の成否は、単一のスキルではなく複数の基盤によって決まります。成果を上げ続ける営業担当者には、共通して備わっている「営業力の土台」が存在します。ここでは、個人の営業力を支える4つの本質的な構成要素について整理していきましょう。
人間力|信頼を得るための土台
営業で成果を上げるには、技術や知識の前に「人間として信頼されること」が欠かせません。たとえば、言葉遣いや礼儀、相手に配慮した立ち居振る舞いは、信頼関係の入り口となります。
さらに、誠実さや責任感といった内面的な姿勢も、人間力の一部として大きな影響を持ちます。相手の立場や背景を理解し、思いやりを持って接することで、対話の質が高まりやすくなるでしょう。営業では数字だけでなく、相手との関係性が大きな成果を生む原動力になります。
したがって、どれだけ商品知識が豊富でも、信頼される人格が伴わなければ契約には至りません。人間力は一朝一夕で身につくものではありませんが、日々の行動や態度によって着実に育まれていきます。
技術力|再現性のある営業技法
営業の世界において、感覚や経験則だけに頼るのでは限界があります。成果を安定的に出すには、再現性のある技術が必要です。
たとえば、ヒアリングの流れや提案資料の構成、商談のフェーズごとの対応など、体系立てて整理された手法を持つことで、誰が行っても一定の成果を出せるようになります。特定の手法に依存するのではなく、状況に応じた柔軟な運用ができるようになると、営業活動全体に余裕が生まれます。
経験だけに頼らず、振り返りと改善を繰り返す姿勢も技術力を高めるポイントです。技術は属人的な能力ではなく、継続的な習得と応用によって進化していくものです。営業力を底上げするうえで、確かな技術を習得することは避けて通れません。
知識量|顧客の期待を超える準備
信頼される営業担当者は、常に情報と知識のインプットを怠りません。顧客が置かれている業界のトレンドや課題、自社サービスの技術的な背景などを把握していることで、より的確な提案が可能になります。
また、競合状況や過去の導入事例などを踏まえたうえでの会話は、相手からの評価を大きく高める要素となります。顧客は単なる商品説明ではなく、自社に合わせた具体的な提案を求めているのです。
その期待を上回るには、日頃の情報収集と自己研鑽が欠かせません。知識量が豊富であれば、想定外の質問にも落ち着いて対応できるようになります。準備の段階でどれだけ相手に向き合っているかが、商談の成否を大きく左右するのです。
情報収集の大切さについて、もう少し詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
管理力|行動を可視化・改善する習慣
営業活動を計画的に進めるには、日々の行動を正確に管理する力が求められます。たとえば、案件の進捗状況や顧客とのやり取りを記録し、次の打ち手を明確にすることで、無駄のないアクションが取れるようになります。
また、スケジュール管理やToDoリストの整理によって、商談機会の取りこぼしを防ぐことも可能です。売れる営業担当者は、感覚ではなくデータをもとに行動を調整しています。さらに、過去の成功・失敗から学び、プロセスそのものを改善していく意識も重要です。
管理力は単なる事務的作業ではなく、自分自身を最適化するための仕組みともいえます。継続的な振り返りと調整を通じて、営業力の精度は着実に高まっていくでしょう。
失敗から学ぶ、営業の本質を見失ったときのサイン

営業活動において、本質から外れてしまう瞬間は誰にでもあります。結果ばかりを追い求めてしまったり、顧客との関係が形骸化してしまうことも少なくありません。ここでは、営業の本質を見失っているときに見られる代表的な兆候を具体的に紹介します。
売上目標に追われすぎて顧客を見失った例
数値目標が明確に設定されている環境では、売上の達成に強く意識が向かいがちです。結果として、顧客一人ひとりとの関係性が後回しになり、対応が事務的・形式的になるケースが目立ちます。
提案内容が顧客の課題に沿っていないにもかかわらず、売上を優先して強引にクロージングを試みると、信頼を損ねる結果につながることもあります。数字ばかりを意識しすぎた結果、契約の質が下がり、クレームや早期解約を引き起こしてしまう恐れもあるでしょう。
営業において成果は重要ですが、目の前の相手に本気で向き合う姿勢を失ったとき、営業活動の本質から外れてしまいます。目標達成と顧客貢献のバランスが取れていなければ、長期的な信頼は築けません。
テクニック偏重になった営業活動の末路
営業ノウハウや話法などのテクニックは、一定の成果を生む可能性があります。しかし、それに頼りすぎると本来の目的である「相手の課題解決」から離れてしまう危険があります。
とくに、初回訪問時からスクリプト通りの説明を進めるだけでは、顧客の反応に柔軟に対応することが難しいでしょう。営業がうまくいかないと感じた際に、さらにテクニックを重ねるだけでは本質的な改善にはつながりません。
重要なのは、相手が何を求めているのかを見極め、それに寄り添った対応を行うことです。表面的な話術で一時的に信頼を得たように見えても、継続的な取引には結びつきません。テクニックを使いこなす前に、その背景にある「なぜ行うのか」という視点を忘れてはなりません。
断られる恐怖に支配される心理状態
営業活動では、提案を拒否される場面が避けられません。しかし、断られることへの恐怖が強くなると、行動そのものが消極的になってしまいます。たとえば、新規アプローチを避けたり、深掘り質問を控えたりするようになると、相手との距離を縮める機会を自ら失ってしまいかねません。
さらに、自信を持てない状態が続くと、提案の際の言葉にも迷いが生じ、結果として信頼性も損なわれます。断られることを極端に恐れてしまうと「失敗を避けること」が目的となり、本質的な価値提供の意識が薄れてしまいます。
断られる経験は決して否定的なものではなく、むしろ改善点や相手のニーズを把握するチャンスと捉えるべきです。恐れを乗り越え、行動量と質を高めることが、営業本来の役割に立ち返る第一歩となります。
断られる恐怖感の克服法についてもう少し詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
法人営業がきついと感じる理由と克服法|続ける価値ややりがいも詳しく解説
顧客との信頼を損ねる行動パターン
営業における信頼は、一度失われると取り戻すのが難しくなります。たとえば、約束した期日を守らない、説明に一貫性がない、または質問に対する回答が曖昧であるといった行動は、相手からの信用を確実に損ねていきます。
こうした状態が続くと、どれだけ魅力的な商品を扱っていたとしても、選ばれることはありません。また、相手の立場に配慮せず、自社の都合ばかりを優先した提案も不信感を生む原因となります。
営業の本質は「相手のために動くこと」であるにもかかわらず、自分本位な行動が目立ち始めたとき、すでに本質から遠ざかっている可能性が高いです。小さな対応の積み重ねが信頼に直結していることを意識し、丁寧で誠実な姿勢を継続することが重要です。
本質に戻るための気づきと行動の再設計
営業の本質を見失ったと感じたとき、必要なのは一度立ち止まり、現在の行動や思考の癖を見直すことです。たとえば、成果を焦るあまりに短期的な視点で動いていないか、提案内容が相手の課題とズレていないかなど、冷静に棚卸しする機会を設けることが効果的でしょう。
改善の第一歩は「なぜ営業という仕事をしているのか」という原点に立ち返ることです。そのうえで、日々の行動を再構築する必要があります。顧客との接点をより意味のあるものにするには、準備・振り返り・仮説立てといった基礎を丁寧に積み上げる姿勢が欠かせません。
成果を出している営業担当者ほど、定期的に自分の行動を見直す習慣を持っています。気づきを行動につなげる姿勢が、本質を再び取り戻す力になります。
営業組織として本質的に強くなるための工夫
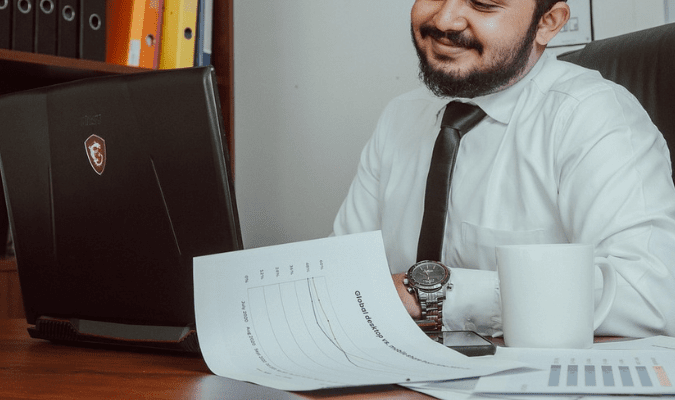
営業担当者の能力だけで成果を出し続けることには限界があります。組織として営業力を高めるには、環境や仕組み、育成手法などに目を向けることが不可欠です。このセクションでは、営業組織が本質的に強くなるための実践的な工夫を紹介します。
個人の属人化を脱するナレッジ共有
営業現場では、成果を出している人のノウハウが個人の中にとどまり、組織全体に共有されない状況が頻繁にみられます。属人化が進むと、特定の人に業績が依存しやすくなり、継続的な成果創出が難しくなるのです。
したがって、営業プロセスを形式知として整理し、全体で共有できるナレッジとして蓄積する必要があります。たとえば、商談録や成功事例をチームで可視化し、共通言語として活用することが効果的です。
さらに、他者の経験を自分の引き出しとして活かせるようなカルチャーを育てることで、知見が組織全体の資産として機能します。ナレッジ共有は、再現性のある営業体制を築くうえで欠かせない基盤となります。
再現性の高い営業プロセスの整備
営業力を組織的に向上させるには、感覚に頼らないプロセスの設計が求められます。営業フローが各自の判断に任されている場合、成功と失敗の要因が不明確になり、改善が難しくなります。
成果が出ている人の行動パターンをモデル化し、案件の進行ステップごとに必要なアクションや判断基準を整理することで、誰が取り組んでも一定の成果を上げやすい仕組みをつくることが可能です。
また、商談管理ツールなどを活用して可視化を行えば、進捗のモニタリングやボトルネックの把握が容易になります。属人的な手法から脱却し、組織としての生産性と成果の安定性を追求する姿勢が、本質的に強い営業組織を支えます。
マネジメントが果たす役割と関わり方
営業組織の強化には、現場任せではなくマネジメントの適切な関与が欠かせません。ただし、細かく管理しすぎると現場の自律性が失われ、逆に放任すると方向性の統一が難しくなります。成果を出している組織では、マネージャーが進捗の確認だけでなく、課題の抽出や行動の意味づけを一緒に行っています。
また、メンバーの成果だけでなくプロセスにも注目し、適切なタイミングでフィードバックを行うことも効果的です。心理的安全性がある環境では、メンバーが自ら課題を共有しやすくなり、改善のスピードも加速します。
マネジメントの役割は、成果を上げさせることだけではなく、各人が営業の本質を理解し、自走できるよう導くことにあります。関与の質が、組織全体の営業力を左右します。
育成の場に必要な実践機会と振り返り
営業スキルは座学やマニュアルだけでは定着しにくく、現場での実践を通じて初めて深まっていきます。しかし、経験だけに頼ると誤った方法が習慣化してしまう恐れもあるため、意図的に振り返りの場を設けることが重要です。
たとえば、商談後の1on1やロールプレイの振り返りを取り入れることで、具体的な行動を言語化し、次に活かす機会をつくれます。成功体験や失敗からの学びをチーム内で共有することで、組織全体の成長速度も向上します。
育成を属人的なOJTに頼るのではなく、体系化されたフィードバックと実践の繰り返しによって、営業の本質的な理解が深まるでしょう。単なる経験ではなく、意図的に設計された実践の場が、人を育てる環境を支えています。
顧客視点を全体に浸透させるチームづくり
営業組織が強くなるためには、個々の意識だけでなくチーム全体に顧客中心の視点を根付かせる必要があります。たとえば、案件の進捗共有において、ただフェーズを報告するのではなく「顧客がどんな課題を持ち、どのように変化したか」を軸に情報を整理すると、関係者全体が顧客起点で思考する習慣がつきます。
また、チームでの振り返りやミーティングでも、成果の理由を顧客の行動から逆算して考えることで、本質的な改善が可能です。このようなカルチャーが形成されることで、顧客視点が個人のスキルではなく、組織全体の標準になります。どのような商談でも一貫性のある価値提供が可能になれば、営業組織としての信頼性も格段に高まります。
今後の営業に求められる本質的な進化とは

ビジネス環境や顧客の意思決定プロセスが大きく変化するなかで、営業活動にも新たなアプローチが求められています。従来のやり方だけでは成果を出し続けることは困難です。ここでは、営業が今後進化すべき本質的な方向性を解説します。
情報提供から価値創出へのシフト
過去の営業では、製品情報やスペックをわかりやすく説明することが主な役割とされていました。しかし、顧客が事前に情報を収集できるようになった現在では、それだけでは差別化が困難です。ただの案内役ではなく、顧客の課題に応じた気づきや、意思決定の質を高める支援が求められます。
たとえば、業界全体の動向や他社の成功事例を踏まえて、顧客の視野を広げるような提案ができる営業担当者は、信頼されやすくなります。情報を渡すだけでなく、その活用方法まで提示できる姿勢が、今後の営業に不可欠な価値創出力といえるでしょう。相手の目線に立ち、まだ言語化されていない潜在的な期待に応える提案が、成果を生む源になります。
人にしかできない営業の深掘り
テクノロジーが進化するなかで、営業の一部は自動化やデジタル対応に置き換わりつつあります。しかし、人にしかできない関係性の構築や信頼の獲得は、今後ますます重要性を増していくと考えられます。
とくに、高額商材や複雑な意思決定が関わる取引では、最終的な判断を支えるのは「誰から買うか」に集約されがちです。人間味のあるやりとりや、相手に寄り添う姿勢、細かなニュアンスへの対応といった領域は、機械には代替できません。
今後の営業は、人としての深さがより強く問われる時代になります。知識やスキルの習得と同時に、人間力や関係構築の力を高めることが、営業としての価値を保ち続けるうえで不可欠になります。
デジタル活用による提案の高度化
営業活動の質を高めるためには、デジタルツールの活用が避けて通れません。SFAやCRM、Web商談ツールなどを適切に取り入れることで、顧客の行動履歴や過去の対応内容をもとに、より個別化された提案が可能です。
また、複数のチャネルから得られる情報を分析することで、顧客の興味関心の変化にもいち早く対応できます。デジタルの活用は、単なる効率化ではなく、提案の深度とタイミングの最適化を可能にする手段です。
ただし、ツールに振り回されないよう、目的を明確にしながら使いこなす意識が求められます。デジタルと人の力を組み合わせることで、より洗練された営業体験を提供できるようになります。
顧客の購買行動変化に対応する柔軟性
現代の購買行動は、多様化と複雑化が進んでいます。かつてのように営業担当者との対話を通じて情報収集するのではなく、顧客自身が事前にインターネットやSNSを通じて比較・検討を進める傾向が強まっているのです。
したがって、従来のアプローチだけではタイミングを逃したり、接点が形骸化してしまうリスクがあります。成果を上げている営業担当者は、顧客の行動パターンや意思決定プロセスを理解し、それに応じて柔軟にアプローチ方法を変化させています。
たとえば、早い段階での情報提供よりも、意思決定直前の不安払拭に注力するケースもあるでしょう。一律な手法ではなく、個別の文脈に合わせた営業活動が必要です。顧客視点を保ちながら、柔軟に変化できる力が求められます。
営業を“仕組み化”する視点の強化
営業の成果を個人の努力やスキルに依存している状態では、安定的な成果を出し続けることが難しくなります。そこで重要になるのが、営業活動全体を「再現性のある仕組み」に落とし込むという視点です。
たとえば、アプローチ方法の標準化や提案書のテンプレート化、商談進捗の可視化といった取り組みは、一定の質を保ちつつ効率的な営業を実現するために有効です。また、仕組み化によって属人性が排除され、誰が担当しても顧客に対する価値提供がブレにくくなります。
さらに、営業プロセスを可視化することで、問題の早期発見や改善にもつなげやすくなります。継続的に成果を出すためには、仕組みと柔軟性の両立が不可欠です。個人頼みの限界を突破するためにも、営業全体を戦略的に設計する視点が求められます。
まとめ
営業は単なる販売活動ではなく、顧客と真摯に向き合い、価値ある関係性を築く仕事です。成果を継続して出していくためには、営業の本質を理解し、実践のなかで磨き続ける必要があります。
本記事で紹介した視点や行動指針は、その出発点となるものばかりです。組織としても、個人の成長に依存せず、仕組みと文化で営業力を支える体制づくりが重要です。成長を目指す営業組織にとって、パートナーの存在は大きな意味を持ちます。
セールスアセットは、現場の実行と戦略設計を両立させ、成果の出る営業体制の構築を支援します。営業部門の立ち上げから内製化支援まで、一気通貫での伴走をご希望の方は、ぜひお問い合わせください。
これひとつで
営業参謀のすべてが分かる!
BtoB営業組織立ち上げ支援サービスの内容や導入事例、料金プランなど営業参謀の概要がまとめられた資料をダウンロードいただけます。



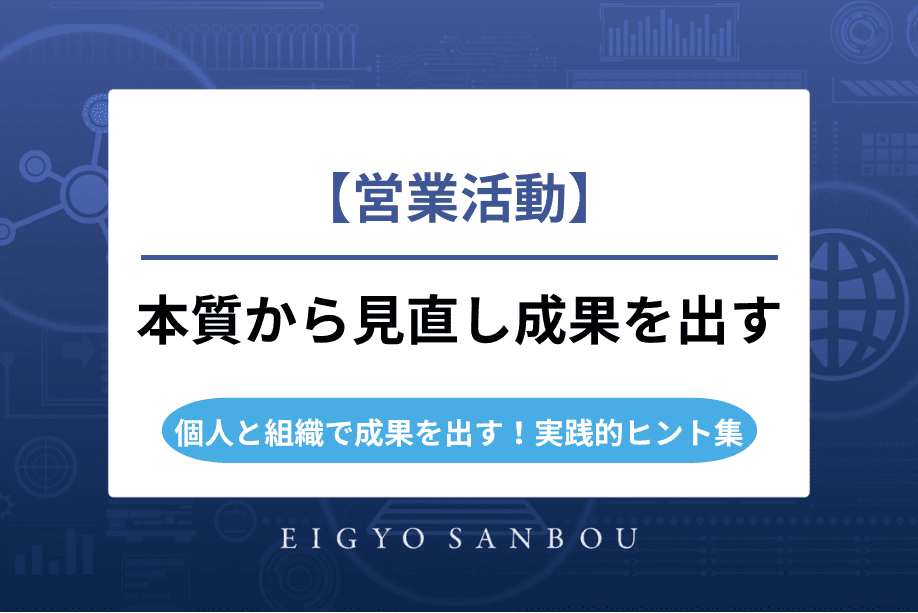
 ツイートする
ツイートする シェアする
シェアする LINEで送る
LINEで送る URLをコピー
URLをコピー