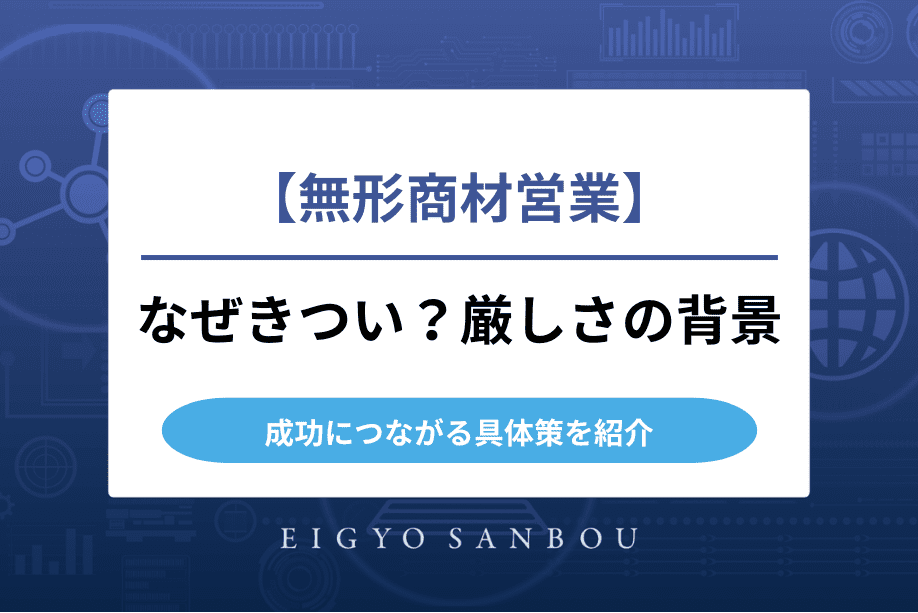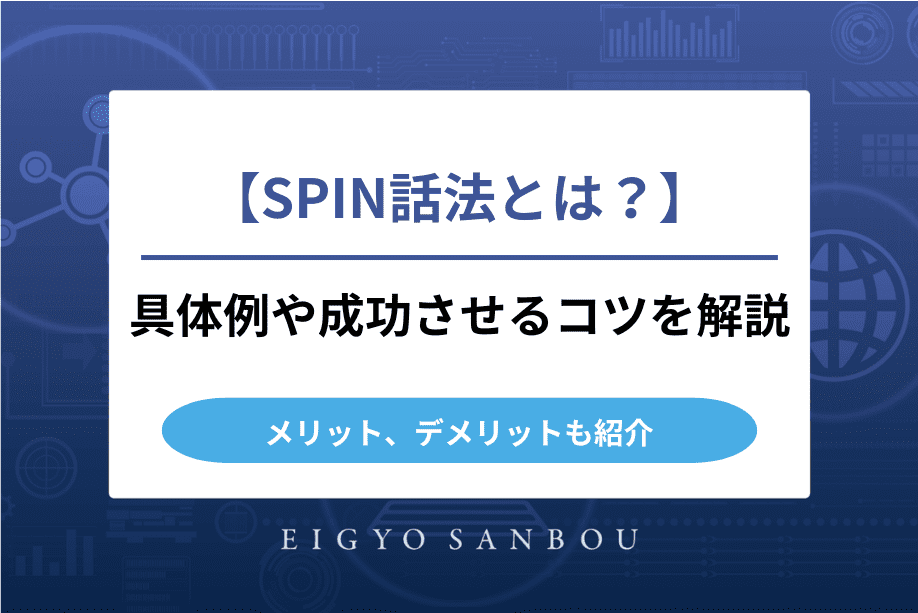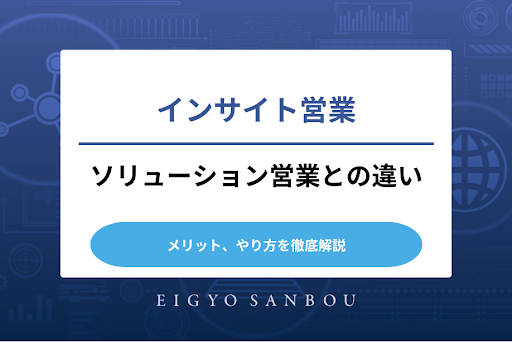テレコールとは営業成果を高めるうえで、顧客との初回接点は重要なステップです。とくにテレコールは、短期間で関心層を見極め、商談のきっかけを生む手法として注目されています。しかし、成果につなげるには単なる架電ではなく、適切なリスト管理や話法、運用体制が不可欠です。
本記事では、テレコールの基本から実践的な活用方法、成果を最大化するための支援サービスについて解説します。
▶貴社の事業成長を営業の側面からサポートするパートナーサービス『営業参謀』についてはこちら
営業でお悩みのことありませんか?
目次
テレコールとは何かを正しく理解する

電話を活用した営業手法として広く知られるテレコールは、業界や目的に応じて呼称や運用形態が異なります。まずは、基本的な概念や近い意味を持つ他の営業手法との違いについて整理し、全体像を把握しましょう。
テレアポやインサイドセールスとの違い
テレコールと混同されやすい手法に、テレアポとインサイドセールスが挙げられます。これらは電話を利用するという共通点がありますが、目的や業務の幅には違いが見られます。
テレアポは主に、訪問や商談のアポイントメントを獲得することを目的とした業務を指します。一方、インサイドセールスは電話に限らず、メールやオンラインミーティングツールも駆使して見込み顧客との関係を深め、受注に近づけていく内勤型の営業スタイルです。
テレコールはその中間的な存在として、とくにアポイント獲得を主目的としつつも、業務内容や会話の質によってはリード育成や情報収集にも貢献します。それぞれの手法を明確に区別することにより、営業活動全体の戦略設計がより効果的になります。
関連記事:インサイドセールスにおけるSDRとBDRの役割と重要性を解説
テレコールの役割と定義
営業活動におけるテレコールは、電話を通じて顧客と初期接点を築くためのアプローチを指します。新規開拓や商談機会の創出を目的とする場合が多く、営業担当者が見込み客に対して商品やサービスの概要を伝え、会話の中で相手の関心を引き出すことが求められます。
多くの企業では、マーケティング施策によって得られたリード情報をもとに電話をかけるケースが一般的です。テレコールの大きな役割は、単なる情報提供にとどまらず、受注につながる商談機会へとつなげる「入り口」として機能する点にあります。
営業フローの上流工程を担うことから、他部門との連携や情報共有の質も成果に直結しやすい領域です。
テレコールの歴史と進化の流れ
テレコールのルーツは、1980年代に活発化した電話営業の時代にさかのぼります。当初は紙の名簿をもとにひたすら電話をかける手法が一般的で、効率や質よりも数に依存したスタイルが主流でした。
しかし、営業現場のデジタル化が進むにつれ、顧客管理ツールの導入やスクリプトの標準化が進み、質の高い対話を重視する流れへとシフトしていきました。近年ではSFAやCRMと連動した業務フローが一般的になり、アプローチの精度が飛躍的に向上しています。
また、インサイドセールスやカスタマーサクセスとの連携により、単発的な架電ではなく、リードナーチャリングの一環としてテレコールが活用されるケースも増加しています。手法は変化しても、顧客とのファーストコンタクトを担う重要性は一貫しているのです。
関連記事:インサイドセールスがBtoB企業で導入が増えている理由
現代のテレコールに求められるスキル
今日のテレコールでは、単なるマニュアル通りの発話では成果につながりにくくなっています。まず第一に必要とされるのが、相手の反応を正確に捉えるリスニング力です。加えて、短時間で商品やサービスの魅力を伝える表現力、そして状況に応じた柔軟な対応力が欠かせません。
さらに、業界知識や競合との違いを理解しておくことで、会話の説得力が増します。声のトーンや話すスピードにも注意を払い、相手に安心感や信頼感を与えることも重要です。
単なる話し手ではなく、相手に寄り添う対話のプロフェッショナルとしての姿勢が求められます。スクリプトに頼るだけでなく、各自が考えて話す力を育てることが、チーム全体の成果向上にも直結します。
関連記事:営業ヒアリングのコツとは?ヒアリングシートの項目や役立つフレームワークも紹介
テレコールのメリットを整理する

営業活動の初期段階において、テレコールは多くの企業で導入されている手法です。電話という手段の特性を活かすことで、対面では得られないスピードや柔軟性が強みとなります。ここでは、営業成果を高めるうえで、テレコールが持つ代表的な利点について紹介します。
新規顧客と短期間で接点を持てる
テレコールの最も大きな魅力は、見込み顧客との初回接点をスピーディに構築できる点にあります。対面営業や訪問営業では、アポイントの調整や移動時間など多くの工数が発生しますが、電話であればタイムロスを最小限に抑えつつ、短期間で数多くの顧客と接触が可能です。
とくにBtoB領域では、営業リソースの制約が大きな課題となる場面が多いため、限られた人員でも成果を出せる効率的な方法として活用されています。加えて、音声を通じたリアルタイムなやり取りは、顧客の関心度や対応姿勢を即座に把握できるという点も利点です。
初動の早さは、その後の営業活動全体のスピード感を大きく左右します。機会損失を防ぐ意味でも、テレコールは重要な役割を果たします。
信頼構築の初動として有効な手段
営業活動の成否を左右する要因として、顧客との信頼関係が挙げられます。テレコールは、顧客と一対一で対話できるため、相手の反応や疑問に即時に対応することが可能です。
たとえば、メールやWeb広告では伝わりにくい温度感や誠意を、声を通じて直接届けることができます。対話を通じて顧客の興味や課題を引き出すことができれば、次のステップである商談への移行もスムーズになります。
また、個別対応が求められる場合でも、その場の空気を読み取りながら会話を進められるため、画一的なアプローチに比べて信頼を得やすいです。短時間でも誠実な対応を積み重ねることで、長期的な関係構築の第一歩として有効に機能する点は、テレコールならではの強みといえるでしょう。
営業スキルやプロセスの改善に役立つ
テレコールは営業担当者にとって、日々の実践を通じてスキルを磨く場にもなります。たとえば、トークスクリプトの使用や顧客対応の反応を記録することで、自身の話し方や質問の仕方を振り返りやすくなります。
また、結果に対するフィードバックが比較的早く得られるため、改善のサイクルを短く保てることも特徴です。加えて、架電のタイミングや切り返しトークの傾向を分析することで、より効果的な営業プロセスの構築が可能になります。
蓄積されたデータをもとにチーム全体のトーク精度が向上すれば、組織的な営業力の底上げにもつながります。個々の担当者だけでなく、部門全体として成果に結びつくプロセス改善を進められる点において、テレコールの運用価値は非常に高いといえるでしょう。
テレコールにおける主な課題とは

営業の初動を担うテレコールは、多くのメリットがある一方で、特有の困難やリスクも伴います。成果につなげるためには、課題を事前に把握し、対策を講じておくことが不可欠です。ここでは代表的な3つの課題について詳しく解説します。
断られることによる精神的ストレス
テレコールでは、多くの場合で「興味がない」「忙しい」「結構です」といった拒否の言葉を受けることになります。とくに新規開拓を目的とする場合は、何十件に1件の成功が平均的な成果となることも珍しくありません。
高い拒否率は、オペレーターや営業担当者にとって精神的な負荷となり、モチベーションの維持を難しくする要因になります。また、相手の感情的な対応や冷たい態度が続くと、自己肯定感が低下しやすくなる傾向もあります。
したがって、成果に一喜一憂せず、プロセス目標を重視する考え方や、定期的なフォロー体制の導入が有効です。感情の消耗を減らし、長期的に続けられる環境を整えることが、テレコールにおける精神面の課題を克服するための重要なポイントです。
相手に不快感を与えるリスクがある
テレコールは、顧客の同意を得ずに電話をかける性質上、タイミングや話し方によっては不快感を与えるリスクがあります。たとえば、忙しい時間帯に突然かかってきた電話に対して、相手が警戒心を抱くのは自然な反応といえるでしょう。
加えて、営業トークが一方的になったり、商品説明が長すぎたりすると、かえって印象を悪くすることもあります。リスクを避けるためには、事前に業種や職種ごとの対応傾向を把握しておくことや、短時間で要点を伝えるスキルを身につけることが求められます。
また、リストの精度を高めることによって、見込みのない相手への無駄な接触を減らすことも重要です。相手に配慮しながら会話を進める姿勢が、長期的な信頼構築にもつながっていきます。
成果につなげるには高度な話法が求められる
テレコールはただの架電作業ではなく、相手の関心を引き出しながら会話をリードする高度なコミュニケーションが求められます。とくにBtoB分野においては、相手の業務理解や課題意識を踏まえた提案ができなければ、商談にはつながりません。
表面的なセールストークでは警戒心を高めるだけになってしまうため、ヒアリングの流れや切り返しのタイミングなど、複数のスキルを組み合わせる必要があります。また、相手の温度感に合わせて話題を調整する柔軟性や、予期しない質問に対応する即興力も欠かせません。
能力を高めるためには、日々の業務でのフィードバックやトークの振り返りを継続する仕組みが必要です。経験を積み重ねながら精度を高めていくことで、成果につながるテレコールへと成長していきます。
成果を高めるテレコールの実践ポイント
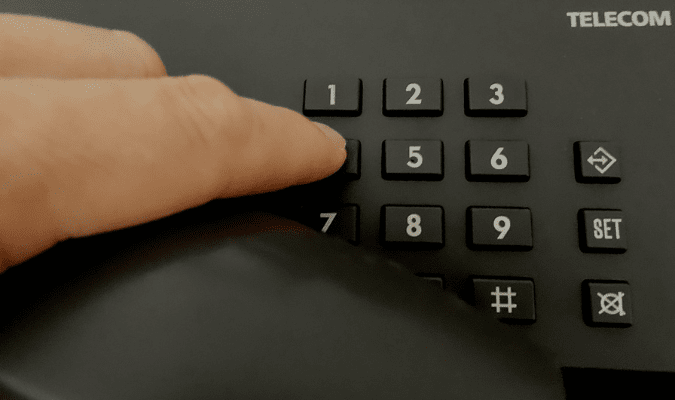
テレコールで安定した成果を上げるためには、単なる架電数の確保ではなく、戦略的なアプローチが求められます。リストの精度やトーク内容、実施のタイミングに至るまで、複数の要素を総合的に見直すことが重要です。ここでは、成果に直結する実践的な工夫を紹介します。
ターゲットを明確にしたリスト作成
テレコールの効率と成果を大きく左右するのが、アプローチ先のリスト精度です。誰に対して電話をかけるのかが明確でなければ、いくら巧みに話せたとしても成果にはつながりません。
業種や役職、過去の接点、検討状況など、複数の条件でターゲットを絞り込んだうえでリストを作成することが重要です。また、展示会やセミナーで得た名刺情報をそのまま使用するのではなく、事前にオンラインで企業情報を確認するなど、リストの事前整備も成果向上に寄与します。
さらに、社内での共有ルールを明確にすることで、属人的な運用を避け、一貫性のある活動につなげることができます。精度の高いリストを基盤とすることが、無駄な架電を防ぎ、実効性の高いテレコールを実現する第一歩です。
ターゲティングについて、もう少し詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
営業ターゲティングスキル:効果的な顧客層選定と売上余地の発見
話す内容の精度を上げるスクリプト作成法
会話の質を左右するのが、事前に用意されたトークスクリプトです。とはいえ、ただ読み上げるだけのマニュアルでは、相手に不信感を与えることも少なくありません。重要なのは、想定される質問や反応に対するパターンをいくつも準備しておくことです。
たとえば、導入の挨拶から本題への入り方、興味を引くフレーズ、断られた際の切り返しなど、各ステージでの台詞を柔軟に選択できる設計にしておくことが求められます。また、商品やサービスの特性に合わせて、複数のバージョンを用意しておくと効果的です。
スクリプトはあくまで「会話の土台」であり、活用する担当者が自分の言葉として自然に話せるよう工夫することが欠かせません。実践を重ねて都度改善を加える運用が、成果を支える要素となります。
成果を左右するベストな架電タイミング
どれほど魅力的な提案をしても、相手の都合に合わない時間帯に電話をかけてしまえば、その価値は半減します。テレコールでは、時間帯や曜日、業種ごとの対応傾向を踏まえた戦略的なタイミングの見極めが重要です。
たとえば、飲食や医療系ではピークタイムを避けるべきですし、管理職層であれば朝の会議前後や夕方の落ち着いた時間帯が適していることもあります。また、過去の通電記録をもとに最も反応が得られやすい時間帯を分析することで、次回の架電精度をさらに高めることが可能です。
「時間を読む力」は、数をこなすだけでは身につかず、継続的な分析と仮説検証によって培われていきます。タイミングの選定を戦略的に考えることが、テレコールの成果に直結する要素となります。
相手の心をつかむトーク技術
電話越しに相手の注意を引き、関心を持ってもらうためには、第一声からの印象が極めて重要です。話し方や声のトーンだけでなく、伝える順番や情報の取捨選択も工夫する必要があります。
たとえば、冒頭の名乗りと要件を明確に伝えたうえで、相手にとっての利点を端的に示すことで、話を聞いてもらえる可能性が高まります。さらに、相手の反応を観察しながらテンポを調整する柔軟性や、沈黙を恐れず間を活かす余裕も欠かせません。
一方的に話すのではなく、会話のキャッチボールを意識した構成にすることで、信頼関係を築きやすくなります。言葉選びや共感を示すひとことが、思わぬ成果につながることもあります。経験だけでなく、繰り返しのトレーニングによって身につくスキルです。
活用すべきテレコール支援サービスとツール

テレコールを効果的に運用するには、人的努力だけでなくテクノロジーや外部支援の活用も視野に入れる必要があります。属人性を抑えつつ再現性を高めるためには、ツール導入や専門機関の利用が重要です。ここでは、業務を支える代表的な支援手段を紹介します。
営業支援ツール(SFA・CRM)の活用
テレコール業務を効率化するうえで欠かせないのが、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理システム)です。ツールを活用することで、顧客情報の一元管理が可能となり、担当者ごとの対応履歴やステータスを簡単に把握できます。
たとえば、過去にどのような会話をしたか、直近の対応がいつだったかといった情報を即座に確認できれば、より適切なトーク内容を準備することができます。また、タスク管理やレポート機能を使えば、業務の抜け漏れを防ぎ、定量的な成果把握も可能です。
さらに、メール配信やWebアクセス履歴と連携することで、ホットリードへの優先的アプローチも実現できます。情報の見える化と共有によって、個人依存を排除した、組織全体での営業力強化が図れます。
SFA・CRMについて、もう少し詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
テレコール代行サービスを活用するメリット
営業リソースが不足している、あるいは専門性の高い対応が求められる場面では、テレコール業務を外部に委託することが効果的です。代行サービスを活用することで、経験豊富な専門スタッフによる架電が可能となり、アポイント獲得や見込み顧客のスクリーニングがスムーズに進みます。
また、社内でノウハウが不足している場合でも、テンプレートやトーク設計まで含めた支援を受けられるため、早期立ち上げが期待できます。ただし、委託する際には、業務範囲の明確化や報告体制の確認が重要です。
品質を担保するうえでは、KPIの設定や定期的なフィードバックも欠かせません。必要に応じて一部の業務だけを切り出すなど、柔軟な活用ができる点も、代行サービスの大きな利点です。
研修やコンサル会社によるスキルアップ支援
テレコールの成果を安定的に高めるには、担当者のスキル向上が不可欠です。したがって、多くの企業では外部の研修や営業コンサルティングを取り入れるケースが増えています。
専門機関が提供するトレーニングでは、ロールプレイングや録音フィードバックを通じて、実践的なスキルを身につけることができます。とくに、課題別・業種別にカスタマイズされたプログラムであれば、自社の状況に合わせた強化が可能です。
また、マネージャー層を対象とした研修では、成果分析や育成ノウハウも習得できるため、現場全体の底上げにも効果的です。社内だけでは難しい体系的な育成環境を整える意味でも、外部の知見を取り入れることは重要な選択肢となります。継続的な教育体制を確立することが、安定的な成果につながります。
展示会後のリードナーチャリングにおける活用
テレコールは、展示会やセミナーといったイベント施策のアフターフォローにも有効です。来場者から得た名刺情報やアンケート結果をもとに、関心度の高い顧客に優先的に架電することで、タイミングを逃さず商談化の可能性を高めることができます。
また、イベント時には話を聞くだけにとどまった参加者に対しても、テレコールを通じて再接触を図ることで、検討のきっかけを提供できます。とくにリードナーチャリングの観点では、複数回にわたる接点の構築が重要になるため、継続的なフォロー体制の一部としてテレコールを位置づけると効果的です。
メールや広告だけでは補えない「人の声」を活用することで、印象の強化や関心の掘り起こしが可能になります。イベント施策と連携させた運用が成果を左右するでしょう。
インサイドセールス部門との連携強化
テレコールの運用効果を最大化するには、社内の他部門との連携が重要です。とくにインサイドセールス部門との協働により、顧客対応の精度とスピードが大きく向上します。
インサイドセールスは、テレコールで得られた情報をもとに、商談につながる見込み顧客を育成・管理する役割を担います。両部門が情報を共有し、リードの状態や対応履歴を把握することで、アプローチの重複や対応漏れを防げるでしょう。
また、ツールを活用してデータ連携をスムーズにすれば、状況に応じた役割分担も明確になります。たとえば、初回接触はテレコールが担当し、一定の関心を示した顧客はインサイドセールスに引き継ぐといった分業体制も有効です。業務の境界を越えた連携こそが、成果の質と量を押し上げる要因になります。
テレコール導入で営業成果を最大化するには

テレコールの導入は、単なる施策ではなく、営業戦略の一部として体系的に運用される必要があります。成果を出すには、実行体制や人材育成、マネジメントの仕組みまで視野に入れた整備が重要です。ここでは導入後に効果を最大化するための視点を紹介します。
社内での運用体制の整備
テレコールを本格的に運用するには、専任チームの設置や社内ルールの整備が求められます。属人的な活動では対応品質や成果にばらつきが生じやすく、継続的な改善も難しくなります。
したがって、まずは目標・役割・評価基準を明確にしたうえで、部門横断的な連携体制を築くことが重要です。たとえば、マーケティング部門と営業部門の間にテレコール専任チームを配置することで、リード対応の初動が速まり、営業部隊への受け渡しもスムーズになります。
また、通話記録や対応履歴を共有できるツールを導入し、情報の見える化と一元管理を進めることで、部門間の無駄なやり取りも削減されます。体制を整備することは、テレコールの成果を継続的に生み出す土台づくりにつながるでしょう。
マネジメントの役割と評価指標の設定
テレコールチームを適切に機能させるためには、管理者によるマネジメントが欠かせません。とくに、評価の基準が曖昧なままでは、担当者のモチベーションが低下したり、目標との乖離が発生する可能性があります。
架電数やアポイント獲得数だけでなく、会話の質や改善行動も含めた多面的な評価項目を設定することで、公平かつ継続的な成果につなげやすくなります。また、週次・月次でのレビューを実施し、成果の振り返りと次回施策への反映を習慣化することも有効です。
マネージャーは現場の状態を把握するだけでなく、改善策を提示し、必要に応じてリソースの再配分を判断する役割を担います。数値の管理だけにとどまらず、育成やチームビルディングの視点も含めた運営が求められます。
成果が出るまでの育成期間の見極め
テレコールでは即時の成果を期待しすぎると、担当者の離職や活動の形骸化につながるリスクがあります。とくに未経験者を中心とした体制では、育成期間に一定の時間がかかることを前提に設計する必要があります。
目先の数値にこだわりすぎず、最初はプロセス目標を中心に設定し、段階的に成果目標へと移行する流れが理想です。また、ロールプレイングやOJTによってトークスキルや判断力を養う機会を定期的に設け、個人の成長を中長期で支援する体制も欠かせません。
習得のスピードには個人差があるため、画一的な基準ではなく、各自の進捗に応じた指導が求められます。焦らず、着実にスキルを高められる環境づくりが、定着率の向上と成果の安定につながります。
営業組織全体での目標共有
テレコールが組織内で孤立した取り組みになってしまうと、成果が上がりにくくなる傾向があります。営業活動全体の流れの中で役割を定義し、他部門と共通の目標を共有することが成果創出のポイントです。
たとえば、営業部門と連携してKPIを設定することで、アポイントの質やリードの状態に関する共通認識が生まれます。また、マーケティング部門と協力してキャンペーン情報を連携すれば、通話の質が高まり、相乗効果が期待できます。
目標の共有は、各部門が連携して顧客対応に取り組む意識を育てる土壌にもなるでしょう。全体最適の視点で業務を設計し、それぞれの活動が成果へとつながっている実感を持てる仕組みが必要です。
現場と経営の連携による継続的改善
現場の努力を確実に成果へとつなげるためには、経営層と実行部隊の間に密接な情報共有が求められます。経営陣がテレコールの実情や課題を正しく把握していなければ、投資判断や方針策定にズレが生じ、組織全体の方向性に影響を及ぼします。
たとえば、現場で上がった改善提案を速やかに反映する仕組みを持つことで、テスト的な施策を短期間で繰り返す「高速PDCA」が可能です。また、経営側が意識的に現場を視察したり、成果を評価する場を設けることで、担当者の意欲向上にもつながります。
経営と現場の距離を縮め、双方向のフィードバックを促進する文化が根付けば、組織としての柔軟性や成長スピードが格段に上がります。継続的な成果を生むには、全社的な巻き込みが不可欠です。
まとめ
テレコールは、見込み顧客との関係構築や商談化の起点として、今なお有効性の高い営業手法です。短期間で接点を持ち、相手の課題感や関心度をつかむうえで役立つ一方、成果につなげるには明確なターゲティングや通話内容の精度が欠かせません。
さらに、SFA・CRMの活用やインサイドセールスとの連携など、組織全体で支援体制を整える必要があります。属人化を避けながら、成果の再現性を高めるためには、ノウハウの蓄積と改善サイクルの確立が求められます。
営業体制を強化したい企業にとって、運用ノウハウや実行支援に長けたパートナーの存在が、取り組みの成否を大きく左右します。実行力と戦略性の両立を実現することで、営業活動全体の成果を最大化していきましょう。
セールスアセットでは、営業部門の立ち上げから実行支援、成果分析、運用の内製化に至るまで、テレコールを含む営業活動を包括的に支援しています。単なる代行ではなく、貴社のビジネスモデルや課題に応じた設計と、現場に根差した伴走体制によって、実効性の高い営業組織づくりをサポートします。
これひとつで
営業参謀のすべてが分かる!
BtoB営業組織立ち上げ支援サービスの内容や導入事例、料金プランなど営業参謀の概要がまとめられた資料をダウンロードいただけます。



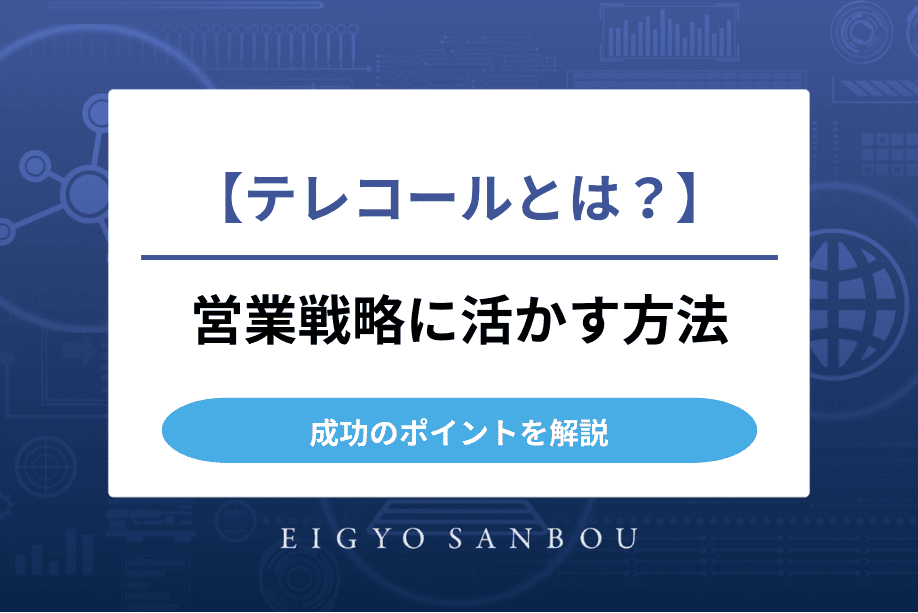
 ツイートする
ツイートする シェアする
シェアする LINEで送る
LINEで送る URLをコピー
URLをコピー