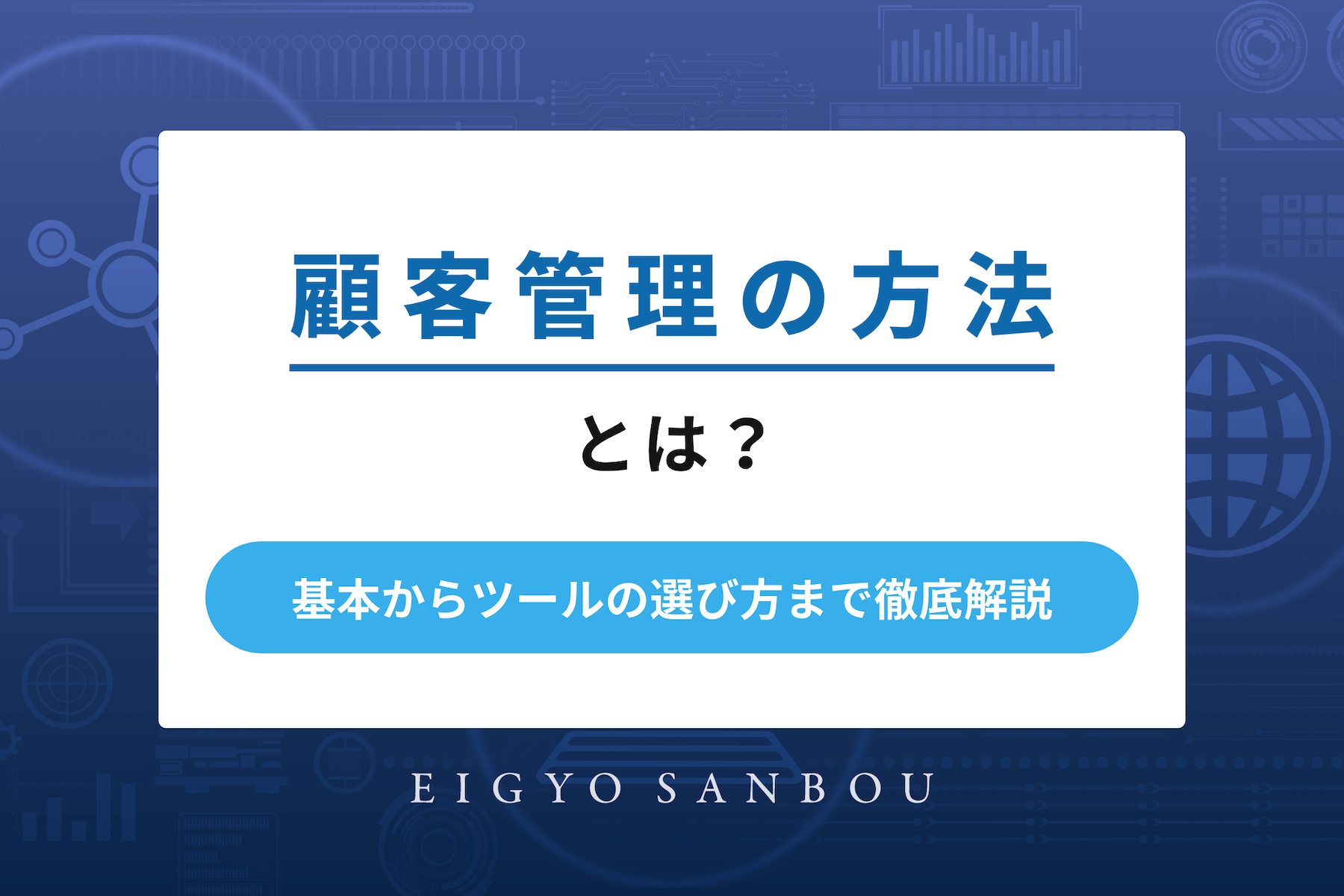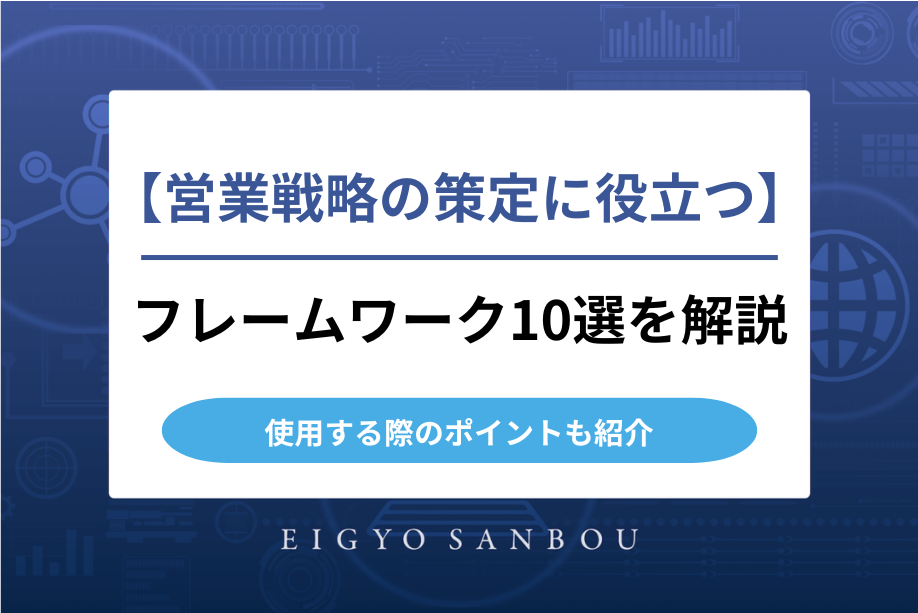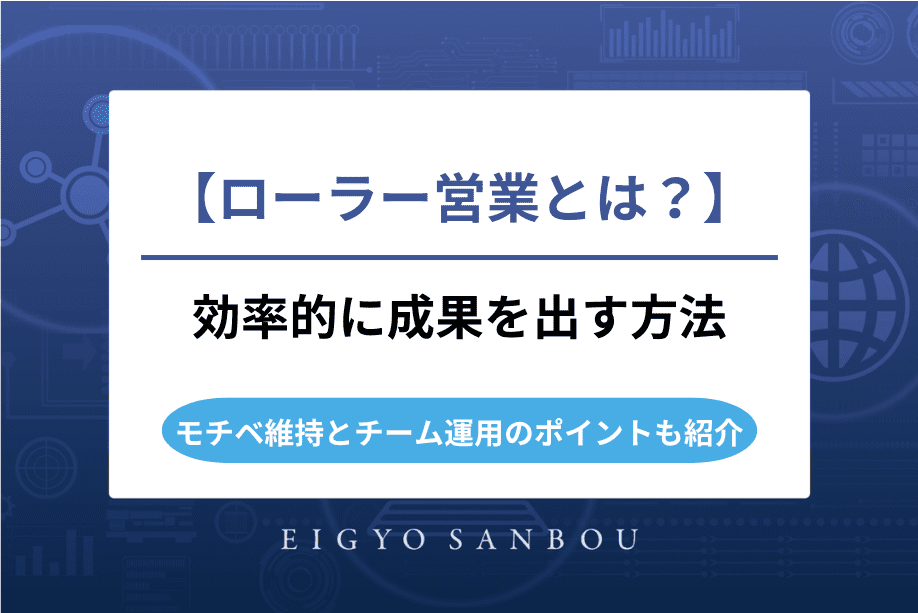法人営業は、担当者の能力だけでなく、企業全体の戦略設計が成果を左右します。とくにBtoBの領域では、複数の決裁者が関与する長期的な商談プロセスに対応するため、明確な方針と一貫性のある営業活動が欠かせません。
感覚に頼った属人的な営業手法から脱却し、組織全体で成果を出すためには、戦略的な視点が求められます。本記事では、営業戦略をどのように設計し、実行へと落とし込むかについて、基本視点から応用施策まで詳しく解説していきます。
▶貴社の事業成長を営業の側面からサポートするパートナーサービス『営業参謀』についてはこちら
営業でお悩みのことありませんか?
目次
BtoBの営業戦略設計で押さえるべき基本要素

営業活動を効率化し、安定的に成果を生み出すためには、戦略の土台となる思考の軸を明確にすることが不可欠です。BtoB営業の特性を理解したうえで、どのような視点で戦略を構築すればよいのかを整理しておくと、実務への展開がスムーズになります。ここでは、法人営業における戦略設計で欠かせない5つのポイントについて詳しく説明していきます。
意思決定者との接点を構造的に捉える
法人営業では、提案を行う相手がそのまま契約の決裁者とは限りません。実際には現場の担当者から始まり、課長や部長、最終的には役員や経営層にいたるまで、複数の人物を通過するケースが一般的です。
したがって、どのタイミングで誰と接触し、どのような情報を提供するかを整理しておくことが求められます。情報の内容や表現方法を、相手の役職や立場に合わせて調整することも大切です。たとえば、担当者には業務改善の視点から話を進め、経営陣には事業インパクトや収益性に焦点を当てた資料を用意すると、意思決定が進みやすくなります。
提案先の構造を見える化し、ステークホルダーごとの課題や価値観を把握することで、より確度の高い営業活動が可能となります。全体の意思決定プロセスを俯瞰し、段階的に信頼を積み重ねる視点が欠かせません。
関連記事:インサイドセールスがBtoB企業で導入が増えている理由
見込み顧客のペルソナを具体化する
営業の成果を高めるには、誰に対して提案を行うのかを明確に設定する必要があります。法人営業では、単に業種や規模を分類するだけでは不十分であり、役職・業務内容・抱えている課題まで細かく想定することが重要です。
たとえば、「中堅の製造業で工場の生産管理を担当する課長」といった具体的な人物像を描くことで、提案内容の精度が格段に向上します。また、過去の商談データや受注履歴をもとに、購買に至った傾向を分析すると、より現実に即したターゲット像を構築できます。
ペルソナの設定は、営業活動の起点であり、コンテンツ設計やチャネル選定にも影響を与えるため、できる限り詳細に定義することが欠かせません。明確なターゲットがあることで、情報提供や提案タイミングの判断も的確になり、商談の効率が高まります。
関連記事:BtoB向け営業代行会社!おすすめの活用事例から注意点まで紹介
購買行動の背景にある課題を可視化する
BtoB領域での購買は、製品そのものの性能や価格だけでは決まりません。むしろ、企業が解決したい課題や、中長期的な事業目標にどのように貢献できるかが重視される傾向にあります。
したがって、見込み顧客の業務上のボトルネックや部門間の連携課題など、表面的なニーズの奥にある本質的な要因を探る姿勢が求められます。営業担当者は、商談やヒアリングの際に得た情報を整理し、課題を仮説立てて言語化することで、より具体的な提案が可能です。
たとえば、「業務の属人化が進み、引き継ぎに時間がかかっている」といった背景がある場合、単なる業務改善ソリューションではなく、マニュアル化支援や教育体制強化も視野に入れた提案ができるでしょう。購買に至るまでのプロセス全体を可視化し、何に困っているのかを明らかにすることが、信頼獲得の第一歩になります。
関連記事:インサイドセールスで成果を上げたい!成功に必要なコツを解説
営業チャネルと手法を最適化する
法人営業において、顧客と接点を持つ手段は多岐にわたります。テレアポやメール、展示会、ウェビナー、さらにはパートナー経由の紹介まで、手法ごとに強みや効果の出やすいタイミングが異なります。
すべてのチャネルを同時に運用するのは現実的ではないため、自社のリソースやターゲットの特性に合わせた選定が重要です。たとえば、情報収集段階の企業にはオウンドメディアやホワイトペーパーを活用し、比較検討中の企業にはインサイドセールスを通じたフォローアップが有効です。
また、接点の数だけでなく、質にも着目する必要があります。一度のやりとりで信頼関係を築けるチャネルと、何度も接触して関係性を深めるチャネルでは、アプローチの設計も変わってきます。目的に応じたチャネル設計を行うことで、営業効率を高めることができるでしょう。
インサイドセールスについて、もう少し詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
自社と競合の違いを言語化する
法人営業では、顧客が複数の提案を比較検討してから意思決定を行うケースが一般的です。競合他社と同じような特徴や訴求ポイントでは、印象に残ることは難しく、選定の候補から外れてしまう可能性もあります。そこで、自社の製品やサービスが持つ独自の価値を、相手に伝わる表現で明示することが必要です。
たとえば、「カスタマイズ性が高い」と一言で伝えるのではなく、「導入後も自社の業務フローに合わせた柔軟な調整が可能であり、現場の運用定着率が高い」といった具体的な説明があると、印象が大きく変わります。
また、全社で共通のメッセージを持ち、一貫した説明ができるように準備することで、営業チーム全体の信頼感も向上します。価値を比較の軸にできるよう、他社との違いを整理しておくことが商談成功のポイントです。
BtoB営業戦略の設計プロセス

法人営業で成果を出すには、思いつきではなく体系的な戦略設計が欠かせません。営業活動のすべてを論理的に組み立てることで、再現性のある仕組みが実現できます。ここでは、営業戦略を構築する際の具体的な手順を5つのプロセスに分解し、それぞれの役割と進め方を明確にしていきます。
営業戦略の目的と達成基準を明確に設定する
戦略を設計する際の出発点は、何を実現したいのかという目的を明確にすることです。売上拡大や新規顧客の獲得、既存顧客の深耕など、目指す成果によって取るべき施策は大きく変わります。目的を定めることで、営業活動の方向性が定まり、チーム全体の行動も統一されやすくなります。また、定量的な達成基準を設定することも不可欠です。
たとえば、「半年以内に新規顧客からの売上を20%増加させる」といった具体的な指標を設けることで、進捗の管理や改善の判断がしやすくなります。目標は曖昧にせず、誰が見ても判断できる状態に落とし込むことがポイントです。全員が共通のゴールを持つことで、行動にブレが生じにくくなります。
現状分析を通じてボトルネックを洗い出す
目的が決まったら、次は自社の営業活動における現状を客観的に把握するステップに移ります。成約率が低下しているのか、商談数が不足しているのか、あるいはアプローチ先が適切でないのかなど、課題の所在を明確にすることで、的確な改善策が立案しやすくなります。
現場のヒアリングや過去データの分析、競合との比較など、複数の視点から問題点を特定していきましょう。たとえば、インバウンドの問い合わせは増えているにもかかわらず、商談化率が低い場合、初期対応やヒアリング手法に課題が潜んでいる可能性があります。
現状の課題が明らかになれば、優先順位をつけてアプローチを改善するための指針が見えてきます。表面的な数値だけでなく、その裏にある構造的な問題に目を向けることが重要です。
ターゲティングとKPIを整合させる
営業戦略の精度を高めるには、誰を対象とするのかというターゲット設定と、達成すべきKPIを一致させて設計する必要があります。たとえば、年間100社の新規開拓を目指す場合、対象企業の属性・予算・業界動向を明確にしなければ、行動量ばかりが増えて成果につながらないリスクがあります。
KPIの設定では、リード数やアポイント件数といった中間指標と、最終的な受注件数や売上額とをセットで管理することが大切です。また、ターゲットとの接点を増やす方法だけでなく、関係構築や提案力の向上によってKPIの質を高めることも検討すべき要素となります。
ターゲットの特性と営業チームのリソースを考慮しながら、現実的かつ成果に直結するKPIを設計しましょう。
営業活動とマーケティングの導線を整理する
営業とマーケティングは連携することで、大きな相乗効果を生み出します。しかし、両者が別々の目標で動いている場合、リードの質が低かったり、商談につながらないケースが増える可能性があります。
営業活動の前段にあたるマーケティング施策と、商談以降を担う営業の役割を明確に区分けしながら、スムーズな連携体制を整えましょう。たとえば、見込み客の行動データを営業側で活用することで、提案内容の個別最適化が進みます。
加えて、営業から得られた顧客の声をマーケティングにフィードバックすれば、より精度の高い集客施策が可能です。部門をまたぐ情報共有を仕組み化し、役割の重複や認識のズレを防ぐことが成果の安定化につながります。
改善サイクルを回す仕組みを用意する
戦略は設計して終わりではなく、実行後に必ず振り返りを行い、改善を重ねることで完成に近づきます。そのためには、PDCAを機能させる仕組みづくりが欠かせません。ただの数字の集計にとどまらず、実行した施策がなぜ成功したのか、あるいはなぜ成果が出なかったのかを言語化して蓄積する必要があります。
定期的なレビュー会議や、各施策ごとの成果分析レポートを共有することで、営業チーム内の学習サイクルを促進することができます。また、改善点が見つかった場合は、すぐに次のアクションへ反映するスピード感も必要です。成功と失敗の両方から学び続ける姿勢が、営業組織としての成長を支える土台となります。
BtoBにおける営業戦略で活用される代表的フレームワーク

BtoB営業における戦略設計では、経験や勘に頼らず、客観的な分析をもとに施策を組み立てることが重要です。そこで有効なのが、体系的に構造を整理できる戦略フレームワークの活用です。ここでは、法人営業でとくに有効とされる代表的な5つのフレームワークについて、それぞれの目的と実践方法を解説していきます。
3C分析で市場構造と競争環境を把握する
営業戦略を立案する前に必要なのが、市場環境を客観的に捉えることです。3C分析は、「市場(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の3つの視点から環境を整理するフレームワークです。
市場分析では、ターゲットの購買傾向や意思決定プロセス、業界全体の動向を読み取ります。競合分析では、主要プレイヤーの強みや弱点を把握し、差別化のヒントを見つけ出すことが重要です。そして自社分析では、自社の技術・実績・営業体制の強みと課題を明確にします。
この3つの要素を同時に比較することで、取るべきポジションが浮き彫りになります。たとえば、「競合は低価格を武器にしているが、対応の柔軟性が低い」という場合には、自社のカスタマイズ性を軸に営業方針を設計する判断ができるでしょう。
SWOT分析で営業リソースの活用軸を見出す
SWOT分析は、自社の営業活動を内部要因と外部要因に分けて評価し、戦略の方向性を定めるための手法です。Strength(強み)とWeakness(弱み)を自社の内部要因として洗い出し、Opportunity(機会)とThreat(脅威)を外部環境の変化として認識します。
たとえば、自社の強みが「特定業種における高い知見」だとすれば、その業種に対する営業強化を図ることができます。一方で、営業人員のリソースが限られている場合には、新規開拓と既存顧客フォローのバランスを見直す必要があるかもしれません。
SWOTを単体で見るだけでなく、組み合わせたTOWS分析へ展開することで、強みを活かしながら外部機会にどう乗るか、弱みをどのように補うかといった戦略が具体化されていきます。
STPでセグメントごとの訴求を最適化する
STPとは、セグメンテーション(Segmentation)、ターゲティング(Targeting)、ポジショニング(Positioning)の頭文字を取ったフレームワークであり、BtoB営業におけるターゲット設定の精度を高めるために活用されます。
まず、市場全体を業種・規模・課題などの軸で分類し、それぞれのセグメントの特性を明確にします。次に、どのセグメントに営業リソースを集中するかを決めることで、無駄のない効率的なアプローチが可能です。最後に、選定したターゲットに対して、自社の価値をどう伝えるかというポジショニング戦略を定義します。
たとえば、「サポート体制を重視する中小IT企業向けの信頼性重視ソリューション」といった形で、自社の立ち位置を明確に示すことで、競合との差別化が図れます。
バリュープロポジションを営業資料に落とし込む
営業活動の中核となるのが、自社が提供する価値を明確に伝える、バリュープロポジションです。顧客が抱える課題に対して、どのような手段で、どのような成果を提供できるのかを一言で表現できると、営業の説得力が飛躍的に高まります。
バリュープロポジションキャンバスというテンプレートを用いると、顧客の期待・不満・目標を整理し、それに対する自社の解決手段を体系的に構築できます。営業資料を作成する際は、この枠組みに沿って構成すると、話の流れが論理的になり、受け手の理解も深まりやすいでしょう。
単なるスペック紹介ではなく、顧客視点で「なぜこの製品・サービスなのか」を訴求する姿勢が重要です。提案の質が高まることで、商談の進行スピードにも良い影響が生まれます。
営業戦略に活用できるフレームワークについて、もう少し詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
BtoB営業の成果を高めた企業事例に学ぶ実践ポイント

戦略やフレームワークを学ぶだけでなく、実際に成果を出した企業の取り組みからヒントを得ることが、営業活動の改善に直結します。ここでは、具体的な企業事例をもとに、営業体制の強化や成約率の向上に成功した5つのアプローチを紹介します。
マーケティングオートメーション導入で商談数が増加した
ある中堅IT企業では、マーケティングオートメーション(MA)ツールの導入によって、見込み顧客との接点を増やし、商談化数を大幅に向上させることに成功しました。従来は営業部門がリストに対して一斉にアプローチを行っていたため、関心度の高い顧客を見極めることが難しく、非効率な営業活動が続いていました。
MAを活用することで、資料請求やサイト閲覧といった行動ログから、興味の高いリードを自動で抽出し、ホットリードへの優先アプローチが実現したのです。営業とマーケティングの連携もスムーズになり、リードごとに最適なタイミングと内容でアプローチできるようになったことで、商談化率が2倍近くに改善されました。
結果として、限られたリソースでもより成果に直結する営業活動を展開できるようになったのです。
営業プロセスを明文化して対応のバラつきを減らした
ある製造業では、営業担当者ごとにアプローチ方法が異なり、商談の進め方や提案内容にばらつきが生じていたことが課題となっていました。そこで、受注までの営業プロセスを標準化し、社内で共有可能な営業マニュアルを整備する取り組みを始めました。
各フェーズで行うべき行動や、ヒアリング項目、提案資料の構成などを具体的に定めたことで、新人営業でも一定の品質を保った対応が可能となり、成約率の安定が実現したのです。営業活動における迷いが減り、顧客対応にも一貫性が生まれたため、顧客からの信頼度も向上しました。結果として、個々のスキルに依存しない、再現性のある営業体制を構築できたことが、全体の受注件数の増加につながっています。
顧客インタビューを通じて訴求力を再構築した
BtoB向けサービスを展開するベンチャー企業では、製品の訴求軸が曖昧で、見込み客からの反応が得られない状況が続いていました。営業資料の刷新を検討するにあたり、実際の顧客数社に対してインタビューを実施したところ、導入の決め手となった要素が「サポート体制」や「導入後の柔軟性」にあることが判明したのです。
これを機に、訴求ポイントを機能紹介から導入後の成果・安心感に切り替えたことで、提案の説得力が増し、商談の歩留まりが大きく改善されました。また、顧客のリアルな声を反映した事例資料を営業資料として活用したことで、提案時の共感を得やすくなりました。顧客起点での情報設計が営業成果の向上に寄与した好例といえるでしょう。
既存顧客の深耕によりリピート率を向上させた
新規開拓に注力していた建設系企業では、既存顧客へのアプローチが手薄になっていたことが課題となっていました。顧客データを分析した結果、リピート率が20%以下に留まっていたことから、フォローアップ体制の見直しに着手したのです。
担当者ごとのフォロー漏れをなくすために、定期面談やニュースレターの配信をルール化し、提案のタイミングを見直しました。加えて、過去の提案履歴をもとにアップセルやクロスセルの余地を可視化したことで、1顧客あたりの売上単価も上昇しました。
結果として、既存顧客からのリピート率が半年で40%を超えるようになり、安定的な売上基盤を構築することに成功したのです。深耕営業の仕組み化が、事業の持続性を高めるポイントになった好例といえるでしょう。
オンライン営業で移動時間を削減し、受注率を改善した
全国に営業拠点を展開するサービス業の企業では、営業担当者の移動にかかる時間が長く、訪問件数や提案回数に限界がありました。こうした背景から、オンライン商談の導入に踏み切り、営業活動の非対面化を進めました。
結果として、1日の提案数が従来の2倍近くに増加し、フォロー対応のスピードも向上したのです。オンライン形式に適した資料や画面共有の工夫を行ったことで、商談の質も保つことができました。
さらに、顧客側も訪問の調整が不要となり、検討スピードが上がったことで、受注までの期間が平均20%短縮されました。営業効率の改善はもちろん、顧客体験の向上にもつながったことが、最終的な受注率の上昇につながっています。
BtoBにおける営業戦略の実行で成果を出すための注意点

営業戦略を構築するだけでは成果に結びつきません。計画通りに実行され、継続的に改善されて初めて結果が伴います。しかし、現場ではさまざまな障害や見落としによって、せっかくの戦略が形骸化するケースも少なくありません。
ここでは、営業戦略を現場で確実に機能させるために注意すべきポイントを5つに整理し、実行力を高めるための視点を紹介します。
営業活動の属人化を可視化ツールで防ぐ
属人性が強い営業活動は、一部の人材に業績が依存する不安定な体制につながります。担当者ごとのやり方が異なると、成果の再現性が低くなり、組織としての成長が阻害されやすくなります。
これを防ぐためには、営業支援ツールや顧客管理システムを活用し、誰が何をしているかを見える化することが効果的です。たとえば、営業日報をデジタルで記録し、チーム全体で進捗や対応履歴を共有することで、引き継ぎやサポートがスムーズになります。
また、商談の要点や提案資料も一元管理すれば、ナレッジが個人に留まらず、チーム全体で活用可能になります。データの蓄積は、成果の分析や改善施策の根拠にもなるため、業務の透明性と効率性を同時に高める手段として有効です。
担当者のスキル差を研修で均質化する
営業活動の成果は、担当者のスキルによって大きく左右されます。とくにBtoB営業では、顧客との信頼構築や課題把握力、提案内容の組み立て方など、幅広いスキルが求められます。個人の経験値に頼っていては、組織としての営業力は安定しません。こうした状況に対応するためには、教育制度や定期的なスキルアップ研修の導入が有効です。
たとえば、ロールプレイを取り入れた実践形式の研修や、実際の商談を録画してフィードバックする仕組みを整えることで、スキルの可視化と強化を同時に進められます。さらに、ベテラン社員によるナレッジの共有会やマニュアルの整備も、全体の底上げに貢献します。個人任せにせず、全社でスキルを磨ける環境づくりが重要です。
ターゲットのミスマッチを定期的に修正する
営業戦略で設定したターゲットが、実際の営業現場にマッチしていない場合、いくら行動量を増やしても成果に結びつきにくくなります。市場環境や顧客のニーズは日々変化するため、ターゲット設定は一度決めて終わりではなく、定期的な見直しが必要です。
たとえば、過去6ヶ月の受注企業の傾向を分析し、属性・業種・意思決定の傾向を洗い出すことで、新たなターゲットセグメントを再定義できます。また、営業現場からのフィードバックをマーケティング部門と共有することで、集客の質も向上させることが可能です。
設定したターゲットが適切かどうかを数値や現場の声で検証し、ズレが生じていれば速やかに修正する判断力が求められます。
営業ツールに依存しすぎない判断基準を設ける
デジタルツールの導入が進む一方で、ツールへの依存が進みすぎると、営業本来の判断力や提案力が損なわれるリスクも存在します。たとえば、スコアリング機能の数値だけを鵜呑みにしてアプローチ先を決定してしまうと、本来重要だったはずの案件を見落とす恐れがあります。
ツールはあくまで補助的な存在であり、最終的な判断は営業担当者自身の洞察や経験に基づいて行う必要があるのです。ツールの数値を参照しつつも、顧客との会話内容や商談の流れなど、定量では測れない情報を統合して判断する視点が欠かせません。
営業チーム全体で、ツールと現場感覚のバランスを取るガイドラインを整備しておくと、判断の質が安定します。
顧客の声を戦略にフィードバックする運用を設計する
営業現場で得られる顧客の声は、営業戦略をブラッシュアップするうえで極めて貴重な情報資源です。しかし、その内容が戦略に活かされないまま個人の記録に留まってしまっているケースも多くみられます。
これを防ぐには、顧客とのやりとりを定期的に集約し、戦略担当者と共有する運用ルールを設ける必要があります。たとえば、定例会議で商談内容を共有し、傾向や変化をデータベース化することで、ターゲットの見直しや訴求内容の改善に役立てることができるでしょう。
顧客からの反応や要望は、施策の評価軸にもなり得るため、継続的にフィードバックを受け取れる体制を整えておくと、営業活動の質が向上します。現場で起きている事実を戦略に反映させることが、継続的な成果につながります。
まとめ
BtoB営業戦略では、属人的な手法から脱却し、組織的かつ再現性のある仕組みを整えることが不可欠です。意思決定者との接点設計や顧客ペルソナの具体化、課題の可視化を行い、チャネルや訴求ポイントを最適化することで成果につながります。
さらに、3C・SWOT・STPなどのフレームワークを活用し、現状分析からKPI設計、改善サイクルまで体系的に進めることが重要です。加えて、成功事例から学び、顧客の声を戦略に反映させる体制を整えることで、持続的な成長を実現できます。
セールスアセットでは、営業戦略の立案から実行、さらに内製化の支援まで一貫して対応しています。
これひとつで
営業参謀のすべてが分かる!
BtoB営業組織立ち上げ支援サービスの内容や導入事例、料金プランなど営業参謀の概要がまとめられた資料をダウンロードいただけます。



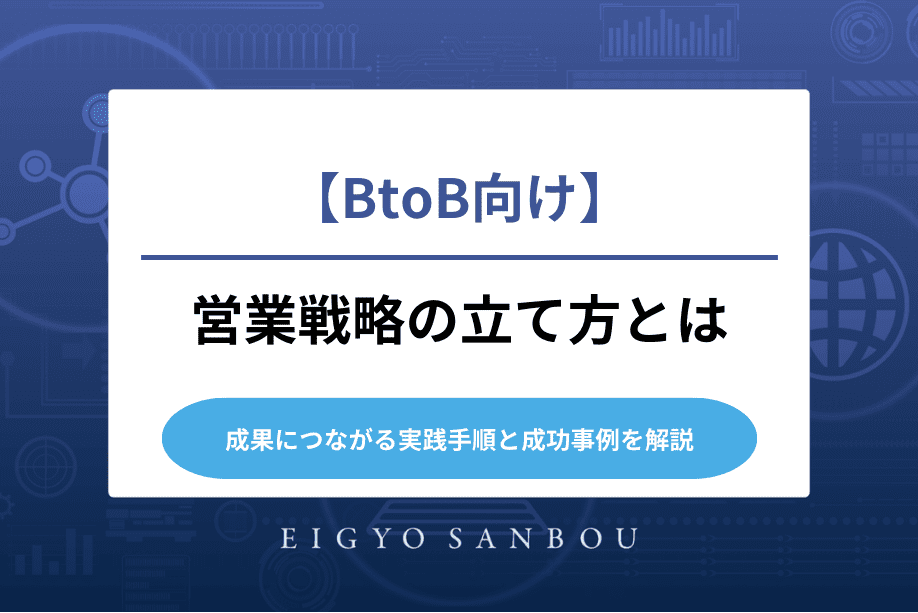
 ツイートする
ツイートする シェアする
シェアする LINEで送る
LINEで送る URLをコピー
URLをコピー