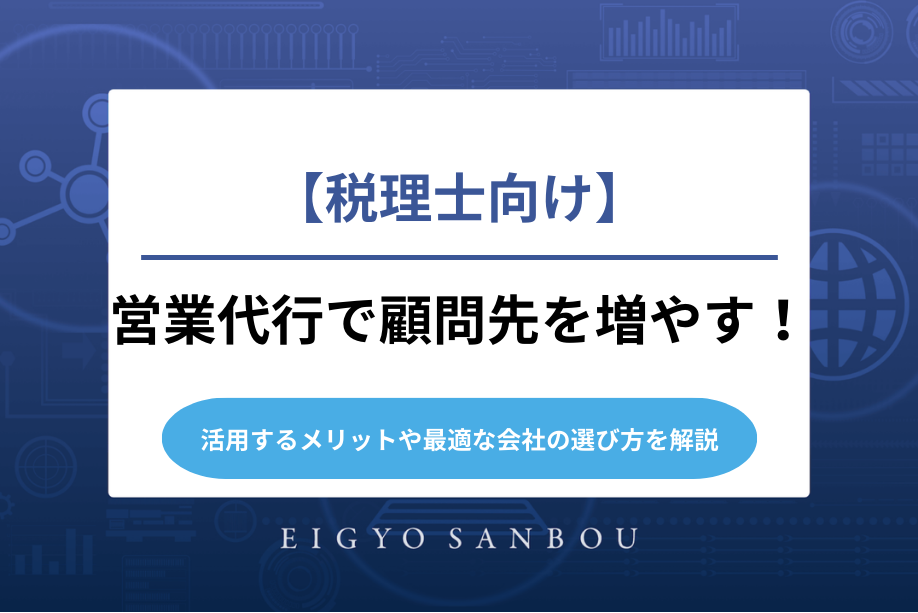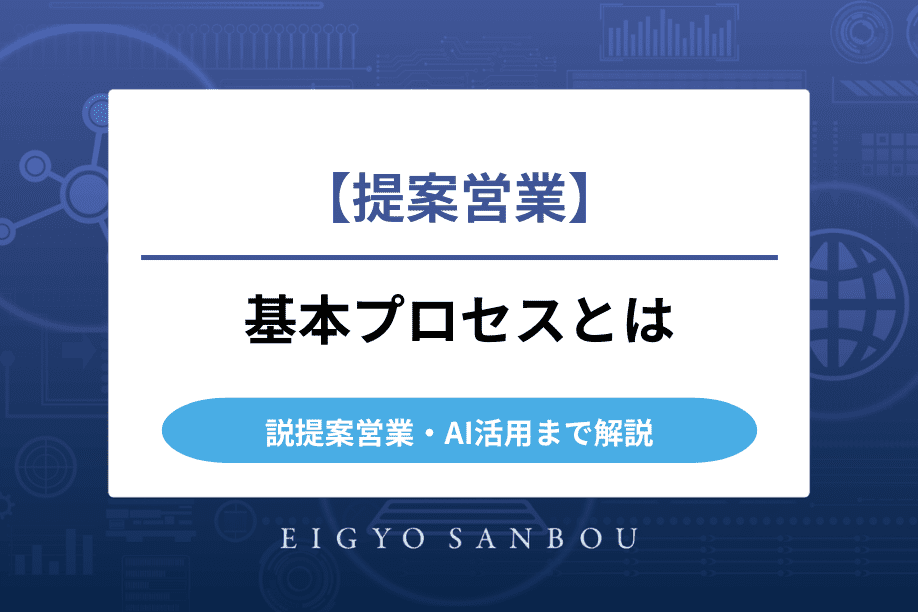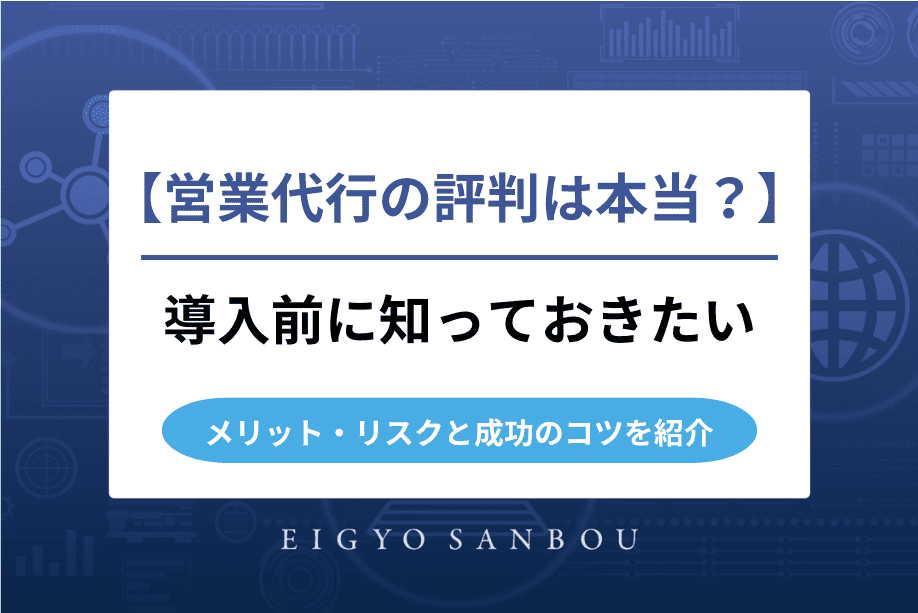営業現場では、提案や商談が順調に進んでいたにもかかわらず、最終的に契約に至らない「失注」が発生することは珍しくありません。成果につながらなかった要因を曖昧なままにしてしまえば、同じ失敗を繰り返すリスクも高まります。
しかし、失注は単なるマイナス要素ではなく、営業活動全体を見直す貴重なヒントでもあるのです。本記事では、失注の定義や主な原因、分析手法から改善策までを体系的に解説し、再現性のある営業力強化と売上向上を実現するためのヒントを紹介します。
▶︎貴社の事業成長を営業の側面からサポートするパートナーサービス『営業参謀』についてはこちら
営業でお悩みのことありませんか?
目次
失注分析の基本と重要性
失注分析の基本と重要性については、以下が挙げられます。
- 失注分析の定義と目的
- データに基づく営業戦略の重要性
失注分析の定義と目的
失注とは、商談や営業活動で契約や注文が取れなかった状態を指します。競合失注(明確な断り)である場合や、検討見送りとして保留になる場合もあるでしょう。
失注分析は、同じミスを防ぎ業務効率を高めるために重要で、営業戦略や製品の課題を明確にし、改善することが求められます。
関連記事:ビジネスモデルの作成・分析に役立つ5つのフレームワークを解説!
データに基づく営業戦略の重要性
ビジネスで迅速かつ効果的な意思決定を行うには、データ分析が重要です。
失注になった商談の履歴や顧客データを分析することで、失注になった要因仮説をたて、問題の特定と改善策をたてます。
関連記事:営業戦略におけるデータ分析の実践法|手法・指標・ツールを解説
そもそも営業における「失注」とは
営業活動における「失注」とは、提案や商談が進んだにもかかわらず、最終的に契約や受注に結びつかなかった状態を指します。顧客と何度もやり取りを重ねた結果であるため、営業現場では精神的ダメージも大きく、次の活動に影響を及ぼすこともあるでしょう。
失注は単なる結果ではなく、プロセス全体を見直すヒントが詰まった重要な情報源でもあります。どのタイミングで、どのような理由で機会を逃したのかを把握することで、今後の営業効率や成約率の向上につなげることが可能です。
分析せずに終わらせるのは、貴重な改善機会を見逃すことになりかねません。
主な失注の理由と予防策
商談が成立しない背景には、営業プロセスや提案内容に潜む複数の課題があります。ここでは、よくある失注理由を7つに分類し、それぞれに対する対処法を詳しく紹介します。
顧客に対する理解不足
ニーズを正確に把握できていない場合、提案内容が的外れになりやすく、商談が進展しません。表面的な情報だけで判断せず、顧客の業務課題やビジネス目標まで掘り下げる姿勢が求められます。
初回のヒアリング段階で課題の全体像を整理し、顧客が求めている本質的な価値にアプローチすることが重要です。定型的な提案では他社との差別化が難しく、相手の期待にも応えられないため、個別対応の精度を高めましょう。
関連記事:営業ヒアリングのコツとは?ヒアリングシートの項目や役立つフレームワークも紹介
不十分な信頼関係
関係構築が不十分な状態では、どれだけ魅力的な提案をしても受け入れられにくくなります。継続的なコミュニケーションを通じて信頼を積み重ねることが基本です。
たとえば、約束の納期を守る、連絡へのレスポンスを早めるなど、日常的な対応の積み重ねが評価につながります。関係性が構築できていれば、小さな懸念が生じた場合も相談されやすくなり、失注リスクを未然に抑えられるでしょう。
商談相手の選定ミス
提案先の担当者が決裁権を持っていない場合、どれだけ話が盛り上がっても契約には至りません。意思決定者と直接やり取りできなければ、判断に必要な材料が正しく伝わらず、結果として失注する可能性が高まります。
初期の段階で相手のポジションや決裁プロセスを確認することが不可欠です。BANT条件などのフレームワークを活用し、関係者の役割を明確にしましょう。
BANT条件については、下記の記事も参考になります。ぜひご覧ください。
営業ヒアリングのコツとは?ヒアリングシートの項目や役立つフレームワークも紹介
価格設定における顧客の不満
提案価格に対する納得感が得られない場合、価格そのものが障壁となって契約を見送られるケースが発生します。ただ安さを追求するだけでは利益を圧迫する恐れがあり、本質的な解決にはなりません。
むしろ、価格と価値のバランスを正しく伝えることが重要です。なぜその費用がかかるのか、どのような成果が期待できるのかを丁寧に説明しましょう。割引や特典に頼る前に、提案全体の価値を整理して伝えることで、価格への理解を深めるアプローチが効果的です。
競合との競り合い
他社と比較検討される場面では、差別化要素が見えにくい提案は埋もれてしまいます。機能や価格での優位性だけでなく、サポート体制や実績、導入後の効果までを含めて訴求する視点が求められます。
また、顧客の立場に立ったストーリー設計があれば、記憶に残る提案につながるでしょう。他社との単純な比較を避け、独自性をもった切り口で商談を進める工夫も必要です。
導入時期の不一致
相手の導入タイミングと営業の提案時期がズレていると、好意的な評価があっても契約に至らないことがあります。予算の都合や社内のスケジュールと合致していなければ、先送りされるリスクも高まります。
導入予定の時期や社内調整の状況を、早い段階で確認しておくことが重要です。無理に押し進めるよりも、次回提案の機会を設計し直す柔軟さが成果につながります。
費用対効果の説明不足
導入後の成果イメージが曖昧な場合、費用に見合う価値があるかどうか判断できず、決定が後ろ倒しになりやすくなります。製品やサービスの特徴だけでなく、それがもたらす成果や業務改善の効果まで具体的に示すことが求められます。
たとえば、同業他社での成功事例や数字を交えた効果予測があれば、説得力が増すでしょう。担当者が社内説明を行う際の材料を提供する視点で、提案を設計することも大切です。
失注分析で期待できる効果
失注の背景を詳細に掘り下げることで、営業活動の課題が明確になります。ここでは、失注分析によって得られる3つの具体的な効果を見ていきましょう。
現状の把握
失注分析を通じて、営業活動における現実の成果と課題を可視化できます。
たとえば、どの商談フェーズで失注が多いのか、あるいは特定の商品や業種で契約に結びつきにくい傾向があるかを把握することが可能です。勘や経験に頼った場当たり的な対応では見えづらい傾向も、データに基づいた分析によって客観的に浮き彫りになります。
現状を正しく認識することは、次の打ち手を誤らないための基盤となります。まずは何が起きているのかを定量的に把握する姿勢が、営業改革の出発点になるでしょう。
営業担当者が行う提案の改善
失注分析の結果は、担当者が行っている提案内容の見直しにも活かせます。
たとえば、過去の失注案件を振り返ることで、ヒアリングが甘かった部分や顧客の意図とずれた提案が行われていた場面が見えてきます。そうした反省点を基に、訴求ポイントや資料の構成、話し方まで改善することが可能です。
担当者ごとの傾向が把握できれば、トレーニング内容や同行サポートの方針も具体的に定めやすくなります。個人任せの営業から脱却し、営業組織全体で再現性のある提案力を育てる土台を築けるでしょう。
営業組織の体制強化に関しては、こちらの記事をご覧ください。
営業組織の体制構築の手順|組織力強化のポイント6選
ボトルネックの発見
商談が滞る原因は、個人のスキルだけに限られません。プロセスや体制に潜む構造的な問題も、失注分析によって明らかになります。
たとえば、見積もりの提示が遅れている、資料の更新が追いついていない、社内調整に時間がかかっているなど、現場では見過ごされがちな課題が蓄積している場合があります。
ボトルネックに気づくことで、業務フローやナレッジの共有体制を整備するなど、全社的な改善にもつながります。根本的な改革には、表面的な結果だけでなく過程に目を向ける視点が欠かせません。
失注分析の具体的手法とステップ
失注の背景を把握するためには、感覚的な判断ではなく、体系的な視点が求められます。ここでは、現場で活用できる6つの分析アプローチを紹介します。
ステージごとの分析を行う
商談がどの段階で頓挫したのかを整理することで、営業プロセス全体の改善点が浮かび上がります。
たとえば、初回訪問後の離脱が多ければヒアリング力の課題が考えられ、提案後に失注が目立つ場合は資料や説得力の不足が疑われます。各ステップを細かく分解し、フェーズごとの離脱率を可視化することで、対処すべきポイントを明確にできます。
感覚に頼らず、数値に基づく分析を行うことで、改善策の優先順位付けがスムーズになるでしょう。
属性ごとに割合を比較する
業種や企業規模、地域など、商談相手の属性別に失注率を集計することで、ターゲット選定や提案内容の見直しにつながります。
たとえば、特定の業界に対して失注が集中している場合は、提案内容がその業界のニーズに合っていない可能性があります。反対に、高い受注率を誇る層が見つかれば、今後の営業戦略を集中させる判断材料にすることも可能です。
属性別の傾向を把握することは、自社の得意分野と改善余地を同時に見つけるきっかけとなるでしょう。
営業担当別に分析する
営業パーソンごとの成約率や失注率を比較することで、チーム全体のパフォーマンスを客観的に把握できます。
たとえば、特定の担当者だけが失注を多く抱えている場合は、提案力やクロージング手法の見直しが必要かもしれません。逆に、成果を出している担当者のアプローチを分析すれば、他メンバーへの共有・教育に活かすことができます。
属人的な要素が強い営業活動こそ、定量的な視点を取り入れてバラツキを減らすことが大切です。
競合企業の傾向を見る
失注時に競合がどのような提案をしていたかを把握できれば、自社の立ち位置を見直すヒントになります。価格差や機能面の違いだけでなく、商談の進め方や訴求ポイントの違いを掘り下げることで、自社提案の改善材料が得られます。
競合が強い案件に共通する傾向を分析すれば、今後の差別化戦略の構築にも役立ちます。競合情報は営業の現場から得られる一次情報であるため、定期的に記録し、全社で共有する仕組みを整えておくと効果的です。
顧客獲得ソースから分析する
商談に至ったきっかけとなるチャネルごとに失注率を確認することで、マーケティング施策と営業活動の連動性を見直すことが可能になります。
たとえば、展示会経由の案件は関心度が高いが成約に至らないケースが多いなど、チャネル特性に応じた対応が必要になることもあります。効果の高い獲得ルートを強化し、成果に結びつきにくい導線は改善または見直す判断材料として活用しましょう。
失注の要因をヒアリングする
データだけでは見えてこない本音や背景を知るには、失注後のヒアリングが欠かせません。たとえば、「価格が高かった」という理由の裏には、納得感の不足や競合との比較など複合的な要素が隠れていることがあります。
実際に顧客から話を聞くことで、表面的な理由にとどまらない本質的な課題が明らかになります。ヒアリングは関係性を維持する手段にもなり、将来的な再提案のチャンスにつながる場合もあります。真摯な姿勢で対話を重ねることが重要です。
多面的な失注分析アプローチ
失注の原因は、外部要因と内部要因の二つに大別できます。
失注分析を行う際には、どちらの要因がより大きな影響を及ぼしているのかを理解することが出発点となります。
また、失注が発生したタイミングにも注意を払うことが重要です。なぜなら、タイミングによって失注の理由が異なる場合があるからです。
具体的に、多角的な失注分析アプローチについては、次のとおりです。
- 営業パーソン、プロセス、競合他社の比較分析
- 業界・セグメント別の受注率分析
内部要因:営業パーソン、プロセス、競合他社の比較分析
営業パーソン、プロセス、競合他社の比較分析は、内的要因に含まれます。内的要因とは、主に企業内部に関連する要素を指します。
例えば、営業担当者のアプローチ方法が適切でない場合や、提案内容の質が低い場合、さらには営業プロセス全体に課題がある場合などが考えられるでしょう。
また、提供しているサービスや製品そのものに問題があることも含まれます。これらの課題は、企業内部での分析と施策の見直しを通じて、改善することが可能です。
内的要因の検討では、失敗の原因が自社内に存在するかどうかを解明することが重要です。
内部要因の観点として、下記のような分類があげられます。
- 機能要因
- 営業要員
- ニーズ・予算の不一致
機能要因vs営業要因:主要な失注理由
失注要因は大きく分けて、製品やサービスの機能に関連する「機能的要因」と、営業プロセスに関する「営業的要因」の2つに分類可能です。
機能的要因による失注は、「導入費用や運用コストが高すぎる」「顧客が求める機能が製品に無い」「業務に必要のない機能が多すぎる」といったケースが該当します。
機能的要因は、製品自体の問題であるため、一見するとコントロールが難しいように思われます。しかし、営業のアプローチ次第では、改善の余地があることも少なくありません。
一方、営業的要因とは、営業活動そのものに問題があり、失注につながるケースを指します。
失注の原因をしっかりと分析し、適切な改善策を講じることが、次の商談成功につながるでしょう。
ニーズと予算不一致の問題
顧客のニーズと自社の提供価値が合わないと、契約を得るのは難しく、無駄な労力がかかってしまいます。
失注率が高い場合、案件の精度や選別に問題があるかもしれません。
また、予算感が合わないこともあります。ニーズや予算のミスマッチを事前に確認することが重要です。
外部要因:業界・セグメント別の受注率分析
業界別の受注率は外部要因に含まれ、これは自社以外の出来事によるものです。
顧客の環境や業界の動向、競合他社の戦略などが影響し、市場や業界のトレンドを理解することで、案件失敗の原因が明らかになります。
法律や規制の変更も商談に影響を与えることがあります。
真の失注理由を明らかにする手法
真の失注理由を明らかにする手法については、次のとおりです。
- 効果的なヒアリングとフィードバック収集
- 「価格が原因」の背後にある本当の理由を探る
効果的なヒアリングとフィードバック収集
ヒアリングの目的は、現在の問題点を明確にし、目標達成のための課題を設定することです。
失注になった顧客に対して、失注が決定するまでにコミュニケーションがある程度発生していれば、失注理由についてのヒアリングにも応じてもらえることが多いでしょう。
商談の場で失注が明らかになればその場でヒアリング、メール等後日連絡で失注が決定した場合は、可能であれば電話やWeb会議の場を設けて理由のヒアリングを行うことが望ましいです。
「価格が原因」の背後にある本当の理由を探る
顧客が「価格が原因」と断る場合、提案内容に他の心配や懸念がなかったか確認することが重要です。
価格以外の理由として、ニーズの誤解、説明不足、競合他社との比較、品質や機能性への不満などが考えられます。
選定基準を事前に確認し、これらの要因を踏まえて真の理由を効果的に聞き出しましょう。
失注分析のためのツールとテクノロジー活用
以下にて、失注分析のためのツールとテクノロジー活用について解説していきます。
SFA/CRMシステムの導入と活用法
営業管理システムとして、多くの企業がCRMやSFAツールを活用しており、失注分析において非常に有用です。
SFA/CRMシステムは、統計データを自動的に収集し、迅速にフォーマット化して視覚的に表示する機能を持っており、管理が容易になります。
そもそもSFAやCRMツールの主要な目的の一つは、営業活動を可視化することです。
営業担当者が提出する報告をカスタマイズできる機能が備わっており、失注分析に必要なデータや情報を取り入れることで、効果的に活用することができます。
新たにSFAやCRMツールを導入または変更することを検討している場合は、分析機能が優れたツールを選ぶことが重要です。ツールに関して詳しく知りたい場合は、以下の記事を参照してください。
営業支援とは:SFAとCRMを活用した効果的な営業活動の実現
AIを活用した自動分析と予測
失注要因の分類は手作業では時間と労力がかかりますが、AIを活用することで自動化でき、効率と正確性が向上します。
日本でもSFAやCRMの使用が一般的ですが、情報入力が負担となり、本来の業務に支障が出ることがあります。
AIを搭載したSFAやCRMは、データの迅速な作成・更新が可能ですが、まだ普及していないため、導入時には事前の確認が重要です。
失注後のアクションと失注を防ぐための事前対策
失注後のアクションと失注を防ぐための事前対策については、以下が挙げられます。
- 失注情報の共有と顧客との関係性維持
- 効果的な商談準備と提案力の強化
失注情報の共有と顧客との関係性維持
失注情報をセールスチーム全体で共有し、解析することが重要です。
原因を分析し、改善策を見つけるため、定期的なミーティングを活用します。
また、失注後も顧客との関係を維持し、信頼を深めることで、将来のビジネスチャンスを広げることができます。
効果的な商談準備と提案力の強化
失敗から学ぶことは、成功への重要なポイントです。
失注理由の分析から、提案する内容や顧客ターゲット、商品の設計の見直しが必要と思われる場合は改善を行い、成約率向上に活かします。
受注率を上げるためのテクニックに関しては、以下の記事を参照してください。
営業の受注率を上げるには?効果的な方法とテクニックを解説
失注分析を活かした営業DXと組織変革
失注分析を生かした営業DXと組織変革については、次のとおりです。
- データドリブンな営業体制の構築
- 営業とマーケティングの連携強化
データドリブンな営業体制の構築
データドリブンな営業とは、営業活動や戦略の策定において、経験や直感に頼るのではなく、実際のデータとその分析結果を中心に据える営業を指します。
この手法では、営業活動をデータに基づいて最適化し、その効果を確認することで、成果の向上を図ることが重要です。
具体的には、以下の方法が挙げられます。
- データ分析
- 顧客セグメンテーション
- パーソナライズドアプローチ
- 予測分析
- 営業プロセスの改善
このように、データドリブンな営業は、競争の激しいビジネス環境で優位に立ち、顧客満足度を高めるための重要なアプローチとなっています。
営業とマーケティングの連携強化
失注を減らすためには、営業とマーケティングの連携強化など企業全体で経営課題に取り組むことが不可欠です。
マーケティングでのメッセージングや、マーケティング活動で獲得する見込み顧客リストがそもそもターゲットに合っていなければ、その後の営業の成約率もあがりません。
顧客接点が多い営業からマーケティングにフィードバックを行うことで、マーケティングでより成約につながりやすい見込み顧客獲得につなげることができます。
まとめ
営業活動の効率化と売上の向上には、失注の原因をしっかりと分析することが非常に重要です。
失注の理由は「機能的な問題」と「営業の問題」に分類されますが、特に営業の問題については適切な対応を行うことで、大きな改善が見込めます。SFAを活用して失注原因を分析することにより、具体的な営業課題を特定し、効果的な改善策を見出すことが可能です。
また、DSRを併用することで、顧客の購入意欲やニーズをリアルタイムに把握し、失注のリスクを事前に回避することができます。
SFAに蓄積されたデータを活用することで、マーケティングと連携し、よりニーズに応えた製品の提供や、精度の高い営業活動が可能になるでしょう。
失注をチャンスと捉えて、営業活動を継続的にブラッシュアップしていきましょう。
セールスアセットでは、単なる業務代行にとどまらず、貴社のビジネスモデルや方針を深く把握したうえで、成果につながる営業戦略の策定から実行、将来的な内製化の支援まで一貫した対応が可能です。
事業の成長を共に目指す戦略的パートナーとして、実行力と提案力の両面からご支援します。
【貴社の事業成長を営業の側面からサポートするパートナーサービス『営業参謀』の資料のダウンロードはこちら】
【参考サイト】
これひとつで
営業参謀のすべてが分かる!
BtoB営業組織立ち上げ支援サービスの内容や導入事例、料金プランなど営業参謀の概要がまとめられた資料をダウンロードいただけます。



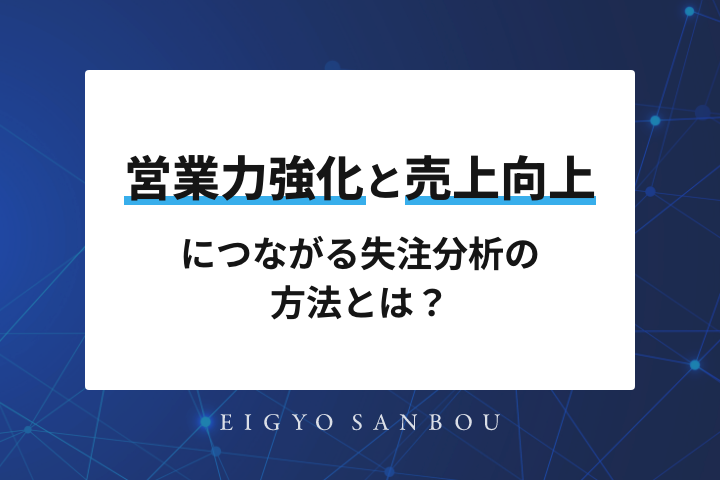
 ツイートする
ツイートする シェアする
シェアする LINEで送る
LINEで送る URLをコピー
URLをコピー