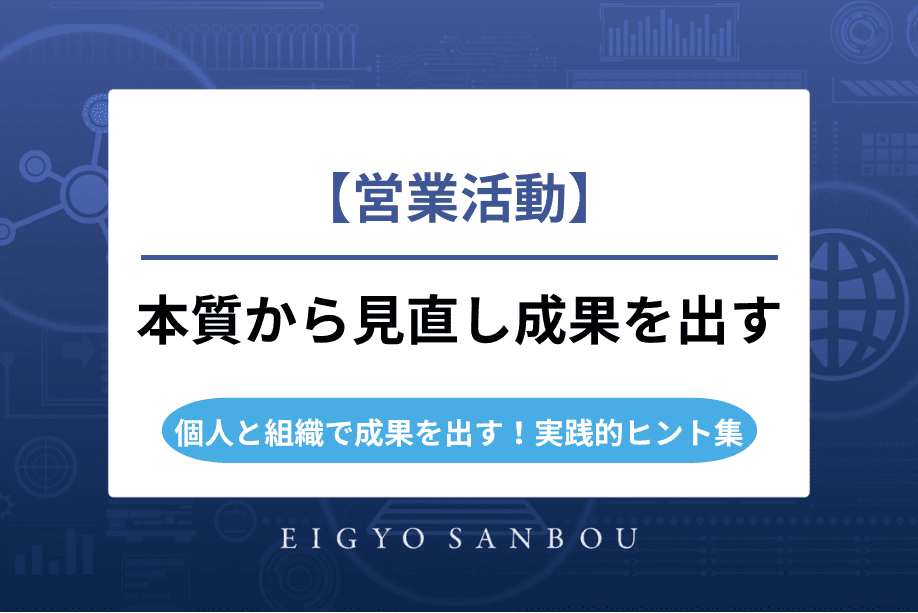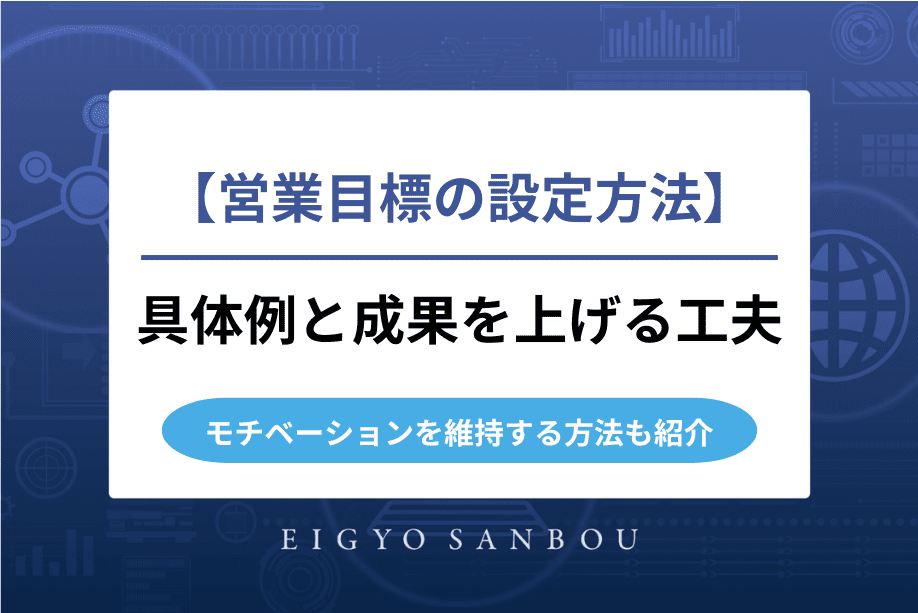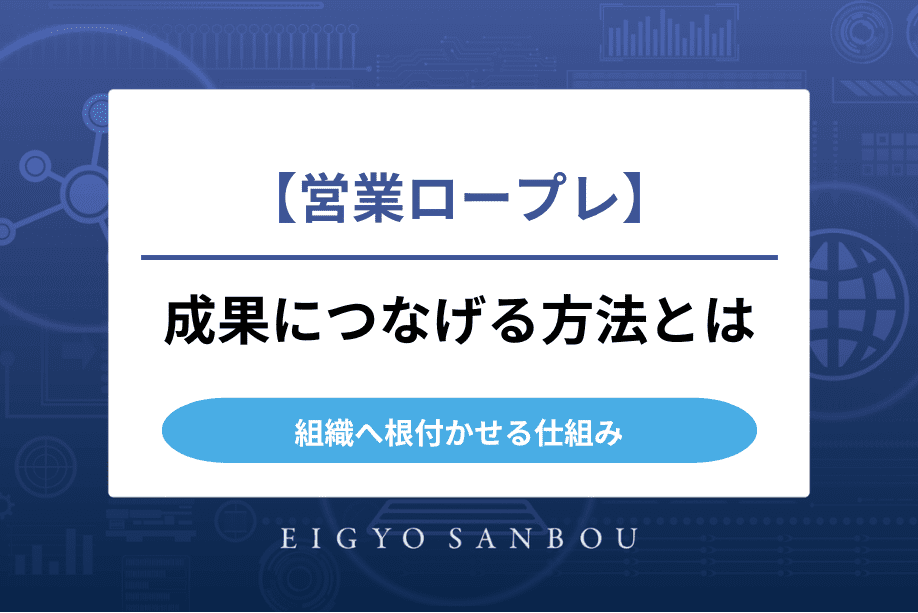新規事業を立ち上げる際、多くの企業が直面する最大の課題は営業活動です。既存事業では顧客基盤や実績が営業を支えますが、新しい取り組みではゼロから信用を築かなければなりません。さらに、勝ちパターンが存在しないため、顧客の反応を観察しながら提案や資料を修正する試行錯誤が続きます。
営業担当者には販売を超えた事業開発の視点も求められるでしょう。とはいえ、体系的なプロセス設計と複数チャネルの戦略的な組み合わせにより、着実に成果を積み上げることが可能です。本記事では、新規事業営業の特徴や戦略、実践方法を整理し、成功への道筋を解説します。
営業でお悩みのことありませんか?
目次
新規事業営業の特徴と既存事業との違い

新規事業の営業活動は、既存ビジネスの延長とは大きく異なる構造を持ちます。リード獲得手段の未成熟さや実績不足など、乗り越えるべき壁が多いためです。
したがって、既存事業で成果を上げた担当者であっても、新しい取り組みでは苦戦する場面が少なくありません。ここでは、新規事業に取り組む際に理解しておきたい三つの違いを整理し、営業活動の方向性を考える材料にしましょう。
商談獲得チャネルが安定しない理由
新規事業では、顧客との接点をどう確立するかが最大の課題になりやすいです。既存の事業では展示会や紹介制度、広告運用などで安定した商談獲得が可能なケースが多くみられます。しかし立ち上げ段階のサービスには、十分な予算も仕組みも整っていないことが一般的です。
担当者自身がテレアポやメール送付、SNS運用など多様な手段を試しながら成果の出るルートを探る必要が出てきます。とくに中小企業ではグループ会社からの顧客紹介も期待できないため、試行錯誤の繰り返しによって効率的なチャネルを見つけるしかありません。したがって、安定的な商談獲得は時間をかけて育てる要素だと理解しましょう。
勝ちパターンが存在しない段階での営業の難しさ
既存事業では「この業界にはこの提案が響く」といった定型の営業パターンが蓄積されていることが一般的です。対して新規事業では、まだ顧客実績がなく、市場の反応を確かめながら仮説を立てる段階が続きます。提案時に相手の反応を観察し、資料やトークを都度調整しなければ、手応えを得られません。商品やサービスそのものの改善が必要になる場合もあります。
さらに、ターゲット像が想定と異なる場合もあり、計画を柔軟に変更する姿勢が欠かせません。営業の現場を通じて学び、検証を重ねることが、やがて勝ちパターンの発見につながります。仮説検証を粘り強く繰り返すことが新規事業営業の本質的な難しさであり、同時に醍醐味でもあります。
関連記事:ターゲット戦略とトークスクリプトの強化で商談率向上:自社営業力強化を目指した伴走型支援
支援実績がなく信頼を得にくい状況への対応方法
立ち上げ間もないサービスでは、顧客に提示できる実績や導入事例が存在しないため、信頼獲得が容易ではありません。購入を検討する企業にとっては、「成果につながるのか」「費用に見合うのか」という疑問が自然と浮かびます。不安を払拭するためには、事業に込めた思いや開発の背景、期待される効果を論理的に説明することが欠かせません。
また、テスト導入や試用期間を設ける方法も信頼構築の助けになります。さらに、代表者やリーダー自らが商談に参加し、強い意欲と自信を伝えることも有効です。最初は地道な取り組みになりますが、少しずつ成果を積み上げることで、実績不足という弱点を克服できるでしょう。
新規事業営業に必要な戦略
新規事業の営業活動では、単純な販売スキルだけでなく、サービスや商品を事業として育てる視点が欠かせません。まだ勝ち筋が定まっていないため、担当者は実際の商談を通じて仮説を検証し、改善を重ねることになります。
そこで重要になるのが、資料の活用、顧客の声の収集、柔軟な姿勢、そして価格に依存しない信頼構築です。ここで具体的な考え方を整理し、営業に取り組む際の指針としましょう。
営業資料をベースに仮説検証を繰り返す
新しい事業では、どのような提案が顧客に響くかを探り当てる作業が必要です。そのためには、営業資料を基盤とした仮説検証が有効です。統一された資料を活用すれば、商談ごとに相手の反応を比較でき、改善点が明確になります。
さらに、資料を少しずつ修正しながら活用すると、どの説明や表現が相手に伝わりやすいかを把握できます。とくに立ち上げ期には、営業担当者ごとに説明がばらつくと正しい検証ができません。共通の資料を使って精度を高めていく必要があります。
将来的に新しいメンバーが加わった際にも同じ基準で説明できるため、組織全体の成長にもつながるでしょう。資料を通じて検証を積み重ねる姿勢が、勝ちパターンを早く確立するポイントになります。
関連記事:営業プロセス可視化の重要性 商談プロセスの型化・マネジメントする方法をステップで解説
顧客の声から改善点を見つける
新規事業の営業活動では、顧客から得られる生の反応が極めて貴重な情報源になります。商談で直接もらう意見はもちろん、ちょっとした表情や沈黙などの非言語的な反応からも多くを学べます。その中から「どの部分が理解されていないか」「どの説明に強い関心を持ったか」を把握することが重要です。
たとえば、長い説明に集中できていないと感じたなら要約を強化し、反対に事例紹介に興味を示したなら資料を拡充すると効果的です。さらに、複数の顧客から同じ反応が見られる場合、それは改善すべき確度の高いポイントになります。
加えて、得られた情報をチームで共有すれば、メンバー全体で営業力を高めることも可能です。顧客の声に耳を傾け、改善を重ねる姿勢が成約への近道となるでしょう。
事業開発の視点で柔軟に対応する
営業活動を単なる販売行為と捉えると、新規事業では壁にぶつかりやすくなります。なぜなら、提案が受け入れられなければ商品自体を変える必要が生じるためです。言い換えれば、新規事業の営業担当者は販売員であると同時に事業開発の担い手でもあります。サービス内容や料金体系を顧客の反応に合わせて修正することは避けられません。
加えて、最初に立てた仮説を固く信じすぎると市場の動向に対応できず、成長の機会を逃す恐れがあります。市場の変化を観察し、顧客からのフィードバックを積極的に取り入れる柔軟さを持つことで、提案の質は飛躍的に高まります。営業と開発を一体化した視点を持てば、結果的に事業の成長を後押しできるでしょう。
値下げに頼らずに信頼を築く
新規事業の立ち上げ段階では、成果を急ぐあまり値引きに走りがちですが、それは中長期的に大きなリスクを伴います。値段でしか判断されない関係ができてしまうと、顧客は簡単に他社へ流れてしまうからです。むしろ、サービスが提供できる価値を正しく理解してもらうことが大切です。
たとえば、継続利用や大規模契約など、合理的な理由があるときにのみ条件を調整する方が双方にとって健全です。営業担当者が自信を持って「自社の商品は投資に見合う」と説明すれば、その説得力が顧客にも伝わります。価格ではなく信頼に基づいた関係が構築され、安定した売上につながります。値下げに依存しない姿勢こそ、成長を支える基盤になるでしょう。
新規事業営業方法の具体的ステップ

新規事業の営業活動は、直感に頼った行動では成果が安定しません。市場調査から顧客像の設計、営業プロセスの最適化、目標設定、そして事例活用までを流れとして整理することが求められます。
段階ごとの役割を理解すれば、営業の方向性が明確になり、無駄な労力を削減できます。ここで具体的な流れを順を追って解説し、実践に役立つ視点をまとめましょう。
市場調査・競合分析から始める
営業を開始する前に、まず市場の全体像を調べる作業が欠かせません。市場規模、成長率、主要なプレイヤーを把握することで、参入余地を判断できます。加えて、競合の価格帯や販売方法を確認すると、自社の優位性がどこにあるかを発見しやすくなります。
たとえば、大手が高価格帯に集中しているなら、中価格帯に活路を見出す選択も可能です。さらに、参入障壁や顧客が抱える不満を探ると、営業時の訴求材料として有効に使えます。こうした調査を軽視すると、営業でどれほど努力しても成果につながりにくいのが現実です。
最初の段階で徹底的に情報を集める姿勢が重要になります。結果として、営業戦略の精度が格段に高まるでしょう。
ターゲットとカスタマージャーニーを設計する
市場の理解を深めたあとは、狙うべき顧客像を鮮明に描き出す必要があります。年齢や役職、業界といった属性に加え、購買の意思決定プロセスや導入シーンまで整理すると、より具体的な像が浮かびます。さらに、顧客が商品を知ってから契約に至るまでの過程をカスタマージャーニーとして図解すれば、営業の接点をどこで持つべきかが明確になるはずです。
たとえば、認知段階ではオンライン広告やイベント参加、比較検討段階では導入事例、最終決定ではコスト試算資料が効果的です。このように段階ごとの行動を整理すると、営業活動が点ではなく線としてつながります。加えて、顧客心理の変化を理解できるため、提案内容を最適化しやすくなるでしょう。
カスタマージャーニーマップの作り方を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
カスタマージャーニーマップの作り方と成功させるためのポイント
営業プロセスを可視化して最適化する
ターゲットを明確にした後は、営業プロセスの流れを整理しましょう。初回接触から契約までのステップを図式化すれば、停滞ポイントが浮き彫りになります。
たとえば、商談数は十分でも成約が少ない場合は、クロージング段階に課題があると分かります。反対に、問い合わせ数が伸び悩む場合は、認知施策を強化すべきです。
このように可視化して検証を続けると、無駄のない行動計画に修正できます。加えて、チームで共通認識を持てるため、メンバー間の連携もスムーズに進みます。プロセスを数値で追える形に整えることは、改善スピードの加速と、成果の安定化に直結します。
SMART原則を用いた目標設定を行う
営業活動を継続的に改善するには、達成可能で明確な目標設定が不可欠です。そこで有効なのがSMART原則です。具体性、測定可能性、達成可能性、関連性、期限設定という5つの要素を満たすことで、実行可能な目標に落とし込めます。たとえば「3か月以内に成約件数を5件増やす」と設定すれば、何をすべきかが明確になります。
さらに、進捗を定期的に確認すれば、計画の遅れを早期に修正できるでしょう。曖昧な目標ではチームが迷走しやすいため、明確な数値を伴った目標設定が重要です。加えて、短期的な成果だけでなく長期的な展望も組み合わせれば、組織全体のモチベーションも高まります。
事例を活用し顧客の不安を払拭する
新規事業の立ち上げ期は実績不足が大きな壁となります。そのため、最初に得た契約や小規模な導入成果であっても積極的に事例化して活用しましょう。導入前の課題、選定理由、利用後の効果を整理すると、説得力のある営業資料になります。たとえば「コスト削減率が20%向上した」といった具体的な数字を提示すれば、顧客の安心感が高まります。
さらに、事例を紹介することで「同じ課題を抱えている自分たちにも当てはまる」と顧客が想像しやすくなるでしょう。営業初期においては事例の数が少なくても構いません。小さな成果を積み上げ、実績として見せる姿勢が信頼の構築につながります。結果として、受注率の改善にも直結するでしょう。
新規顧客開拓の営業方法一覧

新規事業を成功させるためには、見込み顧客との接点をどのように作るかが大きな課題になります。営業チャネルを一つに依存してしまうと、獲得数が伸び悩んだときに停滞してしまいます。
そこで複数の手段を同時に試し、成果の出やすい方法を見極める姿勢が欠かせません。ここでは代表的な新規顧客開拓の方法を整理し、それぞれの特徴と活用のポイントを紹介しましょう。
テレアポを活用して直接接触する
電話によるアプローチは、古典的ながらも効果を発揮する方法です。直接声を届けられるため、相手の反応をリアルタイムで把握できます。ただし、短い時間で相手の関心を引き出す工夫が求められます。事前にターゲット企業を調査し、課題を予測して話を切り出すと、相手が耳を傾けやすくなるでしょう。
さらに、スクリプトを使って会話の流れを設計すれば、担当者ごとの差が少なくなり、検証も進めやすくなります。加えて、断られた場合も理由を聞いて改善に活かすと精度が向上します。成果が出るまで時間はかかりますが、継続すれば信頼構築につながるため、基礎的な手法として取り組む価値は十分にあるでしょう。
トークスクリプトについて、もう少し詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
メール営業で効率的にリーチする
メールを使ったアプローチは、時間や場所に制約されない点で効率的です。とくに法人営業では、担当者がすぐに電話に出られないことも多いため、メールは情報を届けやすい手段になります。ただし、一方的な宣伝文は読まれにくいため、相手の課題解決につながる内容を意識することが重要です。
たとえば業界の最新動向や調査データを添えて「こうした傾向がありますので検討に役立つ資料をお送りします」と提案すれば、関心を持たれやすくなります。さらに、件名の工夫によって開封率を高められます。
反応があった相手に対しては、早めに電話やオンライン面談につなげると効果的です。メール営業は費用対効果に優れるため、他の方法と組み合わせると成果が大きく広がります。
展示会やイベントを通じて関心層を集める
展示会や業界イベントは、見込み顧客が自ら情報を求めて訪れる場であるため、高い確度の商談につながりやすい手法です。実際に商品を見せながら説明できるため、理解を深めてもらいやすい点も魅力です。また、短期間に多くの担当者と接触できる効率性もあります。
とはいえ、ただ名刺を集めるだけでは成果につながりません。イベント終了後のフォロー体制を整え、タイミングを逃さずに連絡することが重要です。さらに、ブースのデザインや説明員のスキルが成果を左右するため、事前準備に力を入れる必要があります。
イベントをきっかけに得た接点を営業プロセスに組み込めば、継続的なリード育成にも発展するでしょう。
オンライン広告を用いて広く周知する
インターネット広告は、潜在顧客に対して短期間で広く認知を獲得できる手法です。検索連動型広告で課題を抱える層に直接アプローチしたり、SNS広告で特定の業界や職種に絞って配信したりと、ターゲティング精度が高い点が強みです。
もっとも、費用をかければ必ず成果が上がるわけではありません。広告文やクリエイティブの質、ランディングページの設計が結果を左右します。加えて、運用結果を定期的に確認し改善を重ねることが不可欠です。
とくに新規事業では、短期間で市場の反応を得られるため、初期段階の仮説検証にも役立ちます。広告を出すだけで終わらせず、成果データを営業活動にフィードバックする仕組みを整えましょう。
SNSやオウンドメディアを活用する
SNSや自社メディアを活用した情報発信は、信頼構築を兼ねた顧客開拓の手段として有効です。継続的に役立つ情報を発信すれば、潜在顧客との関係性が自然と深まります。
さらに、双方向のコミュニケーションが可能な点も特徴です。たとえばSNS上でのコメント対応やアンケートを通じて顧客の声を集めれば、商品改善のヒントを得られます。オウンドメディアに記事を蓄積すれば、検索経由での新規リード獲得にもつながります。
とはいえ、短期的な成果を狙う方法ではないため、他の施策と並行して進めるのが現実的です。信頼関係を育てる中長期的な基盤として取り入れれば、将来的に安定的な顧客獲得につながるでしょう。
営業改善策と組織づくり

新規事業の営業活動を軌道に乗せるためには、個々の努力だけでは限界があります。組織全体で改善を積み重ね、効率的な体制を築くことが成功への近道です。
成果を分析する仕組みや人材育成、部門間の連携強化などを組み合わせることで、継続的な成長を実現できます。ここでは営業を改善し組織を強化するための具体策を紹介しましょう。
データを活用した改善サイクルを回す
営業の改善には、感覚的な判断ではなく数値に基づく分析が欠かせません。受注率や商談数、リード獲得経路などを定期的に集計し、ボトルネックを特定することが大切です。たとえば「アポ獲得は多いが契約につながらない」という結果が出た場合、クロージングの説明力を強化する必要があります。
加えて、過去の成約案件を振り返り、成功要因を抽出すれば、再現性の高いプロセスを築けるでしょう。さらに、データをチーム全員で共有することで、改善の方向性が統一されやすくなります。データドリブンな姿勢を徹底すれば、属人的な営業から脱却し、組織全体の成果を安定的に伸ばせるでしょう。
教育とフィードバックで人材を育成する
新規事業の営業では、経験の浅いメンバーが中心になることも多いため、教育体制の整備が必須です。座学だけでなく、実際の商談に同席させるOJTを取り入れると学びが深まります。
さらに、商談後に先輩から具体的なフィードバックを受けることで、短期間でスキルが向上します。とくに提案資料の使い方や質問の切り返し方など、細かい点まで指摘することが有効です。
また、定期的にロールプレイを実施すれば、失敗を恐れず練習できる環境が整います。教育とフィードバックを繰り返し行う文化を作ると、組織の営業力が底上げされ、事業全体の成果も加速するでしょう。
部門間の連携を強化する
営業の改善を進めるうえで、営業部門だけが努力しても十分ではありません。開発やマーケティングと情報を共有し、組織横断的に課題に取り組むことが大切です。たとえば顧客から挙がった要望を開発に伝えれば、製品改善につながり、営業活動も進めやすくなるでしょう。
加えて、マーケティングと連携して認知施策を強化すれば、営業の負担が軽減されます。さらに、カスタマーサクセス部門と協力して導入後のサポート体制を整えると、継続利用率の向上にも直結します。部門間の壁を越えた連携が、組織全体の力を最大化し、新規事業を持続的に成長させる原動力になるでしょう。
営業組織の仕組み化を進める
新規事業では立ち上げメンバーの個人技に頼る場面が多くなりがちです。しかし、それでは規模を拡大する段階で限界が訪れます。成果を再現性のある仕組みに落とし込むことが重要です。たとえば、商談の進め方を標準化し、スクリプトやチェックリストを整備すれば、誰でも一定の成果を出せるようになります。
さらに、顧客情報をCRMに集約し、活動履歴を管理することで、属人化を防げるでしょう。仕組み化が進めば、新人が参加しても短期間で戦力化でき、組織の成長スピードが加速します。営業活動を個人の力量に依存させず、組織として成果を出す体制を構築することが、新規事業の持続的な発展を支える基盤となるでしょう。
まとめ
新規事業の営業は、既存ビジネスとは大きく異なる課題を抱えています。市場調査や顧客像の設計、営業プロセスの可視化などを通じて仮説を検証し、柔軟に改善を重ねる姿勢が成果につながるでしょう。
さらに、テレアポやメール営業、展示会やオンライン広告など、複数の手法を組み合わせることで顧客獲得のチャンスを広げられます。加えて、組織としてデータ活用や教育体制の強化を進めれば、個人に依存しない安定的な成長が実現するでしょう。
新規事業営業を成功させるためには、戦略的な思考と粘り強い実践が不可欠です。
セールスアセットでは、業務を請け負うだけでなく、貴社のビジネスモデルや方針を深く理解したうえで、成果につながる営業戦略の立案から実行、さらに将来的な内製化まで一貫して支援が可能です。
伴走者にとどまらず、事業成長をともに実現する戦略パートナーとして貢献します。
これひとつで
営業参謀のすべてが分かる!
BtoB営業組織立ち上げ支援サービスの内容や導入事例、料金プランなど営業参謀の概要がまとめられた資料をダウンロードいただけます。



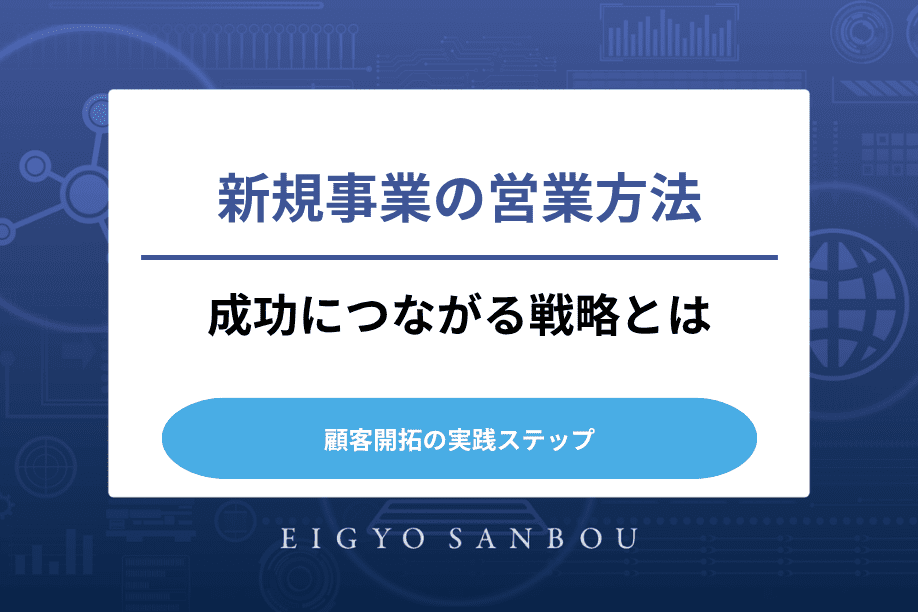
 ツイートする
ツイートする シェアする
シェアする LINEで送る
LINEで送る URLをコピー
URLをコピー