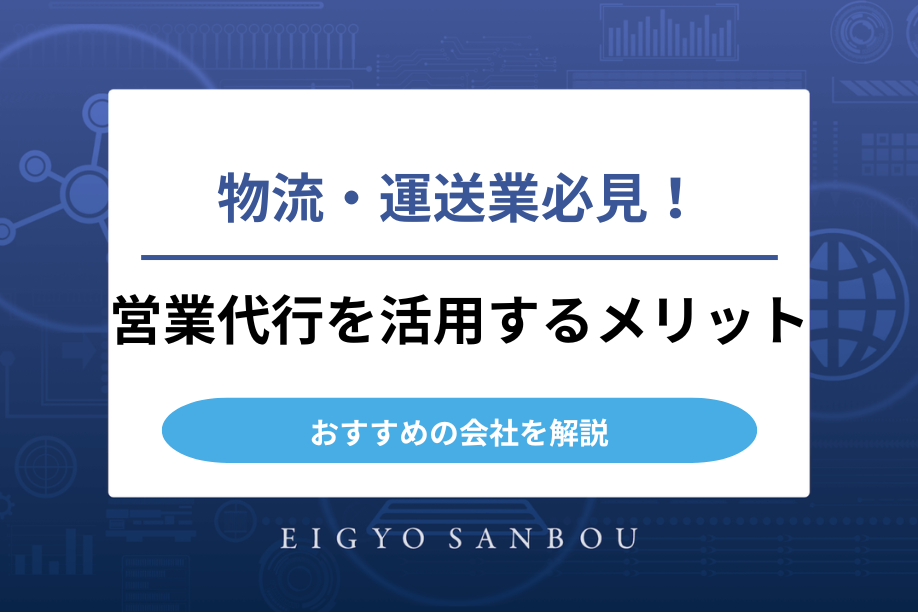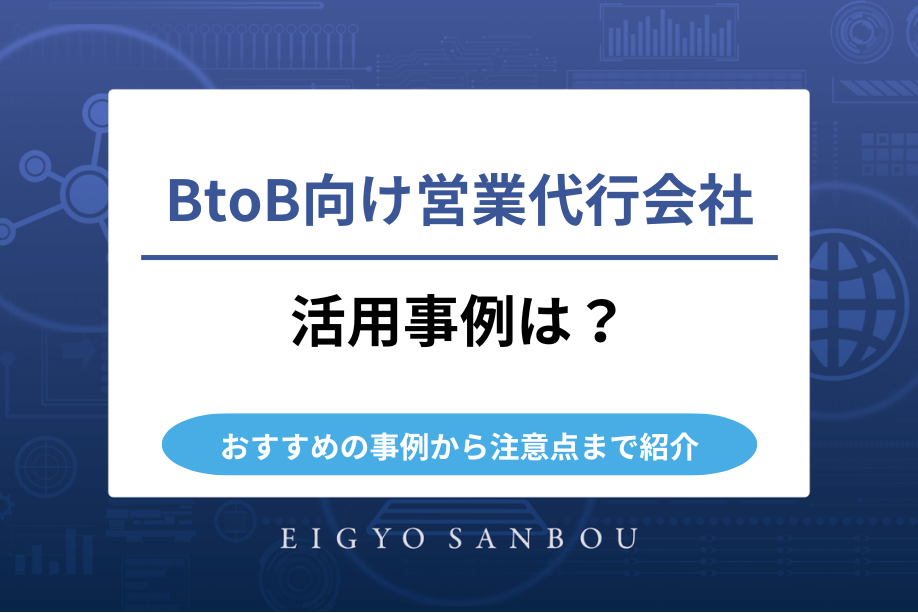営業の成果が伸び悩んだり、ライバル企業に顧客を奪われやすいと感じる状況は、決して珍しくありません。とくに、競争相手が多い市場や限られた戦力で挑む必要がある場面では、取り組み方そのものを根本から見直す必要が出てくるでしょう。
こうした課題に対する解決策として注目されているのが、理論的な数式モデルを背景に持つ「ランチェスター戦略」です。この戦略を営業分野に落とし込むことで、限られた人員や資源でも市場での勝負を有利に進めることが期待できます。
本記事では、ランチェスター戦略の考え方をベースに、強者と弱者それぞれに適した方針や、実践で活かせるフレーム・具体的な企業事例などを総合的に解説していきます。
▶貴社の事業成長を営業の側面からサポートするパートナーサービス『営業参謀』についてはこちら
営業でお悩みのことありませんか?
目次
営業戦略におけるランチェスター戦略とは

営業における競争で成果を上げるためには、戦術以上に「どのような戦略で市場に立ち向かうか」が重要です。ランチェスター戦略は、企業の立ち位置や強みを客観的に把握し、市場で優位に立つための理論的な指針を示しています。ここでは、まずランチェスター戦略の基礎を整理し、なぜ営業戦略において効果を発揮するのかを解説していきます。
ランチェスター戦略の起源と基本原理
ランチェスター戦略は、第一次世界大戦中に英国のエンジニアであるフレデリック・ランチェスターによって提唱された「戦闘における力の法則」に由来します。彼は軍事的な兵力と戦闘力の関係を数式化し、戦力の集中が戦闘結果に与える影響を明らかにしました。
これを企業活動に応用することで、経営資源が限られた企業であっても、特定領域に集中すれば競争優位を築けるという考え方が生まれました。とくに営業分野では、戦略が市場シェアの獲得や顧客基盤の構築に直結するため、実践的な意義が高いとされています。
経営資源の選択と集中によって成果を最大化できる構造は、変化の激しい現代においても通用する理論です。
関連記事:セールスコピーとは?売れる仕組みと営業戦略をつなぐ方法を解説
第1法則と第2法則の違い
ランチェスター戦略には大きく分けて2つの法則があり、異なるシーンで適用されます。第一法則は、個別の接触や小規模な市場での戦いにおいて有効です。たとえば、一人ひとりの営業担当者がどれだけ顧客に影響を与えられるかが成果を左右する場合に適しています。
対して第二法則は、マス市場や大規模な集団戦における競争を想定したものです。メディアを活用した認知戦略や資本力に物を言わせた大量接触型の営業などが該当します。2つの法則を理解することで、自社のポジションや市場規模に応じた正しい戦略選択が可能になります。理論を使い分けることが、成果の分かれ道となるのです。
なぜ営業戦略に有効とされるのか
営業という領域では、接触頻度やターゲットの絞り込み、人的資源の使い方が成果に直結します。ランチェスター戦略は、こうした営業活動の本質に対して合理的な考え方を与えてくれる点が大きな魅力です。特定の地域や顧客層に戦力を集中させることで、リソースを分散させずに高い成果を狙えます。
加えて、戦力差がある中でも勝機を見いだすための方法論としても機能します。営業力で劣る企業が市場で存在感を出すには、相手の強みに正面から立ち向かうのではなく、ニッチな領域や接点に注力することが有効です。ランチェスター戦略は、戦うべき場所と方法を明確にすることに貢献します。
営業とマーケティングにどう影響するか
営業活動とマーケティング戦略は、しばしば分断されがちですが、ランチェスター戦略を取り入れることで両者の連携が促進される効果があります。たとえば営業側が弱者としての戦略を取る場合、マーケティングは対象顧客の細分化や認知の最適化に注力する必要があります。
反対に、強者の立場であれば、認知拡大を最優先としつつも市場全体への継続的なアプローチが欠かせません。営業戦略とマーケティング施策は互いに影響を与え合いながら成果を導くものであり、その統一感を持たせる上でランチェスター戦略は有効な枠組みとなります。
また、活動の整合性が取れることで、部署間の連携や目標達成に向けた意識統一にもつながりやすくなります。実践にあたっては、役割ごとの優先順位を明確にした上で施策を設計するとよいでしょう。
関連記事:営業企画とマーケティングの違いとは?棲み分け方や協力するポイントも解説
強者と弱者で異なる営業戦略の考え方

営業活動を成功させるには、市場での立場を把握したうえで適切な戦略を採用する必要があります。支配的なポジションにある場合と、競合に囲まれている状況とでは、目指すべき方向性が根本的に異なるためです。
ここでは、組織の位置づけをどう判断するか、強者・弱者それぞれに適した戦略、そして誤った選択によるリスクについて整理していきます。
自社が強者か弱者かを見極めるポイント
営業戦略を立てるうえで最初に行うべきことは、自社の市場内におけるポジションを明確にすることです。具体的には、対象エリアでのシェア率、競合他社との力関係、ブランドの認知度などを総合的に確認する必要があります。
たとえば、業界内で影響力を持ち、多くの顧客から安定した支持を得ている状態であれば強者に分類されます。一方で、知名度が限られ、資源も潤沢とは言えない場合は、弱者と捉えるのが妥当です。
事業の成長段階や営業拠点の規模も参考にすべき指標といえます。どのような状況にあっても、現状を冷静に見つめ直すことで、戦略の方向性が自ずと定まります。
関連記事:営業戦略の策定に役立つフレームワーク10選と使用する際のポイントを解説
強者に適した営業戦略の特徴
市場で高いシェアを保持し、競争優位にある企業は、広範囲をカバーする営業戦略が適しています。たとえば、人的リソースを活かした大量訪問や、ブランド力を前面に押し出した営業アプローチが有効です。
加えて、複数のチャネルを駆使した全方位型の施策を組み合わせることで、競合の参入を阻止する効果も期待できます。また、認知度の高い企業であれば、標準化された提案内容でも一定の成果が得られるケースが多くみられます。
現在の地位に甘んじず、常に顧客ニーズの変化や新規プレイヤーの動向に目を向けることが必要です。強者にとっての戦略は「守り」と「攻め」のバランスを取りつつ、持続的な優位性を維持する視点が求められます。
弱者が成果を出すための戦術とは
強大な競合が存在する市場で成果を出すためには、限られた資源をどこに集中させるかが重要です。弱者にとって有効なのは、エリアや業種を絞ったニッチ戦略です。具体的には、自社が得意とする課題領域に対して深い提案を行い、個別対応による信頼獲得を図ります。
差別化の軸を明確に打ち出すことができれば、規模で劣る立場でも選ばれる可能性が高まります。営業活動では、特定の業界や商圏において継続的な訪問や情報発信を行い、密着型の関係を構築することが効果的です。
価格競争ではなく価値訴求で勝負することが求められるため、ヒアリングや提案力の向上が重要なテーマとなります。弱者の営業戦略では、無理な拡張よりも、絞り込みによる深堀りが成功の道につながります。
間違いやすい戦略選択とそのリスク
営業戦略において最も避けるべき失敗の一つが、自社の立ち位置を誤って判断することです。強者ではないのに強者の戦略を採ると、リソース不足によって成果が伴わず、組織に負荷がかかります。
反対に、本来は強者であるにもかかわらず弱者戦略を選ぶと、市場拡大のチャンスを逃しやすくなります。とくに成長フェーズにある企業は、戦略の過渡期にあるため、定期的なポジショニングの見直しが必要です。
また、戦略を途中で変える場合には、現場への共有や方向性の再設計を怠ると混乱を招くこともあります。営業戦略は単独では成立せず、組織全体との連動が求められます。リスクを回避するには、外部環境の変化も加味した継続的な検証が不可欠です。
営業活動で使えるランチェスター戦略の実践手法

ランチェスター戦略を理解するだけでは、成果にはつながりません。実際の営業現場に落とし込んでこそ、価値が発揮されます。とくに限られた人員や時間のなかで成果を上げるためには、現場で即使える具体的な手法の導入が重要です。ここでは、ターゲティングや関係構築、プロセス設計など、営業担当者が取り組みやすい内容を中心に紹介します。
ターゲットの細分化と集中戦略
営業活動において、対象顧客の選定が曖昧なままだと、どれだけアプローチを重ねても成果が見込めません。そのためには、まず市場を細分化し、自社の強みと親和性の高い領域を選び出すことが求められます。たとえば、業種別や企業規模別、課題別にセグメントを切り、それぞれに合ったアプローチを検討します。
そして、最も効果が見込まれるグループに絞り込んでリソースを集中させることで、営業効率を飛躍的に高めることが可能です。集中戦略は、とくに弱者の立場にある企業にとって有効です。
顧客のニーズが明確に定まっている場合は、提案内容にも反映しやすく、受注率の向上にも直結します。結果として、少ない営業回数でも関係性を築くことができるようになります。
見込み顧客との関係構築を重視する
売上につながる営業には、単なる訪問回数よりも、相手との信頼関係の構築が欠かせません。とくに初回接点では、顧客が抱える課題や期待を丁寧に引き出す姿勢が重要です。信頼形成には継続的な接触と価値提供が必要であり、そのためのコミュニケーション設計が求められます。
たとえば、提案内容に関連した業界情報を定期的に共有したり、ニーズに合わせたサンプルや事例を紹介したりするなど、個別対応が有効です。また、ヒアリングを通じて得た情報は、社内で共有しやすい形に整理し、次回訪問に活かす工夫も必要です。
単発のアプローチではなく、顧客と共に成長する姿勢を持つことで、長期的な関係構築が可能になります。営業成果の持続性を高めるには、こうした地道な積み重ねが不可欠です。
「4回訪問の原則」を活かすプロセス設計
新規開拓においては、1回の訪問で結果が出ることは稀です。むしろ、複数回の接触を前提としたプロセスをあらかじめ設計しておくことが、成約率向上の鍵になります。とくに有効とされているのが「4回訪問の原則」です。
1回目は認知を得るための導入、2回目で関心を引き出し、3回目で具体的な課題共有、4回目で提案およびクロージングという段階を踏む方法です。各ステップで目的を明確にし、進捗に応じて内容を調整することで、無駄な訪問を減らすことができます。
また、この設計により営業担当者の活動にも一貫性が生まれ、組織全体でのナレッジ共有も容易になります。成果が出ない要因の多くは計画の不在にあるため、こうしたモデルを取り入れることは有効です。
一点突破型の差別化提案を展開する
市場全体で突出することが難しい場合でも、特定分野に特化した提案であれば優位に立つことが可能です。この発想をもとに、一点突破型の営業戦略が注目されています。
まずは、自社が他社よりも優れている機能やサービス領域を明確にします。次に、その特徴が活きる業種やユースケースを洗い出し、該当するターゲットに絞ってアプローチを行いましょう。提案資料や営業トークでも、この強みが中心となるよう構成し、競合との違いを定量的に伝えることがポイントです。
また、顧客が抱える課題に対して、自社の特化領域がどのように解決に寄与するかを具体的に示すことで、説得力が増します。限られた範囲で成果を最大化するには、こうした専門性を武器にした訴求が効果的です。
営業KPIと成果を可視化する工夫
営業活動の質を高めるには、行動と成果を数値で把握できるようにすることが必要です。そのためには、KPIの設定とその定期的なレビューが欠かせません。たとえば、訪問数・商談数・提案件数といった量的指標に加え、商談化率・成約率などの質的指標も組み合わせると、活動の全体像をより明確に把握できます。
また、これらのデータは営業マネジメントにも活用でき、組織としての改善アクションにつなげることが可能です。さらに、CRMや営業支援ツールを活用することで、日々の活動を可視化しやすくなります。
数値をもとにした振り返りを行うことで、属人化のリスクを減らし、再現性のある営業力を育てることができます。目標達成に向けた地道な改善には、こうした可視化の仕組みが欠かせません。
ランチェスター戦略を支える営業フレームワークとツール

営業戦略の立案と実行において、再現性を持たせるには理論だけでなく仕組み化も不可欠です。とくにランチェスター戦略のような構造的アプローチでは、分析・計画・運用を一貫して支援するフレームワークとツールの導入が成果を左右します。ここでは、営業活動の精度と効率を高めるために活用されている代表的な手法やシステムについて紹介していきます。
あわせて、営業戦略に活用できるフレームワークについて、もう少し詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
営業戦略とは?具体的な立て方とポイント、7つのフレームワークを紹介
SWOT分析をベースに戦略を設計する
営業戦略を考えるうえで、社内外の要因を整理し方向性を見出す作業は欠かせません。その際に有効とされるのがSWOT分析です。この分析では、下記の4つの要素を軸に整理を行います。
- Strength(強み)
- Weakness(弱み)
- Opportunity(機会)
- Threat(脅威)
たとえば、自社の強みとして「価格競争力」や「専門知識」が挙げられる一方で、弱みとして「営業人員の不足」や「知名度の低さ」が見つかる場合があります。情報をもとに戦略を構築することで、現実的かつ実行可能な計画を立てやすくなるでしょう。
さらに、機会や脅威といった外部環境を意識することで、市場の変化にも柔軟に対応できるようになります。定期的に見直すことで、戦略の軌道修正も容易になります。
競合とのポジションを明確化するMECE原則
営業活動において、誰を狙うか、何を提供するかが不明確なままでは成果につながりません。ここで活用できるのが、要素を漏れなく重複なく分類するMECE(ミーシー)原則です。
- Mutually(お互いに)
- Exclusive(重複せず)
- Collectively(全体に)
- Exhaustive(漏れがない)
この手法では、顧客層や提案内容、課題領域などを体系的に整理することで、重複したアプローチや抜け漏れのある営業施策を防ぐことが可能です。とくに複数人で営業を行っている組織では、ターゲットの被りや対応漏れをなくすうえで有効に機能します。
また、セグメントごとの成果も可視化しやすくなり、PDCAの精度が向上します。営業戦略の立案段階からこの考え方を取り入れることで、設計精度が高まり、実行における一貫性を保ちやすくなるでしょう。
CRM/SFAツールで営業活動を管理する
営業成果の可視化や属人化の防止には、活動の管理と記録が重要です。そこで活躍するのが、CRM(顧客関係管理)およびSFA(営業支援)ツールです。これらのツールを導入することで、顧客情報や商談履歴、進捗状況を一元的に管理できるようになります。
また、営業活動の質や頻度を数値で把握できるため、問題の早期発見や改善策の検討にもつながります。加えて、過去の提案内容や対応履歴を参照できることで、営業担当者が変わってもスムーズな対応が可能になります。
属人的になりがちな営業活動をチーム全体で支える体制が整うため、組織としての営業力が底上げされます。戦略的な営業展開を進める上で、こうしたツールの活用は欠かせません。
顧客理解を深めるCRMツールについてもう少し詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
MA・SFA・CRMの違いとは?導入すべきツールと効果的な使い方を徹底解説
セールスDXによる強化施策を取り入れる
営業の現場では、ツールの導入だけでなく、業務全体をデジタル化する取り組みが進んでいます。いわゆるセールスDX(デジタルトランスフォーメーション)です。単なる情報管理にとどまらず、リード獲得から商談化、クロージングに至るまでのプロセスを自動化・最適化することが可能になります。
たとえば、顧客の行動履歴をもとにしたスコアリングや、提案内容の自動レコメンドなどがそれにあたります。さらに、リアルタイムでのダッシュボード共有により、営業マネジメントの精度も向上するでしょう。従来の経験や勘に頼る営業から、データを軸とした営業へと移行することにより、属人性を排除し、成果の安定化を実現できます。
組織で戦略を共有し、実行力を高める
優れた戦略があっても、それが組織全体に伝わっていなければ、期待する成果は得られません。そのため、営業戦略を社内で共有し、現場で実行できる体制を整える必要があります。具体的には、営業部門だけでなく、マーケティングやカスタマーサクセスとも連携した共有会を実施したり、定期的なKPIレビューを行ったりする仕組みが重要です。
また、行動指針やトークスクリプトなどをマニュアル化することで、誰が担当しても一定の品質で営業活動を行える状態が理想です。加えて、フィードバックを受け取るチャネルを確保しておくことで、現場の声をもとに戦略を柔軟に見直すことも可能になります。戦略の実行力を高めるには、情報共有と運用の仕組み化が必須です。
営業戦略でランチェスター戦略を導入した企業事例

理論や手法を学んだあとに求められるのは、実際のビジネス現場でどう成果を出しているかという事例です。成功企業がどのようにランチェスター戦略を応用し、競争のなかでシェアを拡大したのかを把握することにより、自社の営業活動にも活かせる具体的なヒントが得られます。
ここでは、業界や規模の異なる5社の事例を通じて、戦略の活用実態を確認していきます。
HISに学ぶ弱者の逆転劇
旅行業界で後発企業としてスタートしたHISは、まさにランチェスター第一法則の体現ともいえる戦略を実行しました。大手が支配する既存市場には踏み込まず、低価格帯のパッケージツアーに絞り込み、特定の層に集中した提案を行いました。
人件費のかからない小型店舗の多店舗展開によってコスト競争力を確保し、差別化された価格訴求で若年層を中心に支持を集めたのです。集中戦略により、短期間で市場にインパクトを与え、結果的には全国的な知名度を確立しています。
限られた経営資源でも工夫次第で十分に戦えることを証明した事例といえます。リソースの集中と差別化が、いかに競争優位につながるかを示す好例です。
アパホテルの地域密着型営業戦略
ホテル業界で強者に立ち向かう存在として知られるアパホテルも、ランチェスター戦略を巧みに活かしている企業の一つです。全国展開を進める中でも、出店エリアを絞り込み、ビジネス利用客の多い都市部を中心に営業リソースを集中させました。
とくに立地と利便性にこだわった開発方針と、統一感のあるブランドづくりにより、顧客のロイヤリティを高めています。また、自社予約サイトの強化やクーポン施策など、直接顧客との接点を増やす取り組みによって、他社に依存しない営業体制を構築しているのです。
このような独自戦略により、資本力で劣るにもかかわらず、高稼働率を実現しています。集中と一貫性の徹底が成果を支えています。
ピーターパンの限定集中による成功
千葉県内で店舗展開を進めているベーカリーチェーン「ピーターパン」は、大手チェーンとの価格競争に巻き込まれずに成果を上げている例として注目されています。同社はエリアと顧客層を明確に設定し、ローカルな需要に合わせた商品ラインナップや接客スタイルを徹底しました。
さらに、パン作りの工程を一部オープンにするなど、体験型の工夫も取り入れています。加えて、地域密着型のイベントや情報発信によって、来店頻度とブランド愛着を高めることに成功しました。
店舗を拡大するよりも、既存店舗の深耕とファン作りに力を注ぐことで、高い収益性を維持しています。ニッチ戦略の実践例として、営業活動にも通じる多くの学びがあります。
QBハウスの効率的シェア獲得モデル
理美容業界で短時間・低価格を武器にシェアを伸ばしたQBハウスも、ランチェスター戦略の成功事例に数えられます。同社は標準化された施術プロセスと価格設計を用いることで、大手サロンとは異なる市場ポジションを築きました。
また、駅構内や商業施設への出店戦略により、通勤途中の需要を的確に捉えることに成功しています。スタッフ教育を通じたサービス品質の均一化にも力を入れており、どの店舗でも一定水準の体験を提供できる体制を確立しました。
顧客ニーズを踏まえた一点突破型の戦術により、競争が激しい市場においても着実にシェアを獲得しています。営業戦略においても、標準化とスピードを活かす仕組みづくりは見習うべき要素です。
成果を出す企業に共通するポイントとは
各企業の事例を振り返ると、成功を導くランチェスター戦略にはいくつかの共通点があります。第一に、自社のポジションを明確に認識していること。次に、対象とする市場や顧客層を極力絞り込み、集中してアプローチを行っている点です。そして最後に、選んだ戦術を組織全体で徹底して運用しているという共通項が見られます。
いずれも、ただの思いつきの営業施策ではなく、理論と実行の裏付けがあるからこそ成立している要素です。営業戦略で成果を出したい企業にとって、これらの視点は非常に参考になるでしょう。明確な戦略と一貫した実行力が、継続的な成果を生む原動力になります。
まとめ
ランチェスター戦略は、自社の立ち位置を見極めたうえで、限られたリソースを最適に配分するための有力な指針です。とくに営業分野においては、戦術の誤りが大きな機会損失につながるため、戦略設計の重要性が増しています。
本記事では、理論の理解だけでなく、具体的な営業手法や成功事例まで網羅的に解説しました。貴社の営業活動にランチェスター戦略を取り入れることで、より確度の高い成果が期待できるでしょう。
セールスアセットでは、業務を請け負うだけでなく、貴社のビジネスモデルや方針を深く理解したうえで、成果につながる営業戦略の立案から実行、さらに将来的な内製化まで一貫して支援が可能です。
これひとつで
営業参謀のすべてが分かる!
BtoB営業組織立ち上げ支援サービスの内容や導入事例、料金プランなど営業参謀の概要がまとめられた資料をダウンロードいただけます。



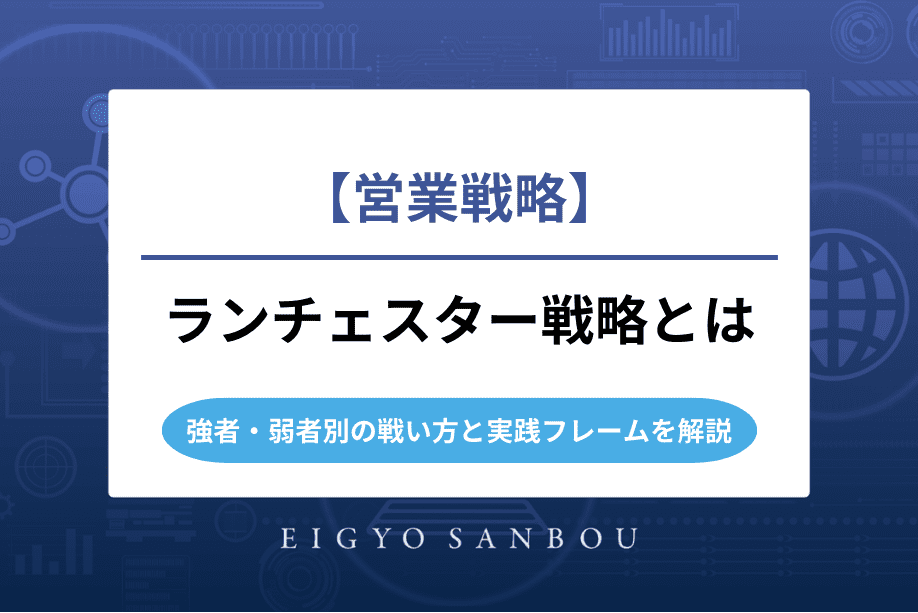
 ツイートする
ツイートする シェアする
シェアする LINEで送る
LINEで送る URLをコピー
URLをコピー