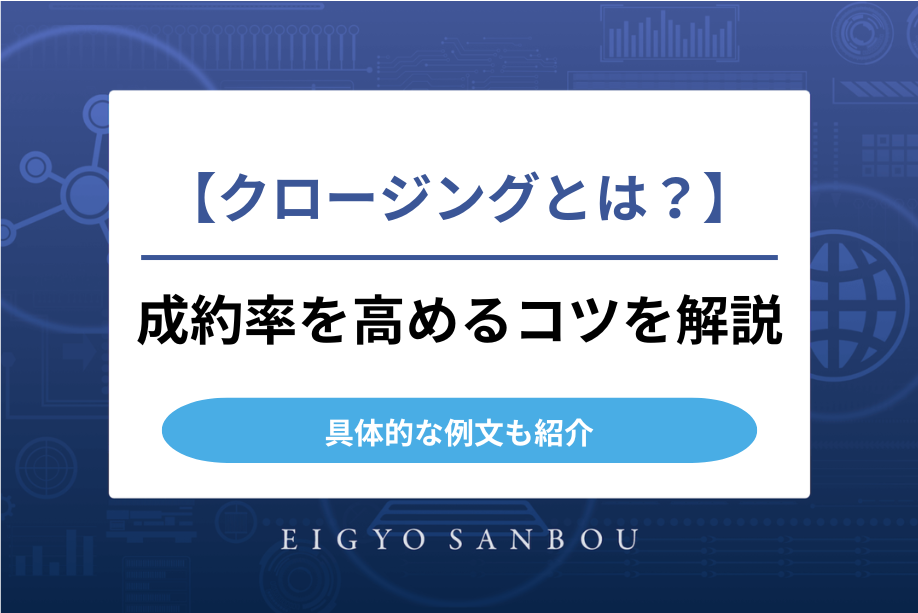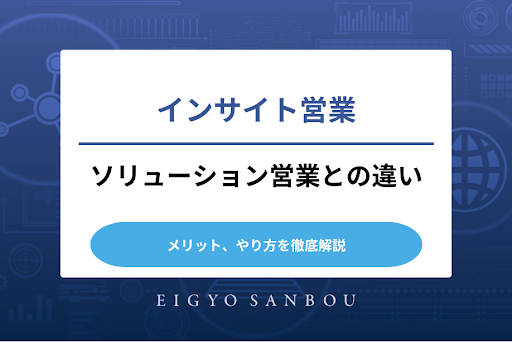営業で成果を出すうえで、ただ商品を説明するだけでは不十分です。顧客の悩みや期待を正しく理解し、的確な提案につなげるには、質の高いヒアリングが求められます。
本記事では、営業ヒアリングの目的や基本の流れ、実践で役立つフレームワーク、効果的に進めるための工夫まで体系的に紹介します。すぐに実践できるポイントも解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
▶︎貴社の事業成長を営業の側面からサポートするパートナーサービス『営業参謀』についてはこちら
営業でお悩みのことありませんか?
目次
営業ヒアリングとは
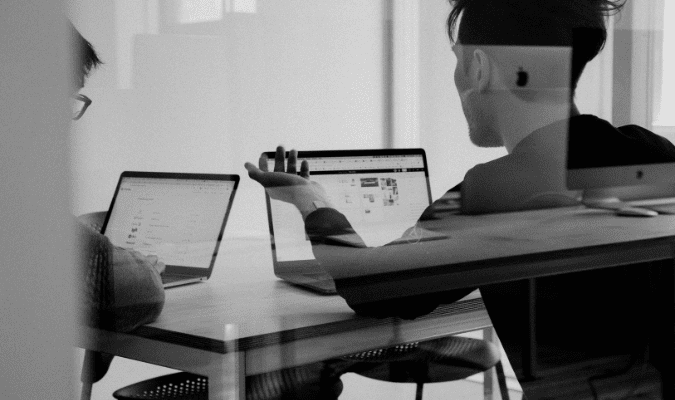
営業ヒアリングは、顧客の真の課題や意向を探るための重要な対話のプロセスです。以下では、ヒアリングの目的と営業全体の流れについて解説します。
営業ヒアリングの目的
営業ヒアリングの主な役割は、表面的な要望だけでなく、その背景にある真の課題や期待を引き出すことにあります。顧客が現在どのような状況にあり、どんな困りごとを抱えているのかを丁寧に把握することで、的を射た提案が可能です。
また、適切なヒアリングは、顧客との信頼関係を築くうえでも非常に有効です。会話を通じて「この人は自分の話を理解しようとしてくれている」と感じてもらえれば、自然と警戒心がほぐれ、話してくれる情報の質も深まっていきます。
関連記事:インサイト営業とは?ソリューション営業との違い、メリット、やり方を徹底解説
一般的な営業活動の流れ
事前の準備で相手の業界や会社状況を把握し、仮説を立てたうえで面談に臨みます。その後の対話を通じて、顧客の課題やニーズを深掘りし、必要に応じて商品やサービスを提案していくのが基本的な流れです。
クロージングに向けては、相手の不安や懸念点を丁寧に解消しながら、納得のうえで合意に至るよう誘導していきます。
すべてのフェーズで求められるのは、相手の立場に寄り添う姿勢と、的確なヒアリング力です。疎かにすれば、どれほど魅力的な提案も空回りしてしまう可能性があります。
関連記事:営業におけるクロージングとは?成約率を高める8つのコツや例文を解説
営業ヒアリングのコツ

効果的なヒアリングを行うには、話す内容そのものよりも、聞く姿勢や伝え方に工夫が必要です。ここでは、商談の質を高めるために押さえておきたい4つの視点をご紹介します。
自分が話すことよりも顧客の話を聞くことを重視する
商談中、営業側が多くの情報を提供したくなる気持ちは自然なものですが、顧客が本当に必要としているのは自分の話に耳を傾けてくれる相手です。
相手の発言に集中し、相槌や表情、リアクションなどを交えながら聞くことで、顧客も安心して話を続けてくれるようになります。
さらに、相手の言葉を遮らず最後まで聞くことで、想定していなかったニーズや課題を引き出せることがあります。こうした傾聴の積み重ねが、信頼と共感につながる土台を築いていくのです。
関連記事:営業ノウハウとは?成果を上げるための営業スキルについて
話の主語を顧客側にする
ヒアリング中の会話では、「弊社では〜」「当社の商品は〜」といった表現が増えがちですが、顧客にとって重要なのは自分自身の状況や課題に焦点を当てた会話です。
そこで意識したいのが、主語を自社ではなく顧客側に置き換える工夫です。たとえば「どのような点に不便を感じていますか?」や「今後どんな変化を望まれていますか?」といった問いかけによって、顧客の立場に寄り添ったコミュニケーションが可能になります。
主語の設定を変えるだけで、相手は「自分のことを理解しようとしてくれている」と感じやすくなり、関係構築にも良い影響を与えるでしょう。
商品・サービスがイメージしやすいように話す
魅力的な提案であっても、抽象的な説明だけでは顧客の理解を得るのは難しいものです。自社の商材を紹介する際には、具体的な事例や導入後の変化などを交えながら説明することが有効です。
「こうしたお悩みを持つ企業で〜のように改善されました」といったストーリー性のある伝え方をすることで、相手が状況を自分ごととして捉えやすくなります。頭の中で使う場面をリアルに想像できれば、商品への興味や検討意欲も自然と高まりやすくなります。
「現在→過去→未来」の流れを意識する
ヒアリングを進める際にとくに有効なのが、「現在どのような状況か」「これまでにどんな経緯があったか」「これからどうなりたいか」という流れに沿った対話です。順番に話を展開することで、顧客自身が無意識に抱えている課題や希望に気づくきっかけになります。
また、時間軸を意識したやり取りによって、相手の意向や優先順位も明確になり、適切な提案にもつなげやすくなるでしょう。
営業ヒアリングの基本的な流れ

商談を円滑に進めるには、段階ごとに適切な対応を取ることが欠かせません。ここでは、成果につながる営業ヒアリングの流れを5つのステップに分けてご紹介します。
事前準備をする
商談に臨む前には、相手企業に関する情報を収集し、目的や業界特性を把握しておくことが肝心です。どのような事業課題を抱えているか、競合状況はどうかといった外部要因を整理することで、会話の方向性に仮説を立てやすくなります。
また、訪問の目的や聞きたい内容をあらかじめ明確にしておくと、無駄のない対話が可能になります。営業活動において準備は地味ながらも極めて重要な要素です。
アイスブレイクをする
面談の初期段階では、いきなり本題に入るよりも、緊張感を和らげる会話が有効です。天気や時事、共通点に触れる雑談などを通じて、相手との距離感を縮めることを意識しましょう。
とくに初対面の場合は、第一印象がその後のやり取りに大きく影響します。短い時間でも、笑顔や相づちなどのリアクションを交えることで相手も心を開きやすくなります。円滑なヒアリングのスタートは、アイスブレイクの出来栄えにかかっているといえるでしょう。
アイスブレイクについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。
営業のアイスブレイク鉄板ネタ|不要なパターンや避けるべき話題、ポイント
ヒアリングをする
本題に入ったら、相手の話に耳を傾けながら情報を丁寧に引き出していきます。
表面的な事実だけでなく、その背景にある意図や課題感まで把握することが重要です。効果的なヒアリングを行うためには、相手が話しやすくなるような順序や言葉遣いも求められます。
また、話のなかで浮かび上がる矛盾や不足情報には、深掘りする姿勢を見せましょう。顧客自身が気づいていなかった問題点を明らかにできれば、提案の説得力にもつながります。
プレゼンテーションをする
顧客の要望や課題が見えてきたら、それに応じた提案を行います。
ただし、この段階では商品の特徴を並べ立てるのではなく、ヒアリングで得た情報を踏まえて「相手にとっての価値」を伝えることが大切です。相手が具体的に導入後の姿を想像できるよう、事例や成果の提示を交えてストーリー仕立てにするのも効果的です。
一方的に伝えるのではなく、相手の反応を見ながら調整する柔軟さも忘れないようにしましょう。
クロージングをする
提案内容に一定の納得感が得られたら、最後は合意形成に向けた対話に入ります。ここでは、導入時期や決裁プロセス、他社との比較状況などを確認しながら、具体的な次の一手を提示することが求められます。
また、相手が不安を抱えている様子が見られる場合には、その原因を特定し、丁寧に解消する必要があります。焦って即決を迫るのではなく、相手の判断を尊重しつつ、自然な形で背中を押す姿勢が理想です。
成約は営業活動のゴールではなく、信頼関係の延長線上にある結果と捉えて向き合いましょう。
クロージングについて、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
営業におけるクロージングとは?成約率を高める8つのコツや例文を解説
営業ヒアリングシートの内容に盛り込むべき6つの項目

成約につなげる営業を実現するには、ヒアリング内容の記録と整理が重要です。ここでは、ヒアリングシートに記載しておきたい6つの観点について詳しく解説します。
1.現状・課題
顧客が今どのような状況に置かれているのかを把握することは、ヒアリングの出発点となります。
たとえば、業務上のボトルネックや現行システムの使いづらさといった声を引き出すことで、具体的な問題の輪郭が見えてきます。さらに、現場と経営層で認識のずれがないかを確認することも欠かせません。
目に見える課題だけでなく、顧客自身が言語化できていない悩みまで掘り下げられるかが、ヒアリングの成否を左右します。
2.自社商材への印象・疑問点
ヒアリング中には、顧客が自社の製品やサービスに対して抱いている印象を確認することも必要です。すでに何らかの情報を得ている場合、その理解にズレがないかを確かめましょう。
また、質問や不安の声があれば、商談の段階で丁寧に解消しておくことが理想的です。商品への興味や期待感だけでなく、懸念やハードルについても早い段階で共有することで、商談の方向性がより明確になります。
3.希望納期・スケジュール
導入を検討している時期や、社内でのプロジェクト進行のタイムラインについても確認が必要です。納期に対する意識は業界や企業によって異なり、提案の段階でずれがあると信頼を損なう可能性があります。
たとえば「なるべく早く」という回答であっても、実際には社内稟議や上長の承認が必要で時間を要するケースもあります。ヒアリング時にはスケジュールの背景や調整可能な範囲も含めてすり合わせておくと、無理のない進行計画が立てられるでしょう。
4.予算・希望価格
営業活動では、価格のすり合わせが避けて通れないポイントです。
ただし、いきなり「ご予算はどのくらいですか?」と尋ねるのは適切とはいえません。まずは、相手がどのような基準で金額を評価するのか、過去にどのような価格帯の製品を導入していたのかなど、間接的な情報からヒントを探るとスムーズです。
希望金額が明確に提示された場合には、予算内で最大限の価値を届けられるような提案を心がけましょう。価格だけに注目せず、対価としての効果も伝える姿勢が大切です。
5.意思決定の基準・検討部門・決裁者
顧客側で誰が導入の判断を担っているかを確認しないまま話を進めると、後々の承認プロセスで足止めを食らうことがあります。実際には複数の部署が関与していたり、決裁までに段階的な承認が必要だったりするケースも珍しくありません。
誰がどのような評価軸を持って導入の可否を判断するのかを把握しておくことで、提案内容に重点を置くべきポイントが見えてくるでしょう。
6.他社の検討状況
競合製品との比較がすでに進んでいる場合には、顧客がどのような観点で選定を進めているのかを確認しておくとよいでしょう。競合に何を評価しているのか、逆にどの点に不満があるのかといった情報を収集することで、自社の提案がより有利になる着眼点が見えてきます。
また、顧客の意思決定の緊急度や検討フェーズを見極めるためにも、他社との比較状況は有益なヒントになります。単に競合の名前を聞くだけでなく、評価軸や選定基準まで踏み込む姿勢が求められます。
営業ヒアリングに役立つフレームワーク4選

営業活動で的確な情報を引き出すには、質問の設計が重要です。ここでは、商談の質を高めるために活用したい代表的な4つのフレームワークを解説します。
| フレームワーク名 | 概要 | 活用目的 | 特徴 |
| 3C分析 | 顧客・競合・自社の3要素から状況を整理する分析手法 | 顧客の課題や市場環境を把握し、最適な提案を組み立てるために使用 | 業界構造や競合動向、自社の強みを横断的に把握できる |
| BANT情報 | 予算・決裁者・ニーズ・導入時期の4項目で商談の質を評価する枠組み | 案件化やクロージングの確度を見極め、優先度の高い顧客を見極める目的で使用 | 購買の実現性を可視化でき、的確なアプローチ設計に役立つ |
| MEDDICモデル | 商談を成功に導くための6項目で構成される高度な営業モデル | 特にBtoBの複雑な案件で、意思決定プロセスや評価基準を深く理解するのに有効 | 組織構造や成果指標まで掘り下げられ、提案の説得力が増す |
| SPIN話法 | 状況→問題→示唆→解決の順に質問を展開していく営業技法 | 顧客の潜在ニーズを自然に引き出し、購買意欲を高めるために活用 | 会話の流れに沿って顧客の気づきを促す構成が、説得力ある提案につながる |
1.3C分析
- 市場・顧客(Customer)
- 競合(Competitor)
- 自社(Company)
上記の3つの視点から状況を捉えるフレームワークです。
営業においては、顧客の抱える課題だけでなく、その背景にある業界構造や競合動向、自社の強みとの重なりを整理するのに役立ちます。ヒアリングでは、顧客がどのような立場で競合と差別化しようとしているのか、現場と経営層で見ている視点にズレはないかといった切り口で質問を組み立てましょう。
2.BANT情報
- 予算(Budget)
- 決裁者(Authority)
- ニーズ(Needs)
- 導入時期(Timeline)
上記の頭文字を取った営業の基本項目です。この枠組みは、商談の優先度を判断するうえで重宝します。
たとえば、ニーズが明確でも予算が確保されていない、あるいは決裁者と接点が持てていない場合、クロージングまで時間を要する可能性があります。ヒアリングでは、直接的な質問だけでなく、相手の回答から情報を引き出す工夫が求められます。
BANT情報を把握することは、無駄な提案を避け、的確なフォローアップを行うための出発点になるのです。
3.MEDDICモデル
MEDDICは、以下を意味する高度な営業支援モデルです。
- 計測基準(Metrics)
- 経済的購買責任者(Economic Buyer)
- 意思決定基準(Decision Criteria)
- 意思決定プロセス(Decision Process)
- 課題(Identify Pain)
- 提案の関連性(Champion)
とくにBtoBの大型商談では、意思決定の構造が複雑なケースも多いため、このモデルの有効性が発揮されます。
ヒアリングでは、顧客のビジネスゴールに対して、どのような成果指標が設定されているかを掘り下げる必要があります。
また、購買プロセスや担当者の評価軸に沿った説明ができれば、提案の説得力は一層高まるでしょう。情報の精度と深度を求める場面で、MEDDICは強力な武器になるはずです。
4.SPIN話法
SPIN話法は、以下の順で質問を展開する営業手法です。
- 状況(Situation)
- 問題(Problem)
- 示唆(Implication)
- 解決(Need-Payoff
上記の順序で進めることで、顧客の潜在ニーズを引き出し、購買意欲を自然に高めていけます。
状況を確認する段階では事実ベースの情報を、問題に焦点を移す際には感情や困りごとを引き出す質問が効果的です。その後、問題を放置した場合の影響を伝え、最後に導入後の利点をイメージさせることで、相手は前向きな判断をしやすくなります。
SPIN話法について、詳しく知りたい方は以下の記事をご一読ください。
SPIN話法とは?具体例や成功させるコツを解説
営業ヒアリングをスムーズに進めるために

ヒアリングの精度を高めるには、実践的なスキルだけでなく日々の取り組みも重要です。ここでは、現場で役立つ3つの具体的な工夫をご紹介します。
研修・ロールプレイングを行う
営業ヒアリングの質は、日常的な訓練によって大きく左右されます。とくにロールプレイングは、理論だけでは習得しにくい対話力や応答力を実践形式で磨ける手段です。
さまざまな業種や商材を想定した設定で行うことで、対応力の幅を広げることも可能でしょう。本番さながらのシミュレーションを繰り返すことで、実際の商談においても余裕を持って話を進められるようになります。
トップセールスに同行する
トップセールスのヒアリングは、単なる質問の羅列ではなく、相手に応じた空気の読み方や間の取り方に特徴があります。同行することで、その場の空気感や顧客との関係性の築き方、質問の切り出し方といった細かな部分を体感できるでしょう。
また、商談後に振り返りを行うことで、自分との違いに気づき、改善点を明確にできます。実力者の「型」を観察し、それを自分なりにアレンジする姿勢が、スキルの底上げにつながります。
営業支援ツール(SFA)を利用する
営業活動の中で得られた情報を蓄積・活用するためには、ツールの導入も欠かせません。SFA(Sales Force Automation)を活用すれば、ヒアリング内容の記録を整理しやすくなり、次回の訪問時やチーム内での共有もスムーズに行えます。
また、過去の商談履歴や進捗状況を一覧できることで、話の重複や聞き漏れを防ぐとともに、的確なアプローチを選びやすくなります。適切なツールの運用が、ヒアリングの精度をさらに高めてくれるでしょう。
まとめ
営業ヒアリングは、顧客の真意を把握し、信頼関係を築くうえで欠かせないプロセスです。目的を理解したうえで段階的に進めれば、ニーズを的確に捉えた提案が可能になります。
また、ヒアリングシートの活用やフレームワークの導入によって、聞き漏れや情報の偏りも防げます。さらに、ロールプレイや営業支援ツールなどを活用すれば、実践の場でも安定した成果が期待できるでしょう。
日々の営業活動の中でヒアリングの精度を高めていくことが、信頼を得る営業スタイルへの第一歩となります。今回紹介した内容を参考に、ぜひ実践に取り入れてみてください。
セールスアセットでは、貴社のビジネスモデルや方針を深く理解したうえで、成果につながる営業戦略の策定から実行、将来的な内製化の支援まで一貫した対応が可能です。
事業の成長を共に目指すパートナーとして、実行力と提案力の両面から支援します。
【貴社の事業成長を営業の側面からサポートするパートナーサービス『営業参謀』の資料のダウンロードはこちら】
これひとつで
営業参謀のすべてが分かる!
BtoB営業組織立ち上げ支援サービスの内容や導入事例、料金プランなど営業参謀の概要がまとめられた資料をダウンロードいただけます。



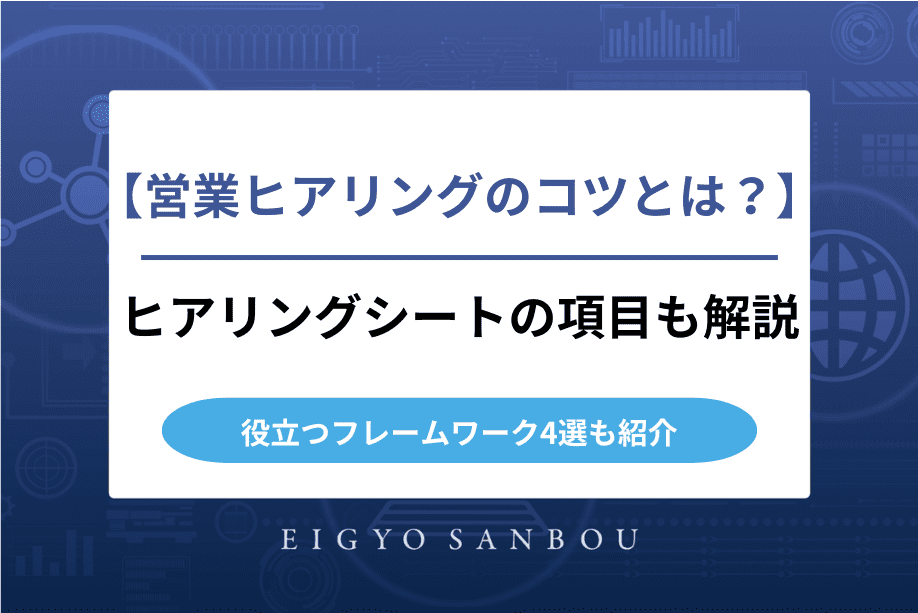
 ツイートする
ツイートする シェアする
シェアする LINEで送る
LINEで送る URLをコピー
URLをコピー